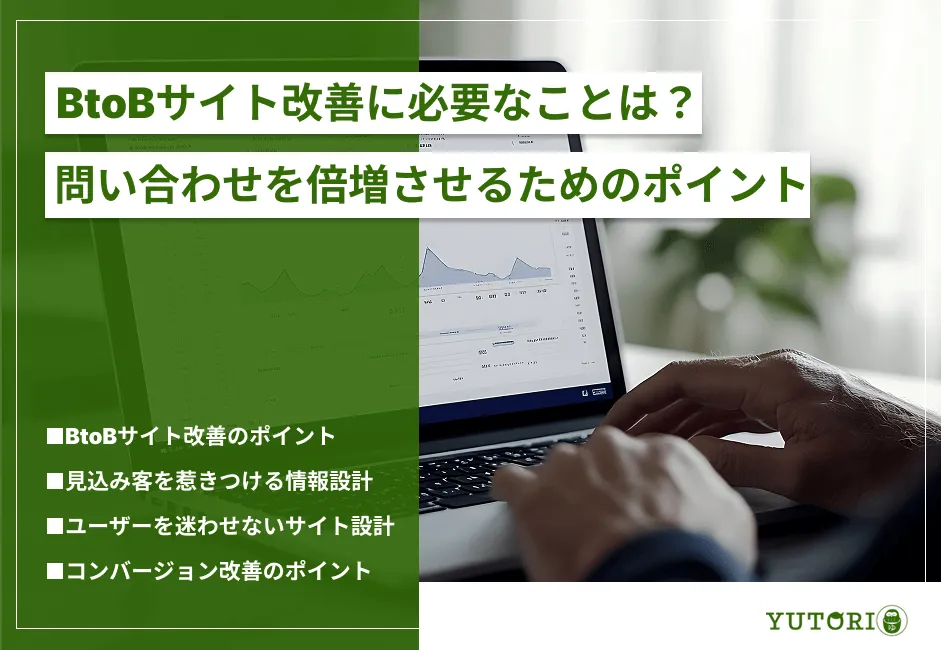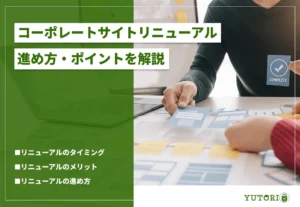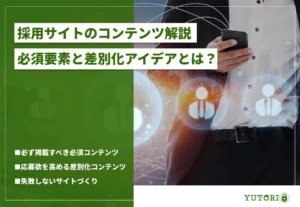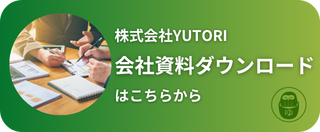企業の顔とも言えるBtoBサイト。しかし、「アクセスはあるのに、一向に問い合わせが増えない」「サイトが営業の役に立っている実感がない」といった悩みを抱えるWEB担当者は少なくありません。BtoBサイトの成果は、単に見た目を良くするだけでは向上しません。顧客となる企業の担当者が、どのような情報を求めて、どのようなプロセスで購買を決定するのかを深く理解し、戦略的にサイトを設計・改善していく必要があります。
本記事では、BtoBサイトの問い合わせを倍増させることを目標に、改善の成果を左右する「戦略設計」から、見込み客を惹きつける「コンテンツ改善」、直感的な「UI/UXデザイン」、そして問い合わせへの最後の壁を突破する「コンバージョン改善」まで、具体的なポイントを網羅的に解説します。
目次
BtoBサイト改善の成果を左右する3つのポイント
具体的なコンテンツ制作やデザイン改修に着手する前に、まず取り組むべき最も重要なフェーズが「戦略設計」です。誰に、何を、どのように伝えるのかというサイトの根幹が定まっていなければ、どんなに優れたコンテンツやデザインも的外れなものになってしまいます。ここでは、改善の成否を分ける土台となる3つの戦略的ポイントを解説します。
ターゲットの再定義
BtoBサイト改善の第一歩は、「誰に情報を届けたいのか」を明確にすることです。そのために有効な手法が「ペルソナ」の設定です。ペルソナとは、自社の理想的な顧客像を、具体的な一人の人物かのように詳細に設定したものを指します。
BtoBの購買プロセスは、情報収集者、担当者、決裁者など複数の人物が関わるため複雑です。だからこそ、「どのような部署の、どの役職の人物が、どんな業務課題を抱え、どのように情報を収集し、何を決め手に導入を判断するのか」を深く掘り下げてペルソナを設定することで、発信する情報の精度が格段に上がります。このペルソナが、今後のコンテンツ企画やサイトデザインの全ての判断基準となります。
顧客の行動を可視化する「バイヤージャーニーマップ」の策定
ペルソナが設定できたら、次はそのペルソナが自社の製品やサービスを認知し、最終的に購買に至るまでのプロセスを可視化する「バイヤージャーニーマップ」を作成します。一般的に、顧客は「認知」「興味・関心」「比較・検討」「導入・購買」といった段階を経て意思決定を行います。
この各段階で、ペルソナが「どのような感情を抱き、どのような情報を求めて、どのような行動をとるのか」を時系列で描き出すのがバイヤージャーニーマップです。例えば、「認知」段階では課題に気づくためのブログ記事、「比較・検討」段階では他社との違いがわかる導入事例や詳細な資料が求められます。
このマップを作成することで、サイトに必要なコンテンツや、各ページで促すべき行動が明確になり、顧客の思考プロセスに寄り添ったサイト設計が可能になります。
競合サイト分析から学ぶべきポイントと自社の強みの見つけ方
自社の顧客を理解すると同時に、市場における自社の立ち位置を客観的に把握することも不可欠です。競合他社がどのようなメッセージを打ち出し、どのようなコンテンツで顧客にアプローチしているのかを分析しましょう。
分析すべきは、デザインの良し悪しだけではありません。「どのようなキーワードで上位表示されているか」「導入事例ではどのような価値を訴求しているか」「どのようなCTA(行動喚起)を設置しているか」などを多角的に調査します。競合の強みと弱みを把握した上で、顧客、競合、自社の3つの視点から、「自社だけが提供できる独自の価値」は何かを再定義します。この独自の強みこそが、サイト全体のメッセージングの核となります。
コンテンツ改善のポイント
サイトの戦略が固まったら、次はその戦略を具体化する「コンテンツ」の改善に移ります。特にBtoBにおいては、製品やサービスの価格が高額で、導入の意思決定が慎重に行われるため、顧客からの「信頼」を獲得することが極めて重要です。
ここでは、信頼を醸成し、質の高い見込み客(リード)を惹きつけるための情報設計について解説します。
専門性と権威性を示す(E-E-A-T)
E-E-A-Tとは、Googleがサイトの品質を評価する上で重視する概念で、「経験(Experience)」「専門性(Expertise)」「権威性(Authoritativeness)」「信頼性(Trustworthiness)」の頭文字をとったものです。BtoBサイトでは、このE-E-A-Tをコンテンツで示すことが、検索エンジン評価とユーザーからの信頼獲得の両面で重要になります。
具体的な施策として、コラムやブログ記事には、その分野に精通した社員の顔写真とプロフィール(経歴や資格など)を著者情報として明記しましょう。さらに、業界の有識者や外部の専門家に記事内容を監修してもらい、その事実をサイト上に記載することも、権威性を高める上で非常に有効です。
導入事例・実績紹介の正しい見せ方
導入事例は、BtoBサイトにおける最強のコンテンツの一つです。しかし、単に導入企業名と実績を羅列するだけでは、見込み客の心には響きません。重要なのは、読んだ顧客が「これはまさに自社のことだ」と「自分ごと化」できるストーリーとして提示することです。
優れた導入事例には、「導入前の具体的な課題」「サービスを選んだ決め手」「導入プロセスで工夫した点」「導入後に得られた定量的・定性的な成果」といった要素が具体的に描かれています。ターゲットとなるペルソナに近い業種や企業規模の事例を複数用意することで、見込み客は自社での成功イメージを具体的に描くことができ、問い合わせへのモチベーションが高まります。
ホワイトペーパーの配置
サイトを訪れる全てのユーザーが、今すぐ製品の導入を検討しているわけではありません。多くは、まだ漠然とした課題を抱えている段階や、情報収集を始めたばかりの段階にいます。こうした潜在的な見込み客にアプローチするために有効なのが、彼らの課題解決に直接役立つ「お役立ち資料」です。例えば、「業界の最新動向レポート」「〇〇業務を効率化するノウハウ集」といったホワイトペーパーを用意し、無料でダウンロードできるようにします。
製品への関心がまだ高くない層の連絡先(リード情報)を獲得でき、その後のメールマーケティングなどで継続的に関係を構築していくことが可能になります。これらの資料は、関連するブログ記事の末尾や、サービスの概要ページなどに戦略的に配置することが重要です。
営業部門との連携
サイトコンテンツの質を飛躍的に高めるヒントは、社内に眠っています。それは、日々顧客と直接対話している「営業部門」が持つ情報です。営業担当者は、顧客が抱えるリアルな悩み、よくある質問、導入をためらう理由、競合と比較されるポイントなど、貴重な「生の声」を誰よりも知っています。
WEB担当者は、定期的に営業部門へヒアリングを行い、これらの情報をコンテンツに反映させましょう。「よくあるご質問(FAQ)」ページの拡充、顧客の懸念を払拭するコラム記事の作成、競合比較資料の作成など、現場の声を活かすことで、コンテンツはより実践的で説得力のあるものへと進化します。
UI/UXデザイン改善のポイント
どれだけ優れたコンテンツを用意しても、サイトが使いにくかったり、情報が見つけにくかったりすれば、ユーザーはすぐに離脱してしまいます。UI(ユーザーインターフェース:接点)とUX(ユーザーエクスペリエンス:体験)の改善は、ユーザーにストレスを与えず、スムーズに目的の情報へ導くために不可欠です。
ここでは、信頼感を醸成し、直感的な操作を可能にするサイト設計のポイントを解説します。
信頼性を伝えるデザインの原則
BtoBサイトのデザインは、奇抜さや派手さよりも、「誠実さ」「信頼性」「専門性」が伝わることが重要です。企業のブランドイメージを反映したコーポレートカラーを基調とし、サイト全体で一貫性のあるカラースキームを適用しましょう。
また、長文を読むことが多いBtoBサイトでは、可読性の高いフォントを選ぶことが基本です。文字サイズや行間にも配慮し、ユーザーが疲れにくいデザインを心がけます。情報を詰め込みすぎず、余白を効果的に活用したレイアウトは、コンテンツの視認性を高め、洗練された印象を与えます。
直感的なナビゲーション設計
ユーザーがサイト内で迷子にならないよう、どこに何の情報があるかが一目でわかるナビゲーション(メニュー)設計は極めて重要です。特に注意したいのが、メニューのラベル(名称)です。社内では当たり前に使っている専門用語や独自の製品名を避け、ユーザー(ペルソナ)が使うであろう一般的で分かりやすい言葉を選びましょう。
例えば、「弊社のソリューション」ではなく「課題から探す」、「製品ラインナップ」ではなく「製品・サービス一覧」といった具合です。また、サイトの階層構造はできるだけ浅くし、ユーザーが目的のページに3クリック以内でたどり着ける構成が理想とされています。
モバイルファーストとアクセシビリティへの配慮
近年、BtoBにおいても移動中や出先からスマートフォンで情報収集をするケースが増えています。PCだけでなく、スマートフォンやタブレットなど、あらゆるデバイスで快適に閲覧できるよう、レスポンシブデザインに対応することは今や必須条件です。
さらに、企業の公式サイトとして、Webアクセシビリティへの配慮も重要です。アクセシビリティとは、年齢や身体的な条件、利用環境にかかわらず、誰もが等しく情報にアクセスし、サービスを利用できることを指します。画像に代替テキストを設定する、十分なコントラスト比を確保するなど、基本的な配慮を行うことは、社会的責任を果たす上でも、ユーザー体験を向上させる上でも大切です。
表示速度の改善とSSL化
サイトの表示速度は、ユーザー体験に直接的な影響を与えます。ページの読み込みに3秒以上かかると、多くのユーザーは待ちきれずに離脱してしまうと言われています。表示速度の遅さは機会損失に直結するだけでなく、Googleの検索順位評価においてもマイナス要因となります。画像のファイルサイズを圧縮する、不要なプログラムを削除するなど、表示速度の改善は継続的に行いましょう。
また、サイト全体の通信を暗号化するSSL化は、セキュリティ対策として必須です。ユーザーの情報を安全に守るという姿勢を示すことは、企業の信頼性に関わります。SSL化はGoogleも推奨しており、SEO評価の面でも基本的な対策とされています。
コンバージョン改善のポイント
サイトを訪れた見込み客を惹きつけ、コンテンツに満足してもらった後、最終的なゴールである「問い合わせ」や「資料請求」といった行動へと導くための「最後の一押し」がコンバージョン改善です。ユーザーが行動を起こす直前の、心理的・物理的な障壁をいかに取り除くかが鍵となります。
CTA(行動喚起)ボタンの最適化
CTA(Call To Action:行動喚起)とは、ユーザーに具体的な行動を促すためのボタンやリンクのことです。「お問い合わせはこちら」「資料ダウンロード」などがこれにあたります。このCTAを最適化することで、コンバージョン率は大きく改善します。
配置:ユーザーが情報を読み終えた直後や、関心が高まったタイミングで自然に目に入る場所に設置します(例:ページの最初と最後、右サイドバーなど)。
デザイン:背景色や周りの要素とは対照的な目立つ色を使い、クリックできるボタンであることが一目で分かるデザインにします。
マイクロコピー:ボタンに記載する文言は非常に重要です。「送信」といった無機質な言葉ではなく、「無料で相談してみる」「詳しい資料を今すぐ入手する」など、ユーザーが得られるメリットや、クリック後のアクションが具体的にイメージできる言葉を選びましょう。
EFO(入力フォーム最適化)
せっかくユーザーが問い合わせを決意しても、入力フォームが複雑で分かりにくいと、途中で面倒になって離脱してしまいます。EFO(入力フォーム最適化)は、この離脱を最小限に抑えるための重要な施策です。以下のポイントを見直してみましょう。
項目数は最小限に:不要な項目は徹底的に削る。
必須項目を明記:「必須」ラベルを分かりやすく表示する。
エラー表示をリアルタイムに:入力ミスがあればその場ですぐに知らせる。
半角/全角の自動変換:ユーザーの手間を省く。
住所自動入力機能:郵便番号から住所を自動で入力できるようにする。
プレースホルダーの活用:入力例を薄い文字で示しておく。
プライバシーポリシーへの同意を明確に:安心感を与える。
入力完了までのステップ表示:あとどれくらいで終わるかを示す。
ボタンの文言を分かりやすく:CTAと同様に、次のアクションが分かる言葉を選ぶ。
複数のCVポイントの設置
コンバージョン(CV)のゴールを「問い合わせ」や「見積もり依頼」といったハードルの高いものだけに設定していませんか?まだ検討段階が浅いユーザーにとっては、いきなり営業担当者と話すことには抵抗があるかもしれません。そこで、顧客の検討段階に合わせた複数の受け皿(CVポイント)を用意することが重要です。
関心が高い層向け:「個別相談会」「無料デモ」「見積もり依頼」
関心が中程度の層向け:「サービス詳細資料」「導入事例集」「料金表」のダウンロード
関心が低い(潜在)層向け:「お役立ちホワイトペーパー」「メルマガ登録」「セミナー申し込み」
このように複数の選択肢を用意することで、今すぐの顧客だけでなく、将来顧客になりうる層とも接点を持つことができ、機会損失を防ぎます。
BtoBサイトの制作や改善に関するご相談はYUTORIにお任せください
本記事では、BtoBサイトの成果を最大化するための具体的な改善ポイントを解説しました。しかし、これらの施策を自社だけで実行するには、専門的な知識とリソースが必要です。
株式会社YUTORIは、Webサイト制作などのWebクリエイティブ事業から、Webマーケティング、プロモーション事業までをワンストップで提供し、企業成長を支える総合パートナーです。
「サイトはあるが成果に繋がらない」「何から手をつければ良いか分からない」といったお悩みをお持ちでしたら、ぜひ一度YUTORIにご相談ください。