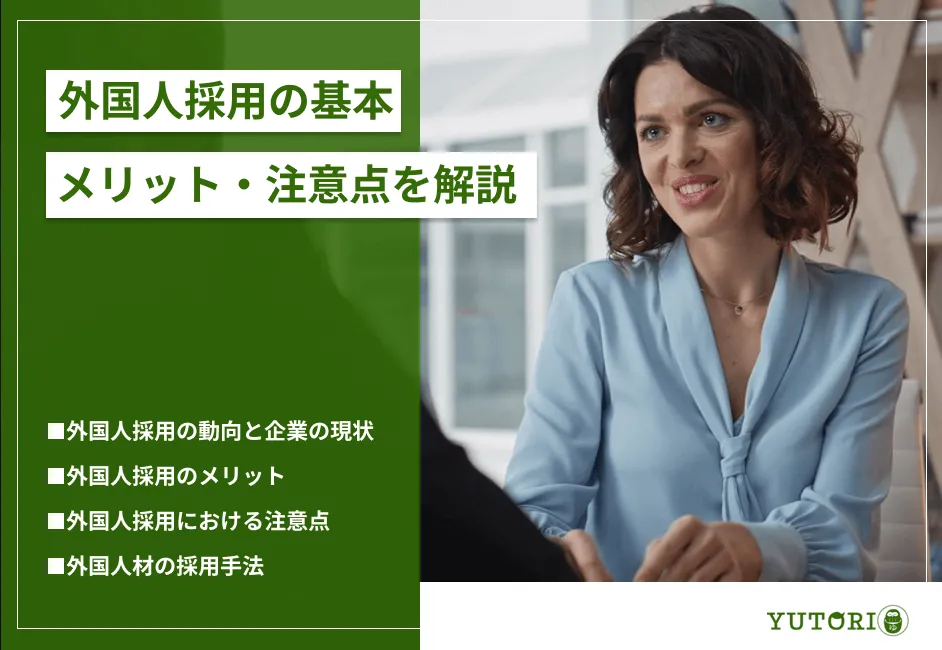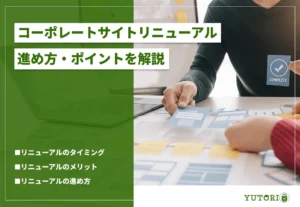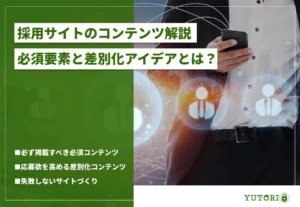少子高齢化による労働力不足が深刻化し、企業のグローバル化が加速する現代において、外国人採用はもはや特別な選択肢ではなく、事業成長のための重要な戦略の一つとなっています。しかし、多くの企業担当者様が「何から始めればいいのか分からない」「法律や手続きが難しそう」といった不安を抱えているのも事実です。
この記事では、外国人採用の最新動向から、具体的なメリット・注意点、採用手法、そして採用後の定着・活躍支援まで、人事担当者が知っておくべき基本を解説していきます。
目次
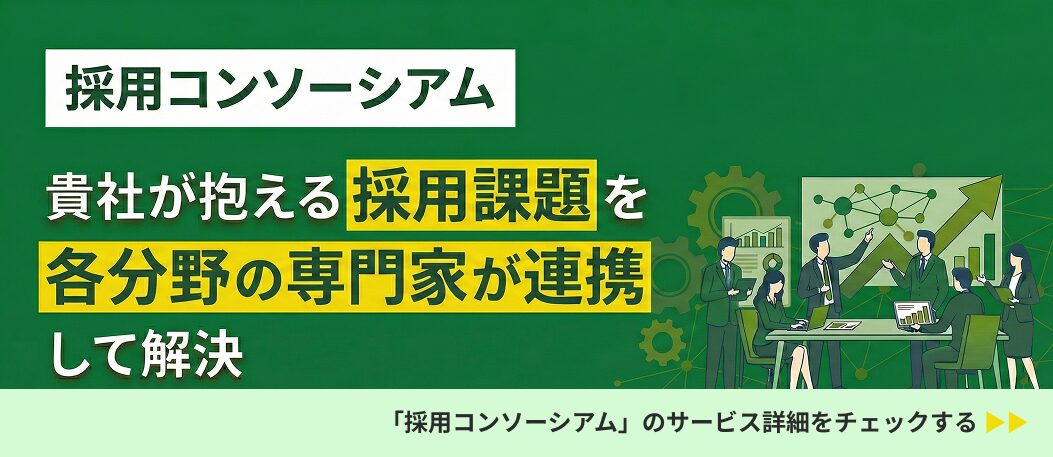
外国人採用の最新動向と企業の現状
まずは、現在の日本において外国人採用がどのくらい進んでいるのか、そして企業はどのような理由で外国人採用に踏み切っているのか、その全体像を把握しましょう。データと現場の声から、外国人採用の「今」が見えてきます。
過去最高を更新する外国人労働者数
厚生労働省の発表によると、日本で働く外国人労働者数は年々増加の一途をたどり、過去最高を更新し続けています。この背景には、深刻化する日本の人手不足はもちろんのこと、企業の海外展開やインバウンド需要の増加に伴い、多様な言語や文化を持つ人材のニーズが高まっていることがあります。また、政府による高度人材や特定技能外国人材の受け入れ促進政策も、この流れを後押ししています。もはや、外国人労働者は一部の業界だけでなく、日本の経済社会を支える不可欠な存在となっているのです。
「人手不足解消」だけではない、企業が外国人採用に踏み切る本当の理由
外国人採用の動機として「人手不足の解消」が最も大きいことは事実です。しかし、先進的な企業はそれだけを目的とはしていません。日本人だけでは得られない多様な視点や価値観を取り入れることで、既存のビジネスモデルに新たな発想をもたらし、イノベーションを創出することを期待しています。また、海外市場に精通した人材を獲得することで、グローバル展開の足がかりにしたり、多様化する顧客ニーズに対応したりと、事業成長を加速させる「攻めの採用」として外国人採用を位置づけている企業が増えています。
企業にもたらされる外国人採用のメリット
外国人材の採用は、単に労働力を確保する以上の、多くの肯定的な影響を企業にもたらします。ここでは、企業が享受できる具体的なメリットを4つの側面から解説します。
若手・優秀人材の確保
少子高齢化が進む日本では、特に若年層の労働力確保が年々難しくなっています。一方、世界に目を向ければ、意欲と能力にあふれた若い人材が数多く存在します。国内の採用市場だけでは出会えないような、特定の技術や専門知識を持つ優秀な人材にアプローチできることは、外国人採用の大きな魅力です。特にIT分野や技術開発分野では、国籍を問わず優秀な人材を確保することが企業の競争力を左右します。
社内の活性化とイノベーション促進
異なる文化や言語、価値観を持つ人材が組織に加わることは、社内に新たな風を吹き込みます。日本人従業員にとっては、多様性を受け入れ、異なる背景を持つ人々と協働する貴重な経験となり、国際感覚の醸成にも繋がります。また、これまで「当たり前」とされてきた業務の進め方や考え方に対して、外国人材が新たな視点から疑問を投げかけることで、組織の硬直化を防ぎ、業務改善や新しいアイデアの創出を促進する効果が期待できます。
グローバル事業展開の加速
海外への事業展開や、インバウンド(訪日外国人向け)事業を検討している企業にとって、ターゲット国の言語や文化、商習慣を深く理解している人材は即戦力となります。現地の市場調査、海外の取引先との交渉、外国人顧客へのきめ細やかな対応など、彼らの知見やネットワークは事業成功の鍵を握ります。日本人従業員だけでは乗り越えがたい壁を、外国人材が架け橋となってスムーズに乗り越えさせてくれるでしょう。
助成金の活用可能性
国や地方自治体は、外国人労働者の雇用促進や職場定着を支援するための助成金制度を設けています。例えば、就労環境の整備(研修の実施、相談窓口の設置など)にかかった費用の一部を助成する「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」などがあります。これらの制度をうまく活用することで、採用や受け入れにかかるコスト負担を軽減できる可能性があります。
事前に把握しておきたい外国人採用における注意点
多くのメリットがある一方で、外国人採用には特有のルールや注意点が存在します。これらを正しく理解しないまま採用を進めると、意図せず法律違反となってしまうリスクも伴います。ここでは、担当者が必ず押さえておくべき重要なポイントを解説します。
「在留資格」と「在留カード」の確認方法
外国人採用において最も重要なのが「在留資格」の確認です。日本に滞在する外国人は、その活動内容に応じた在留資格を持っており、その資格で許可された範囲内でしか就労できません。採用面接などの際には、必ず「在留カード」の原本を提示してもらい、①就労が認められている在留資格か、②在留期間が切れていないか、③「就労制限の有無」欄に「就労不可」や「指定書により指定された活動のみ可」といった記載がないかを確認する必要があります。出入国在留管理庁のウェブサイトでは「在留カード等番号失効情報照会」も可能なので、併せて確認するとより確実です。
就労が認められる在留資格と認められない在留資格
在留資格は多岐にわたりますが、就労できるかどうかで大きく分けられます。
就労が認められる在留資格の例
技術・人文知識・国際業務:
エンジニア、通訳、企画、営業など、専門知識を活かす職種。
特定技能:
特定の産業分野(介護、外食、建設など)で即戦力として働くための資格。
技能:
外国特有の料理の調理師など、熟練した技能を要する職種。
身分・地位に基づく在留資格(永住者、日本人の配偶者等、定住者など):
活動に制限がないため、原則としてどのような職種にも就労できます。
原則として就労が認められない在留資格の例
留学、文化活動、短期滞在:
これらの資格では働くことはできません。ただし、「留学」や「家族滞在」の資格を持つ人は、事前に入国管理局から「資格外活動許可」を得ていれば、週28時間以内のアルバイトが可能です。
知らないでは済まされない「不法就労助長罪」のリスクと罰則
もし、就労資格がないことを知らずに外国人を雇用してしまったり、在留カードの確認を怠ったりした場合、企業側が「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。この罪に問われると、事業主に対して3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科される重い罰則があります。「知らなかった」では済まされないため、在留資格の確認は慎重すぎるほど慎重に行う必要があります。
「同一労働同一賃金」の遵守
労働基準法などの労働関係法令は、国籍を問わず日本で働くすべての労働者に適用されます。「外国人だから」という理由で、同じ仕事をしている日本人従業員よりも低い給与を設定したり、不合理な待遇差を設けたりすることは、法律で固く禁じられています。賃金、労働時間、福利厚生など、すべての待遇において「同一労働同一賃金」の原則を遵守し、公平な労働条件を提示しなければなりません。
どこで出会う?自社に合った外国人材の採用方法の選定ポイント
自社が求めるスキルや人物像に合った外国人材と出会うためには、適切な採用チャネルを選ぶことが重要です。ここでは、代表的な4つの採用方法とその特徴を解説します。
求人サイト・SNS
国内外の多くの外国人が利用する求人サイトや、LinkedInなどのビジネス特化型SNSを活用する方法です。広範囲に募集をかけられるため、多くの候補者と接点を持てる可能性があります。一方で、応募者のスクリーニングや在留資格の確認、面接調整などをすべて自社で行う必要があるため、採用ノウハウや工数が求められます。
人材紹介・派遣会社
外国人材の紹介や派遣を専門に行うエージェントを活用する方法です。自社の採用要件を伝えれば、条件に合った人材を探し出し、在留資格の確認や日本語レベルのチェックまで行った上で紹介してくれます。採用工数を大幅に削減でき、専門家のアドバイスも受けられるメリットがありますが、採用が成功した際には成功報酬などのコストが発生します。
公的機関の活用
国が運営する「ハローワーク(外国人専門窓口)」や「外国人雇用サービスセンター(東京、名古屋、大阪など)」を利用する方法です。これらの機関では、無料で求人情報を掲載でき、外国人留学生や専門的な知識を持つ外国人材の紹介を受けることができます。コストをかけずに採用活動を始めたい企業にとって、最初の選択肢となるでしょう。
大学・専門学校との連携
日本国内の大学や専門学校で学ぶ外国人留学生をターゲットにする方法です。各学校のキャリアセンターと連携して求人票を提出したり、学内で開催されるジョブフェアに参加したりすることで、卒業を控えた優秀な学生に直接アプローチできます。専門分野の知識と一定の日本語能力を兼ね備えた人材に出会える可能性が高いのが魅力です。
外国人材の定着と活躍を促すためのポイント
採用はゴールではなく、スタートです。採用した外国人材が能力を最大限に発揮し、長く会社に貢献してもらうためには、受け入れ後の環境整備と継続的なサポートが不可欠です。
定着の鍵を握る初期サポート
入社直後は、仕事に慣れるだけでなく、日本の生活に慣れる上でも非常に重要な時期です。社会保険や税金などの公的手続きのサポートはもちろん、企業によっては銀行口座の開設、携帯電話の契約、住居探しといった生活面のサポートも行っています。こうした細やかな初期サポートは、外国人従業員の不安を和らげ、会社への信頼感(エンゲージメント)を高める上で極めて効果的です。
文化・宗教・習慣の違いへの配慮とコミュニケーションの工夫
職場での円滑な人間関係は、定着の重要な要素です。イスラム教徒の従業員のためにお祈りの時間を確保したり、礼拝用のスペースを用意したり、ベジタリアンやハラールなど食文化に配慮した対応を検討することが大切です。また、指示を出す際には「空気を読む」といったハイコンテクストな表現を避け、具体的かつ明確な言葉で伝える「ローコンテクスト」なコミュニケーションを心がけることで、認識のズレを防ぐことができます。
キャリアパスの提示と育成計画
外国人従業員も、日本人従業員と同様に、自らのキャリア成長を望んでいます。「この会社で働き続ければ、将来こうなれる」という明確なキャリアパスを示し、必要なスキルを習得するための研修や教育の機会を提供することが重要です。定期的な面談を通じて本人の意向を確認し、個々の能力や志向に応じた育成計画を共に考えることで、仕事へのモチベーションを高め、長期的な活躍を促します。
義務化されている「外国人労働者雇用管理責任者」の選任とは
外国人労働者を常時10人以上雇用する事業所では、「外国人労働者雇用管理責任者」を選任し、ハローワークに届け出ることが義務付けられています。この責任者は、人事・労務管理の担当者などから選任され、外国人労働者からの相談対応、労働条件の明確化、安全衛生教育、生活支援など、彼らが円滑に働けるようにするための中心的な役割を担います。
採用に関するご相談はYUTORIにお任せください
株式会社YUTORIでは、採用コストの高騰や求人広告の効果低下といった採用課題を抱える企業に対し、「採用コンソーシアム」という独自の支援体制で採用プロモーションをサポートします。
採用コンソーシアムとは、メディア、原稿作成、HP制作、広告分析、LINE運用など、各分野の専門性を持つパートナー企業がチームを組むことで、企業の採用課題を多角的に解決する仕組みです。部分的な課題解決から全体的な採用戦略の見直しまで、企業の状況に合わせて柔軟に対応し、採用課題の根本的な解決と、その先の事業成長までをサポートします。