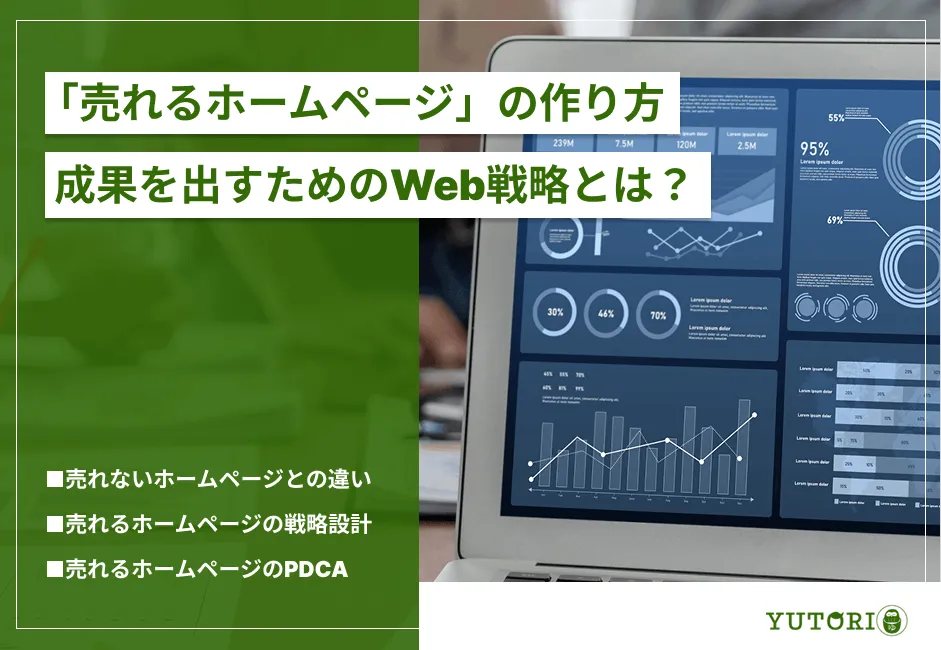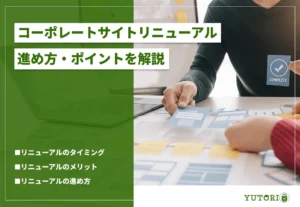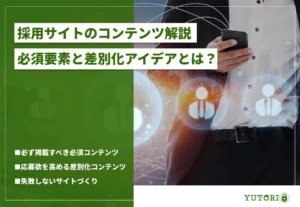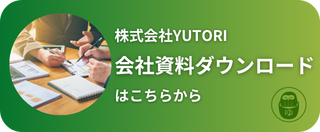「多額の費用をかけてホームページをリニューアルしたのに、問い合わせも売上も全く増えない…」
「Webサイトの重要性は理解しているが、具体的に何から手をつければ成果に繋がるのか分からない…」
企業のWeb担当者として、このような悩みを抱えてはいないでしょうか。現代のビジネスにおいて、ホームページは単なる「会社のパンフレット」ではなく、24時間365日働き続ける「優秀な営業マン」となり得る強力なツールです。しかし、そのポテンシャルを最大限に引き出せている企業は決して多くありません。
この記事では、「売れるホームページ」と「売れないホームページ」を分ける決定的な違いから、成果を最大化するための戦略設計、そして実践できる具体的な施策までを網羅的に解説します。
目次
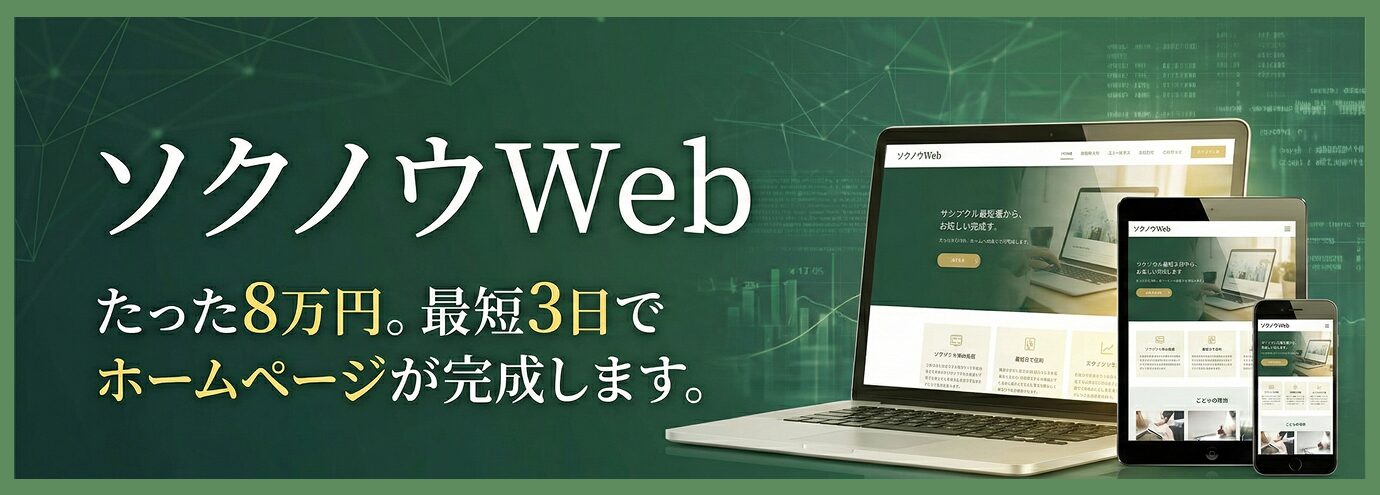
売れるホームページと売れないホームページの違い
多くの企業がホームページを持っていますが、その成果には大きな差が生まれています。問い合わせが殺到し、売上を伸ばし続けるサイトがある一方で、全く反応がなく、ただ存在しているだけのサイトも少なくありません。この違いはどこから来るのでしょうか。ここでは、成果の出るサイトと出ないサイトを構造的に理解し、自社サイトの課題を発見するための視点を提供します。
売上の方程式で課題を分解する
ホームページの売上は、シンプルな方程式で分解できます。
売上 = 訪問者数 × 成約率(CVR) × 顧客単価
多くの「売れないホームページ」は、この方程式を意識せずに「とにかくアクセスを増やそう」「デザインをきれいにしよう」と、漠然とした施策に走りがちです。しかし、成果を出すWeb担当者は、まずこの方程式に自社の現状を当てはめ、「訪問者数が足りないのか?」「訪問はされているが成約率が低いのか?」「成約はしているが単価が低いのか?」というように、ボトルネックとなっている課題を特定することから始めます。課題を正しく分解して捉えることが、的確な施策を打つための第一歩です。
サイトは優秀な営業マンか?それとも一方的な訪問販売?
「売れるホームページ」は、まるで優秀な営業マンのように振る舞います。顧客が抱える悩みや課題に寄り添い、その解決策として自社の製品やサービスを最適なタイミングで提案します。顧客の疑問に先回りして答えを用意し、信頼関係を築きながら、自然な流れで購入へと導きます。
一方で、「売れないホームページ」は、一方的な訪問販売に似ています。企業が言いたいこと(自社の強み、製品のスペックなど)を一方的に並べ立てるだけで、顧客が本当に知りたい情報を提供できていません。これでは、訪問者はすぐにドア(ブラウザのタブ)を閉じてしまうでしょう。
売れないサイトに共通する7つの典型的な問題点
成果の出ないホームページには、いくつかの共通した問題点が存在します。自社のサイトがこれらに当てはまっていないか、チェックしてみましょう。
ターゲットが不明確
「すべての人」に向けたメッセージは、結局「誰の心にも」響きません。どのような悩みやニーズを持った人に、どのような価値を提供したいのかが明確になっていないサイトは、当たり障りのない内容になりがちで、訪問者の共感を得ることができません。
情報が探しにくい
訪問者が目的の情報にたどり着けないサイトは、それだけで大きな機会損失を生んでいます。ナビゲーションメニューが分かりにくかったり、サイト構造が複雑だったりすると、ユーザーはストレスを感じてすぐに離脱してしまいます。
コンテンツの質が低い・古い
ブログ記事の内容が薄かったり、何年も前の情報が更新されていなかったりすると、訪問者は「この会社は信頼できない」と感じてしまいます。ユーザーの課題解決に貢献する、専門性の高い、新鮮な情報を提供し続けることが重要です。
競合との差別化ができていない
競合他社と同じような強みやメリットを並べているだけでは、訪問者は「なぜこの会社から買うべきなのか」を理解できません。自社ならではの独自の価値(強み)が明確に伝わらなければ、価格競争に巻き込まれるだけです。
信頼性が欠如している
会社概要や代表者の情報が不十分であったり、導入実績やお客様の声が掲載されていなかったりするサイトは、訪問者に不安を与えます。また、サイトがSSL化(https://)されていないといった技術的な問題も、信頼性を損なう大きな要因です。
行動喚起(CTA)が弱い
サイトを訪れたユーザーに、次に何をしてほしいのか(例:「資料請求する」「問い合わせる」「購入する」)を明確に示せていないケースです。「お問い合わせはこちら」のボタンが小さくて見つけにくかったり、どこにも設置されていなかったりしては、せっかく興味を持ったユーザーを取り逃がしてしまいます。
デザインへの過度なこだわり
見た目の美しさやインパクトを追求するあまり、ユーザーの使いやすさが犠牲になっているサイトも少なくありません。デザインはあくまでも、情報を分かりやすく伝え、目的を達成させるための手段です。目的と手段を履き違えてはいけません。
成果を最大化する「売れるホームページ」の戦略設計のポイント
「売れないホームページ」の問題点を理解した上で、次はいよいよ「売れるホームページ」を構築するための戦略設計に入ります。やみくもに施策を打つのではなく、しっかりとした戦略の骨子を定めることが成功への最短ルートです。ここでは、「誰に」「何を」「どうやって」という3つのシンプルな問いを通じて、戦略を具体化していきます。
誰に届けるのか?(ペルソナ設定と顧客理解)
戦略の出発点は、顧客を深く理解することです。自社の製品やサービスを最も必要としているのは、一体どのような人物でしょうか?その人物像を具体的に描き出したものが「ペルソナ」です。
年齢、性別、職業といった属性情報だけでなく、その人が日常的にどのような課題や悩みを抱え、どのような情報を、どのチャネル(Webサイト、SNSなど)で収集しているのかまでを詳細に設定します。明確なペルソナを設定することで、チーム内でのターゲット像のズレを防ぎ、メッセージやコンテンツの方向性がブレなくなります。
何を伝えるのか?(独自の価値提案とコンテンツ戦略)
ターゲット(ペルソナ)が明確になったら、次はその人に対して「何を伝えるか」を考えます。ここで重要になるのが「独自の価値提案」です。これは、競合他社にはない、自社だけが提供できる顧客への価値を、簡潔に言い表したものです。
「我々は何屋で、誰のどんな課題を、他社とどう違った方法で解決できるのか?」を突き詰めて考えましょう。そして、その独自の価値を伝えるために、どのようなコンテンツが必要かを計画します。ブログ記事、導入事例、お客様の声、ホワイトペーパー、動画など、ペルソナが求める情報と、自社の価値が伝わるコンテンツを戦略的に用意していきます。
どうやって届けるのか?(流入計画とカスタマージャーニー)
最高の価値提案とコンテンツを用意しても、それがターゲットに届かなければ意味がありません。設定したペルソナが、どのような経路で自社のホームページにたどり着くのかを想定し、計画的に集客を行う必要があります。SEO(検索エンジン最適化)、Web広告、SNSなど、複数のチャネルを組み合わせた流入計画を立てましょう。
さらに、ユーザーが自社を認知し、興味を持ち、比較検討を経て、最終的に購入・問い合わせに至るまでの一連のプロセス(カスタマージャーニー)を可視化します。各段階でユーザーがどのような情報を必要としているかを理解し、適切なタイミングで適切なコンテンツを届けることで、スムーズなゴール達成を後押しします。
売れるホームページを作るための具体的施策
戦略設計が完了したら、いよいよ具体的な施策の実行フェーズです。ここでは、「売上の方程式」で解説した「訪問者数」「成約率」「顧客単価」の3つの要素をそれぞれ向上させるための具体的な施策をご紹介します。自社の課題に合わせて、優先順位を付けて取り組んでいきましょう。
【フェーズ1】訪問者数を増やすための集客施策
まずは、ホームページに見込み客を呼び込むための施策です。
SEO対策
検索エンジン経由のアクセスは、特定の悩みやニーズを持った質の高いユーザーを呼び込めるため、最も重要な集客施策の一つです。ターゲットが検索するであろうキーワードを徹底的に調査し、その検索意図に応える質の高いコンテンツを作成・発信し続けることで、中長期的に安定した集客が見込めます。
Web広告
短期的に特定のターゲット層にアプローチしたい場合に非常に有効です。検索結果に表示するリスティング広告や、他のWebサイトの広告枠に表示するディスプレイ広告、SNS広告などを活用し、認知拡大や特定のキャンペーンへの集客を加速させます。
SNS活用
Facebook、X(旧Twitter)、Instagram、LinkedInなど、自社のターゲット層が多く利用するSNSプラットフォームを活用して情報発信を行います。潜在顧客との接点を作り、ファンを育成することで、公式サイトへの継続的な流入を創出します。
【フェーズ2】成約率を高めるためのサイト内部最適化施策
集めたアクセスを、実際の問い合わせや購入(コンバージョン)に繋げるための施策です。
ファーストビューの最適化
ユーザーがページを訪れて最初に目にする画面(ファーストビュー)で、「誰のための」「どんなサービスか」が3秒で伝わるように改善します。魅力的なキャッチコピー、信頼感のあるメインビジュアル、そして次に取るべき行動(CTA)を分かりやすく配置することが重要です。
CTA(行動喚起)の改善
「資料請求」「お問い合わせ」といったボタンのデザイン(色、形、大きさ)や文言を、よりクリックしたくなるように工夫します。例えば、「無料で資料請求する」「まずは専門家に相談する」のように、ユーザーのメリットや心理的なハードルの低さを示す文言が効果的です。
導入実績・お客様の声の掲載
第三者からの評価は、企業の信頼性を飛躍的に高めます。具体的な企業名や担当者様の顔写真、直筆の推薦文などを掲載することで、「自分と同じような悩みを持つ人も、このサービスで成功している」という安心感を与え、意思決定を後押しします(社会的証明)。
魅力的なコンテンツの充実
製品・サービスの紹介だけでなく、ユーザーの課題解決に役立つコラム記事や、導入後の成功イメージが湧く導入事例、専門知識をまとめたホワイトペーパーなどを充実させます。質の高いコンテンツは、専門性を示し、信頼関係を築く上で不可欠です。
内部リンクの最適化
関連性の高いページ同士をリンクで繋ぐことで、ユーザーはサイト内をスムーズに回遊し、より多くの情報を得ることができます。サイトの滞在時間を延ばし、離脱率を低下させる効果があります。
オリジナル写真・画像の活用
安価なフリー素材ではなく、実際の社員、オフィス、製品を使用している風景など、オリジナルの写真や画像を使用しましょう。リアルな写真は、企業の透明性や親近感を伝え、信頼性を高める上で非常に効果的です。
スマートフォン対応
今やアクセスの半数以上がスマートフォンからです。PCでの表示だけでなく、スマートフォンで見た際の文字の大きさ、ボタンの押しやすさ、表示速度などが最適化されているか(レスポンシブデザイン)は、必須の対応項目です。
キャッチコピーの磨き込み
各ページのタイトルや見出しは、ユーザーが続きを読むかどうかを判断する重要な要素です。ターゲットの心に刺さる言葉、メリットが端的に伝わる言葉、続きが気になる言葉を選び、徹底的に磨き込みましょう。
入力フォームの最適化(EFO)
せっかく問い合わせを決意したユーザーが、入力フォームの煩雑さで離脱してしまうのは非常にもったいないことです。入力項目を必要最小限に絞る、入力例を明記する、エラー表示を分かりやすくするなど、ユーザーの負担を極限まで減らす工夫(EFO: Entry Form Optimization)が求められます。
【フェーズ3】顧客単価を高めるための施策
一人あたりの顧客から得られる売上を最大化するための施策です。
アップセル・クロスセルの提案
ある商品に興味を持っているユーザーに対して、より高機能な上位モデルを提案(アップセル)したり、関連商品を一緒に提案(クロスセル)したりする仕組みを導入します。ECサイトの「この商品を買った人はこんな商品も見ています」などが代表例です。
価格ではなく「価値」で選ばれるためのブランディング要素
価格競争から脱却するためには、自社ならではのブランド価値を高めることが重要です。創業ストーリー、企業の理念、デザインの統一性、社会貢献活動などを発信し、機能的な価値だけでなく、情緒的な価値に共感してもらうことで、高単価でも選ばれる存在を目指します。
インサイドセールスへの連携計画
BtoBビジネスにおいて特に重要です。ホームページから獲得した見込み客(リード)情報を、ただ営業担当者に渡すだけでは成約に繋がりません。電話やメールで継続的にコミュニケーションを取り、顧客の検討度合いを高めてから営業に引き渡すインサイドセールス部門との連携体制を構築することで、商談化率と受注単価の向上が期待できます。
作って終わりではない「売れるホームページ」の運用と改善サイクル
「売れるホームページ」は、一度作ったら完成、ではありません。むしろ、公開してからが本当のスタートです。市場や顧客のニーズは常に変化します。その変化に対応し、継続的に成果を出し続けるためには、データに基づいた改善サイクル(PDCA)を回し続けることが不可欠です。
定期的な効果測定と分析
Google AnalyticsやGoogle Search Consoleといった無料のアクセス解析ツールを活用し、ホームページの現状をデータで把握しましょう。「どのページが多く見られているか」「ユーザーはどのようなキーワードで流入しているか」「どのページで離脱が多いか」などを定期的に分析し、課題や改善のヒントを発見します。勘や経験だけに頼らず、客観的なデータに基づいて仮説を立てることが重要です。
A/Bテストによる継続的な改善プロセス
データ分析から導き出した改善仮説を検証するために、A/Bテストは非常に有効な手法です。例えば、「ボタンの色を赤から緑に変えたらクリック率は上がるのではないか?」という仮説を立てた場合、オリジナルパターン(A)と変更パターン(B)をランダムにユーザーに表示し、どちらの成果が高いかを比較検証します。このような小さな改善を積み重ねていくことが、成約率を最大化させるための確実な道筋です。
売れるホームページの構築はYOTRIにご相談ください
ここまで「売れるホームページ」の作り方について、戦略から具体的な施策までを解説してきましたが、これらをすべて自社だけで実行するには、専門的な知識と多くのリソースが必要となります。
株式会社YUTORIは、Webサイト制作はもちろんのこと、Webマーケティング、映像制作、写真撮影までをワンストップで提供し、あなたのビジネスに”ゆとり”をお届けする総合パートナーです。
「何から手をつければいいか分からない」「今のホームページに課題を感じているが、改善方法が分からない」もしそうお考えでしたら、ぜひ一度、株式会社YUTORIにご相談ください。