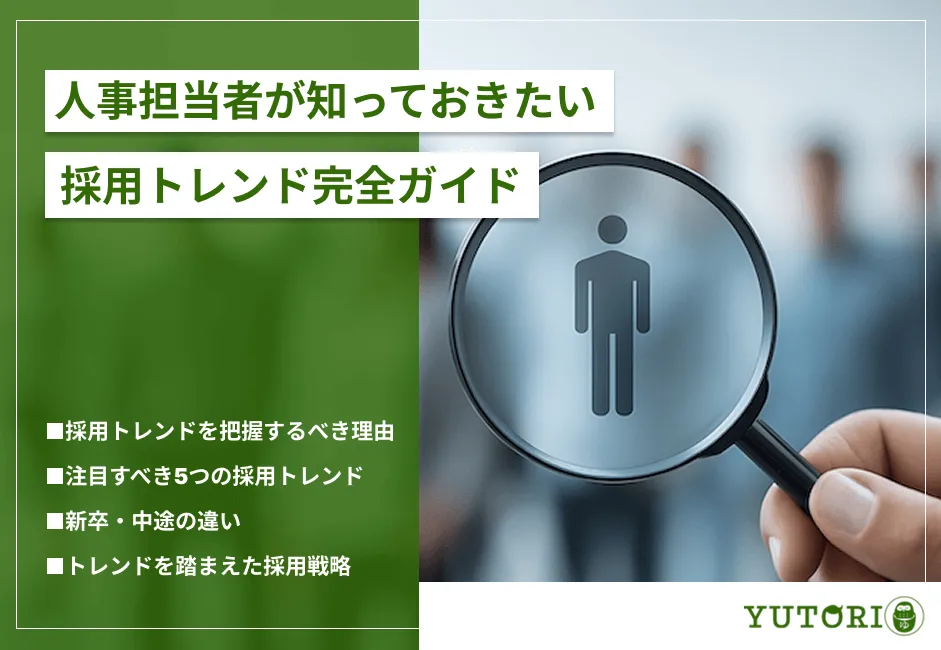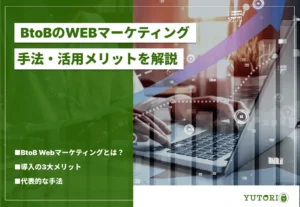企業成長の根幹を成す「人材獲得」。しかし、労働市場はかつてない速さで変化しており、従来の手法だけでは優秀な人材の獲得は困難になっています。本記事では、人事担当者が今こそ知るべき最新の採用トレンドを徹底解説。2025/26年に向けた採用戦略立案のヒントとなる情報をお届けします。
目次
採用トレンドの把握が不可欠な理由
採用活動を取り巻く環境は、社会構造の変化やテクノロジーの進化とともに、常に変動しています。最新の採用トレンドを正確に把握し、自社の戦略に活かすことは、競争優位性を確立し、持続的な企業成長を実現するために不可欠です。このセクションでは、なぜ今、採用トレンドの理解が重要なのか、その背景と具体的な理由を解説します。
採用市場の現状:労働人口減少と売り手市場の加速
日本の生産年齢人口は、かねてより指摘されている通り減少の一途をたどっており、多くの産業で人手不足が深刻化しています。特に若年層の労働力不足は顕著で、新卒採用・中途採用ともに、企業が候補者を選ぶ「買い手市場」から、候補者が企業を選ぶ「売り手市場」へと完全にシフトしています。この状況は今後も続くと予測され、企業はより一層、候補者から選ばれるための魅力を高め、戦略的な採用活動を展開する必要に迫られています。従来の待ちの姿勢では、優秀な人材の獲得はますます困難になるでしょう。
テクノロジー進化と働き方の多様化がもたらす変革
AIやビッグデータ、クラウドサービスといったテクノロジーの進化は、採用活動にも大きな変革をもたらしています。採用管理システム(ATS)の高度化、オンライン面接の普及、AIによる書類選考や候補者マッチングなど、テクノロジーを活用することで採用業務の効率化や質の向上が可能になりました。また、コロナ禍を経て、リモートワークやハイブリッドワークといった柔軟な働き方が急速に普及し、従業員の価値観も多様化しています。企業は、これらの変化に対応した採用プロセスや労働環境を整備しなければ、多様な人材の獲得機会を逸してしまう可能性があります。
トレンドを無視するリスクと、適応するメリット
最新の採用トレンドを無視し、旧態依然とした採用活動を続ける企業は、知らず知らずのうちに多くのリスクを抱えることになります。例えば、優秀な人材の応募が集まらない、採用コストが増大する、内定辞退率が上昇する、入社後のミスマッチが頻発するといった問題が顕在化しやすくなります。その結果、事業成長の鈍化や競争力の低下を招く恐れもあるでしょう。 一方で、トレンドを的確に捉え、迅速に適応する企業は、大きなメリットを享受できます。採用競争における優位性の確立、採用効率の向上、より質の高い人材の獲得、従業員エンゲージMENTの向上、そして企業ブランドイメージの向上などが期待できます。変化を恐れず、積極的に新しい手法を取り入れる姿勢が、これからの採用活動の成否を分けると言っても過言ではありません。
2025/26年に注目すべき5つの採用トレンド
目まぐるしく変化する採用市場において、常にアンテナを張り、最新の動向を把握しておくことは人事担当者の重要な責務です。ここでは、2025/26年に向けて特に注目すべき5つの採用トレンドをピックアップし、それぞれの詳細と企業が取るべき対策について解説します。これらのトレンドを理解し、自社の採用戦略に組み込むことで、より効果的な人材獲得を目指しましょう。
1. DX推進と採用テクノロジーの活用
デジタルトランスフォーメーション(DX)の波は、採用領域においても例外ではありません。むしろ、効率化と質の向上を両立させるために、テクノロジーの活用は不可欠と言えるでしょう。AI、ビッグデータ、RPAといった技術を駆使し、採用プロセス全体を最適化する動きが加速しています。
生成AIの選考プロセスへの導入
ChatGPTをはじめとする生成AIの進化は目覚ましく、採用業務においてもその活用が期待されています。例えば、求人票の自動作成、応募者との初期コミュニケーション(チャットボット)、書類選考の一次スクリーニング、面接日程の調整といった定型業務の自動化が可能です。これにより、人事担当者はより戦略的な業務や、候補者との深いコミュニケーションに時間を割けるようになります。ただし、AIの判断にバイアスがかからないような倫理的な配慮や、最終的な判断は人間が行うといった運用体制の整備も重要です。
データドリブンな採用戦略の重要性
勘や経験に頼った採用ではなく、収集・分析したデータに基づいて意思決定を行う「データドリブンな採用戦略」の重要性がますます高まっています。応募経路別の効果測定、選考段階ごとの離脱率分析、採用ターゲットに合致した人材の属性分析などを通じて、採用プロセスの課題発見や改善策の立案、そして投資対効果(ROI)の最大化を目指します。採用管理システム(ATS)やアナリティクスツールを効果的に活用し、継続的なデータ収集と分析を行う体制を構築することが求められます。
採用におけるデジタルスキル人材の獲得と評価
あらゆる産業でDXが進む中、デジタルスキルを持つ人材の需要は高まる一方です。しかし、こうした人材は獲得競争が激しく、従来の採用手法だけでは十分な母集団形成が難しいのが現状です。企業は、求めるデジタルスキルを明確に定義し、スキルを見極めるための選考方法(テクニカルテスト、ポートフォリオ評価、専門的な面接など)を導入する必要があります。また、社内での育成体制の整備や、外部の専門家との連携も視野に入れるべきでしょう。
2. リモートワーク・ハイブリッドワークの常態化と採用戦略
コロナ禍を契機に急速に普及したリモートワークやハイブリッドワークは、一過性のものとしてではなく、新しい働き方のスタンダードとして定着しつつあります。この変化は、採用戦略にも大きな影響を与えており、企業は柔軟な働き方に対応した採用活動を展開する必要があります。
柔軟な働き方を求める候補者への対応
多くの候補者、特に若手層や優秀な人材は、働く場所や時間に柔軟性を求める傾向が強まっています。企業は、リモートワークやフレックスタイム制度の導入・拡充を検討し、求人票や企業説明会などで積極的にアピールすることが重要です。また、単に制度を導入するだけでなく、リモート環境でも円滑なコミュニケーションが取れるツールや、成果を正当に評価する仕組みを整備することで、候補者の信頼を得ることができます。
リモート環境で活躍する人材の見極め方
リモートワーク環境で高いパフォーマンスを発揮できる人材には、自己管理能力、コミュニケーション能力、自律性、そしてICTスキルなどが求められます。選考プロセスにおいては、これらの能力を見極めるための工夫が必要です。例えば、オンライン面接での的確な質問、過去のプロジェクト経験における具体的な役割や成果の深掘り、オンラインでのグループワークや課題解決型のテストなどが有効です。また、リファレンスチェックを通じて、客観的な評価を得ることも検討しましょう。
3. ダイバーシティ&インクルージョン (D&I) の本格化
性別、年齢、国籍、障がいの有無、性的指向、価値観などの多様性を受け入れ、それぞれの能力を最大限に活かせる組織を目指すダイバーシティ&インクルージョン(D&I)の推進は、今や企業成長に不可欠な要素として認識されています。採用活動においても、D&Iの視点を取り入れることが強く求められています。
D&I推進が企業成長にもたらす価値
D&Iを推進することで、多様な視点やアイデアが生まれ、イノベーションの創出や問題解決能力の向上が期待できます。また、従業員のエンゲージメント向上、企業イメージの向上、そしてグローバル市場への対応力強化にも繋がります。採用においては、多様なバックグラウンドを持つ人材にアプローチすることで、優秀な人材の獲得機会が広がり、組織全体の活性化に貢献します。
公平な採用プロセスの構築
D&Iを実現するためには、採用プロセスにおける無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)を排除し、すべての候補者に対して公平な機会を提供することが重要です。具体的には、応募書類の匿名化、構造化面接(予め評価基準と質問項目を統一する面接手法)の導入、面接官トレーニングの実施などが有効です。また、多様な属性の社員が採用プロセスに関わることで、より多角的な視点からの評価が可能になります。
女性活躍推進と採用戦略
D&Iの中でも特に重要なテーマの一つが、女性活躍推進です。出産・育児などのライフイベントとキャリア形成を両立できる環境整備はもちろんのこと、管理職への積極的な登用や、女性が能力を発揮しやすい職場風土の醸成が求められます。採用においては、ロールモデルとなる女性社員の情報を発信したり、育児中の社員向けのサポート制度を明確に伝えたりすることで、女性候補者からの応募を促進することができます。
4. 候補者体験とエンプロイヤーブランディングの強化
売り手市場が加速する中で、企業が候補者から「選ばれる」ためには、候補者一人ひとりの体験価値を高める「候補者体験(Candidate Experience)」の向上が不可欠です。また、働く場としての企業の魅力を発信する「エンプロイヤーブランディング」も、これまで以上に重要性を増しています。
SNSを活用した採用ブランディング戦略
企業のリアルな情報や社風、働く社員の声を届ける上で、SNSは非常に有効なツールです。ターゲットとする人材層に合わせたプラットフォームを選定し、定期的な情報発信や、候補者との双方向のコミュニケーションを通じて、企業のファンを増やすことが重要です。社員インタビュー、オフィス紹介、社内イベントの様子などを発信することで、企業の魅力を多角的に伝え、共感を醸成することができます。
選考フローの個別化と迅速化
画一的な選考フローではなく、候補者のスキルや経験、志向性に合わせて選考プロセスを柔軟に調整する「個別化」が求められています。また、選考期間の長期化は候補者の離脱に繋がるため、迅速な意思決定とフィードバックが不可欠です。応募から内定までのリードタイムを短縮し、各選考ステップで丁寧なコミュニケーションを心がけることで、候補者の満足度を高め、入社意欲を維持することができます。
5. スキルベース採用と柔軟な雇用形態の拡大
従来の学歴や職歴偏重の採用から、個人の持つスキルや専門性を重視する「スキルベース採用」への移行が進んでいます。また、正社員だけでなく、副業・兼業人材やフリーランスといった多様な働き手を受け入れる動きも活発化しています。
副業・兼業人材、フリーランスの活用
特定のプロジェクトや専門業務において、外部のプロフェッショナル人材の力を借りることは、企業にとって有効な選択肢です。副業・兼業人材やフリーランスを活用することで、必要なスキルを柔軟に確保できるだけでなく、社内に新たな知見やネットワークを取り込むことができます。これらの人材を受け入れるための契約形態や情報管理体制、コミュニケーション方法などを整備しておく必要があります。
高度IT人材・専門職人材の獲得競争
AIエンジニア、データサイエンティスト、サイバーセキュリティ専門家といった高度IT人材や、特定の分野で深い専門知識を持つ人材の獲得競争は、ますます激化しています。これらの人材は、給与水準だけでなく、挑戦的なプロジェクトや成長機会、裁量権の大きさなどを重視する傾向があります。魅力的な業務内容の提示、技術志向の強いコミュニティへのアプローチ、リファラル採用の強化など、多角的な採用戦略が求められます。
【対象別】新卒・中途採用における特有のトレンドと対策
採用トレンドは、対象となる候補者層によっても異なる様相を見せます。新卒採用と中途採用、それぞれに特有のトレンドが存在し、企業はそれに応じた対策を講じる必要があります。このセクションでは、新卒採用と中途採用における最新トレンドと、人事担当者が取るべき具体的なアクションについて解説します。
新卒採用トレンド:早期化、個別化、エンゲージメント重視
新卒採用市場は、学生の就職活動の早期化が顕著であり、企業はより早い段階から学生との接点を持ち、関係性を構築していくことが重要になっています。また、学生一人ひとりの価値観やキャリアプランに寄り添った「個別化」されたアプローチや、入社意欲を高めるための「エンゲージメント」の向上が求められています。
ダイレクトリクルーティングの更なる拡大
企業が自ら求める人材を探し出し、直接アプローチする「ダイレクトリクルーティング」は、新卒採用においても主要な手法の一つとして定着しつつあります。特に、ニッチなスキルを持つ学生や、特定の研究分野で高い専門性を持つ学生にリーチするためには有効です。ダイレクトリクルーティングサービスを活用するだけでなく、大学の研究室との連携強化や、OB・OG訪問の積極的な活用も検討しましょう。
長期インターンシップの戦略的活用
学生が実際の業務を通じて企業理解を深め、自身の適性を見極める機会となる長期インターンシップは、ミスマッチの防止や早期離職の抑制に繋がる有効な手段です。単なる職場体験に留まらず、学生に具体的な役割や責任を与え、成長を促すようなプログラム設計が重要です。また、インターンシップ参加者との継続的なコミュニケーションを通じて、入社意欲を高めていくことが求められます。
中途採用トレンド:即戦力志向とリテンションの重要性
中途採用市場においては、企業側の即戦力志向が一層強まっています。一方で、採用した人材が早期に離職してしまうことを防ぎ、定着(リテンション)させるための取り組みも、採用活動と表裏一体の重要な課題として認識されています。優秀な人材の獲得競争が激化する中、採用後のフォローアップ体制の強化が不可欠です。
リファラル採用・ヘッドハンティングの有効活用
社員の知人や友人を紹介してもらう「リファラル採用」は、企業文化にマッチした人材を効率的に採用できる可能性が高く、採用コストの抑制にも繋がるため、多くの企業が積極的に取り入れています。また、経営幹部や高度専門職といった特定のポジションの人材を獲得するためには、専門のエージェントを通じた「ヘッドハンティング」も有効な手段です。それぞれの特性を理解し、目的に応じて使い分けることが重要です。
シニア人材の雇用拡大とその可能性
労働力不足の深刻化を背景に、豊富な経験や専門知識を持つシニア人材の活用に注目が集まっています。年齢に関わらず意欲と能力のある人材を積極的に採用し、その知見を若手育成や事業課題の解決に活かそうという動きが広がっています。シニア人材が活躍できる柔軟な勤務形態や役割を提供するとともに、社内の受け入れ体制や意識改革も重要になります。
採用トレンドを踏まえた人事担当者のアクションプラン
ここまで解説してきた採用トレンドは、それぞれが独立しているわけではなく、相互に影響し合っています。これらの変化を的確に捉え、自社の採用戦略に落とし込むためには、人事担当者自身が主体的に行動を起こす必要があります。このセクションでは、具体的なアクションプランのポイントを提示します。
自社の採用戦略・プロセスの見直しポイント
まずは、現状の採用戦略やプロセスが、最新のトレンドと照らし合わせてどの程度適合しているのかを客観的に評価することから始めましょう。ターゲットとする人材像は明確か、採用チャネルは最適か、選考プロセスは候補者にとって魅力的か、そして採用基準は公平かつ妥当か、といった点を多角的に検証します。その上で、強化すべき点、改善すべき点を洗い出し、具体的な改善計画を策定します。この際、経営層や現場の責任者とも連携し、全社的な理解と協力を得ることが成功の鍵となります。
採用テクノロジー導入の初期ステップ
採用テクノロジーの導入は、業務効率化や採用の質向上に大きく貢献しますが、やみくもに導入しても効果は期待できません。まずは、自社の採用課題を明確にし、その課題解決に最も寄与するテクノロジーは何かを見極めることが重要です。例えば、応募者管理に課題があるならATS、選考のスピードアップが目的ならオンライン面接ツールやAIによる書類選考支援などが考えられます。スモールスタートで導入し、効果を検証しながら段階的に活用範囲を広げていくアプローチが現実的です。導入にあたっては、現場の担当者が使いこなせるような研修やサポート体制も欠かせません。
継続的なトレンドウォッチと戦略のアップデート
採用トレンドは常に変化し続けるため、一度戦略を見直したら終わりではありません。業界の動向、競合他社の採用戦略、新たなテクノロジーの登場など、常に最新情報を収集し、自社の戦略を柔軟にアップデートしていく姿勢が求められます。人事関連のセミナーや勉強会への参加、専門メディアの購読、他社の人事担当者との情報交換などを通じて、常にアンテナを高く張っておくことが重要です。そして、定期的に採用戦略の効果測定を行い、データに基づいて改善を繰り返していくサイクルを確立しましょう。
採用戦略の立案はYUTORIにお任せください
貴社が抱える採用のお悩み、株式会社YUTORIが提供する「採用コンソーシアム」で解決しませんか。
「採用コストが増加している」「求人広告の効果が薄れてきた」「社内に採用ノウハウが蓄積されない」「中長期的な採用戦略が描けない」といった課題はありませんか。 YUTORIの採用コンソーシアムは、これらの悩みを多角的に解決するための新しい仕組みです。
私たちは、メディア運用、原稿作成、HP制作、広告分析、LINE運用など、各分野の専門知識を持つパートナー企業と連携し、「採用コンソーシアムチーム」を組成します。 このチームが一体となり、Webマーケティングを主軸とした戦略立案から実行まで、貴社の採用活動全体を最適化します。採用活動に関するお悩みがある企業様は、まずはお気軽にお問い合わせください。