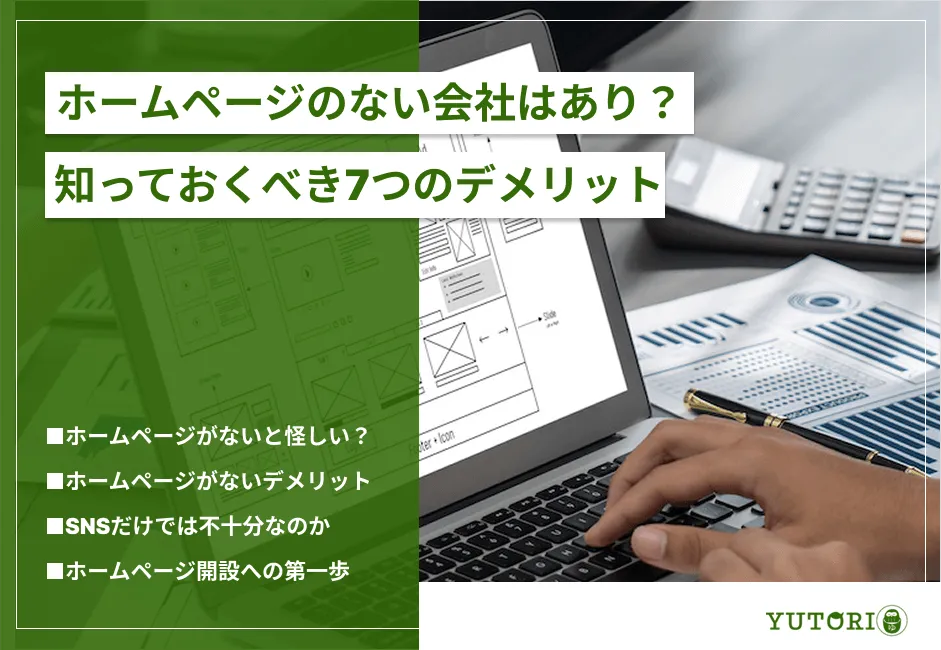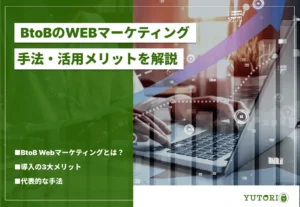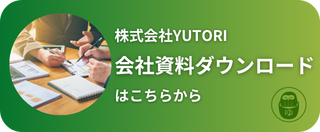現代のビジネスシーンにおいて、企業のホームページはもはや「あって当たり前」の存在です。顧客、取引先、そして未来の社員に至るまで、あらゆるステークホルダーが、会社を判断する最初の入り口としてホームページを訪れます。
本記事では、ホームページがないことで失われる信頼やビジネス機会、そしてそれらがもたらす経営上の具体的な7つのデメリットを徹底的に解説します。
目次
なぜ「ホームページがない会社は怪しい」と思われるのか?
インターネットが社会インフラとなった今、企業に関する情報を得ようとする人々が最初に行うのは「企業名での検索」です。その検索結果に公式サイトが表示されないという事実は、人々に「なぜ?」という疑問と、それに続く不信感を抱かせます。このセクションでは、なぜホームページがないだけで「怪しい」とまで思われてしまうのか、その具体的な理由を3つの視点から解説します。
デジタル時代の「会社の顔」であり「名刺」であるホームページ
かつて会社の信頼性を示すものが立派な社屋やパンフレットであったように、現代ではホームページがその役割を担っています。デザインや掲載されている情報を通じて、企業の理念、事業内容、そして文化までが伝わります。ホームページがないということは、デジタル社会において「顔」も「名刺」も持たずにビジネスを行っているのと同じです。第一印象を決める重要なツールを持たないことで、顧客や取引先に不信感や不安感を与えてしまいます。
顧客や取引先が最初に行う「オンライン与信調査」
新しい取引先を検討する際や、商品・サービスを購入する前に、その会社が本当に信頼できるのかを調べるのは当然の行動です。多くの人が、その第一歩として企業の公式ホームページを確認します。そこには、会社概要、事業実績、所在地、連絡先といった基本的な情報が掲載されているはずだと期待しているからです。ホームページが存在しない、あるいは情報が極端に少ない場合、「この会社は実在するのか?」「事業をきちんと行っているのか?」といった疑念を抱かれ、与信の段階で候補から外されてしまう可能性が非常に高くなります。
求職者が企業を判断する第一のフィルター
採用活動においてもホームページは決定的に重要です。今日の求職者、特に若手層は、応募を検討している企業のホームページを必ずと言っていいほどチェックします。彼らは、事業内容だけでなく、企業文化、社員の様子、将来性といった情報をホームページから読み取ろうとします。情報発信の場であるホームページがない企業は、求職者にとって「情報開示に積極的でない」「将来性が不安」といったネガティブな印象を与え、優秀な人材を獲得する機会を自ら手放していることになります。
ホームページがないことによる7つの経営デメリット
ホームページがないという事実は、単に「印象が悪い」という問題にとどまりません。売上減少、競争力の低下、採用コストの増大など、経営の根幹を揺るがす具体的なデメリットに直結します。ここでは、見過ごすことのできない7つの経営デメリットを一つずつ詳しく見ていきましょう。
デメリット1:潜在顧客に見つけてもらえず、ビジネスチャンスを逃す
現代の顧客は、何か商品やサービスを探すとき、まずスマートフォンやPCで検索します。例えば「地域名+サービス名」といったキーワードで検索された際、ホームページがなければ、あなたの会社は検索結果に表示されません。これは、自社の存在を知ってもらう最大の機会を逃していることを意味します。あなたの商品やサービスをまさに必要としている潜在顧客が、すぐ近くにいるにもかかわらず、その存在に気づいてもらえないのです。
デメリット2:比較検討の土俵に立てない
顧客が複数の企業を比較検討する際、その判断材料のほとんどは各社のホームページから得られます。ホームページがない企業は、この「比較検討の土俵」にすら上がることができません。たとえあなたの会社が優れた技術やサービスを持っていたとしても、その情報がなければ、最初から存在しないものとして扱われ、全ての見込み客は情報を提供している競合他社へと流れてしまいます。
デメリット3:企業の信頼性が低下する
BtoBの取引や金融機関からの融資審査など、企業の信頼性が問われる場面は数多くあります。公式サイトがないことは、事業の実態が不透明であると見なされ、信頼性の著しい低下につながります。結果として、新規取引の契約に至らなかったり、融資の審査で不利になったりと、ビジネスの根幹に関わる大きな不利益を被る可能性があります。
デメリット4:優秀な人材の採用機会を失う
前述の通り、求職者はホームページを通じて企業の情報を得ます。ホームページがないことで、自社の魅力やビジョンを伝える機会を失い、優秀な人材からの応募が期待できなくなります。結果として、有料の求人媒体への出稿費用や人材紹介会社への手数料など、採用コストが余計に増大してしまうという悪循環に陥ります。
デメリット5:24時間働く営業・広報ツールを持たない非効率
ホームページは24時間365日、機能し続ける優秀な営業・広報担当者です。事業内容を説明し、商品やサービスの魅力を伝え、問い合わせを受け付け、会社の最新情報を発信します。この強力なツールを持たないということは、ビジネスの多くをアナログな手法や人的リソースに頼らざるを得ず、極めて非効率な経営を続けることになります。
デメリット6:正しい情報を発信できず、ブランドイメージを毀損する
自社の公式ホームページがない場合、インターネット上に存在するあなたの会社に関する情報は、第三者が作成した古い求人情報や口コミサイト、非公式なまとめ記事などに限られてしまいます。これらの情報は必ずしも正確ではなく、ときにはネガティブな内容が含まれていることもあります。公式な情報発信源がないことで、誤った情報が独り歩きし、意図せずブランドイメージが毀損されるリスクを常に抱えることになります。
デメリット7:電話対応など、不要な業務コストが増加する
「営業時間は何時までですか?」「場所はどこですか?」といった基本的な問い合わせに、その都度電話で対応していませんか? これらの「よくある質問」は、本来ホームページに掲載しておけば顧客が自己解決できるものです。ホームページがないことで、本来必要のない問い合わせ対応に時間と人件費というコストを払い続けることになり、従業員はより生産性の高いコア業務に集中できなくなります。
ホームページがない会社によくある5つの思い込み
ここまでデメリットを解説してきましたが、それでもなお「自社には必要ない」と考える経営者の方も少なくありません。その背景には、ホームページに対するいくつかの「思い込み」があります。ここでは、代表的な5つの思い込みを挙げ、それがなぜ現代のビジネス環境において通用しないのかを解説します。
「コストがかかるだけで、費用対効果が見えない」
確かにホームページ制作には初期費用や維持費がかかります。しかし、近年では低価格で利用できるサービスやツールも数多く登場し、選択肢は大きく広がりました。そして何より、これまで述べてきた「機会損失」という目に見えないコストと比較すべきです。ホームページがもたらす新規顧客の獲得、採用コストの削減、業務効率の向上といったリターンを考えれば、その費用対効果は決して低くありません。
「小規模・地域密着だから必要ない」
「うちは近所のお客様が相手だから」という考えは、もはや通用しません。地域密着型のビジネスこそ、ホームページが不可欠です。なぜなら、地域の人々が飲食店や工務店、士業を探す際に「〇〇市 ラーメン」「〇〇町 水道修理」と検索するからです。Googleマップと連携したホームページがあれば、地域での認知度と集客力を飛躍的に高めることができます。
「既存の営業方法や紹介で十分うまくいっている」
現在はうまくいっているかもしれません。しかし、その顧客や紹介ルートは未来永劫続くでしょうか。顧客の世代交代や市場環境の変化によって、既存の方法がいつ通用しなくなるか分かりません。ホームページは、未来の顧客と接点を持つための重要な布石です。事業の継続性を考えたとき、新たな顧客獲得チャネルを構築しておくことは、リスク管理の観点からも極めて重要です。
「SNSがあればホームページは不要だ」
FacebookやInstagramなどのSNSは、確かに強力な情報発信ツールです。しかし、SNSはあくまで「フロー型」のメディアであり、情報は次々と流れていってしまいます。また、デザインの自由度が低く、あくまでプラットフォームの一機能に過ぎません。企業の公式情報や世界観を体系的に伝え、信頼性の基盤となる「ストック型」のホームページの役割を、SNSだけで代替することは不可能です。
「ITに詳しい社員がいないので、制作・運用できない」
この懸念は多くの企業が抱える問題ですが、もはやホームページ制作・運用に高度なITスキルは必須ではありません。専門知識がなくてもブログ感覚で更新できるCMS(コンテンツ・マネジメント・システム)や、プロの制作会社による手厚いサポートプランなど、IT担当者がいない企業でも安心して導入・運用できる環境が整っています。
SNSだけでは不十分? ホームページとの違い
「SNSで十分」という思い込みについて、もう少し深掘りしてみましょう。SNSとホームページは、似ているようでその役割と特性が全く異なります。両者をうまく使い分けることが重要ですが、企業の「核」となるのは間違いなくホームページです。ここでは、その3つの違いを解説します。
資産性:コンテンツが蓄積される「ストック型」メディア
SNSの投稿は時系列で流れ去る「フロー型」の情報です。一方、ホームページに掲載した会社概要、事業内容、実績、ブログ記事などは、削除しない限りインターネット上に蓄積され続ける「ストック型」の資産となります。これらの情報は検索エンジンの評価対象となり、長期間にわたって潜在顧客を呼び込み続ける貴重な情報資産へと成長していきます。
信頼性:公式情報としてのオーソリティ
SNSは誰もが気軽に発信できる反面、その情報の信頼性はホームページに劣ります。企業の「公式サイト」として存在するホームページは、発信される情報に公的な重みと権威(オーソリティ)を与えます。プレスリリースや重要なお知らせなど、企業の公式見解を発信する場として、ホームページの信頼性はSNSとは比較になりません。
自由度:デザインと情報掲載のコントロール
SNSは、運営会社の提供するプラットフォームの規約やデザインの枠内でしか情報を発信できません。突然の仕様変更や、最悪の場合アカウント凍結のリスクもゼロではありません。一方、自社で管理するホームページは、デザイン、コンテンツの構成、掲載する情報量など、全てを自社のブランド戦略に合わせて自由にコントロールできます。いわば、デジタルの世界における「自社の城」なのです。
ホームページ開設への選択肢
ホームページの重要性を理解した上で、次なるステップは「どうやって作るか」です。制作方法には大きく分けて、自社で制作する方法とプロに依頼する方法があります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、自社の予算や目的、人的リソースを考慮して最適な方法を選択することが成功の鍵となります。
選択肢1:自社で制作する(CMS、ノーコードツール)
WordPressのようなCMS(コンテンツ・マネジメント・システム)や、専門知識がなくても直感的な操作でサイトを構築できるノーコードツールを利用する方法です。
メリット:コストを低く抑えられる、思い立ったらすぐに始められる、簡単な修正や更新を自社で迅速に行える。
デメリット:デザインのテンプレート化や機能の制約がある、一定の学習時間が必要、セキュリティ対策などを自社で行う必要がある。
選択肢2:プロの制作会社に依頼する
Web制作の専門会社に企画からデザイン、構築、運用までを依頼する方法です。
メリット:クオリティの高いオリジナルデザインのサイトが作れる、集客やブランディングといった戦略的な視点での提案が受けられる、制作や運用の手間がかからない。
デメリット:自社制作に比べてコストが高くなる、制作会社との打ち合わせや意思疎通に時間がかかる。
ホームページ制作はYUTORIにご相談ください
この記事を通じて、ホームページの重要性をご理解いただけたことと思います。未来への投資としてホームページ制作をご検討の企業様は、ぜひ株式会社YUTORIにご相談ください。
YUTORIは、Webサイト制作やランディングページ制作といったWebクリエイティブ事業を軸に、採用支援、Webマーケティング、映像制作まで、企業成長を支える総合パートナーです。私たちは「あなたのビジネスに”ゆとり”を提供します」をスローガンに、お客様の課題解決に貢献します。
Webサイト制作に留まらず、集客を見据えたWebマーケティングやSNS運用、サイトに使用する写真撮影や動画制作まで、ワンストップでの対応が可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。