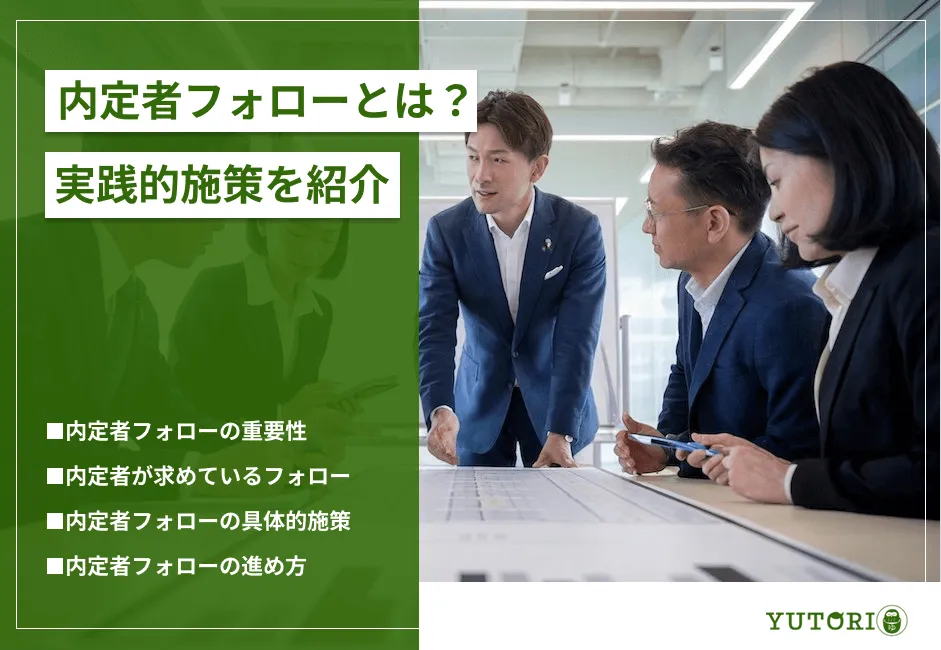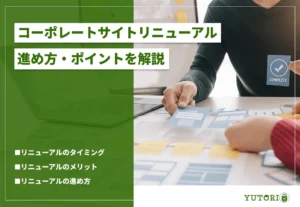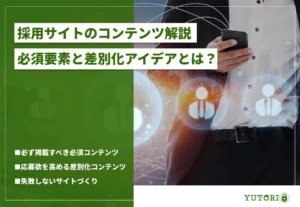優秀な人材を確保し、入社後に最大限のパフォーマンスを発揮してもらうために、「内定者フォロー」の重要性がかつてないほど高まっています。売り手市場やオンライン採用の普及により、学生は複数の内定を保持しながら、企業に対する不安や迷いを抱えやすくなりました。
本記事では、内定辞退や早期離職といった課題を解決するため、内定者フォローの重要性から、内定者が本当に求めていること、実践できる具体的な施策、そして避けるべきNG対応までを網羅的に解説します。
目次
内定者フォローの重要性
現代の採用活動において、内定はゴールではなく、エンゲージメントを高めるための新たなスタートラインです。なぜ今、これほどまでに内定者フォローが重要視されているのでしょうか。その背景には、採用市場の変化や働き方の多様化、そして見過ごすことのできない「コスト」の存在があります。
売り手市場と採用競争の激化がもたらす変化
近年の採用市場は、学生優位の「売り手市場」が続いています。少子化による労働人口の減少を背景に、多くの企業が採用目標人数の達成に苦戦しており、優秀な学生の獲得競争は激化の一途をたどっています。現代の学生にとって、複数の企業から内定を得ることは珍しくありません。企業側は「選考で学生を選ぶ」立場から、「内定を出した学生から選ばれる」立場へと変化しているのです。この状況下では、内定通知を送付しただけでは安心できません。内定承諾後も、学生の心を惹きつけ、自社で働く魅力を伝え続ける継続的なアプローチ、すなわち内定者フォローが不可欠となっています。
オンライン採用の普及が生んだ「内定者の新たな不安」とは
新型コロナウイルスの影響で急速に普及したオンライン採用は、時間や場所の制約をなくし、採用活動を効率化させた一方で、新たな課題も生み出しました。それは、内定者の「リアリティ・ショック」の増大です。オンラインの画面越しでは、企業の細かな雰囲気や社風、社員同士の何気ないコミュニケーションといった「生の情報」が伝わりにくくなります。その結果、内定者は「本当にこの会社に馴染めるだろうか」「どんな人たちと一緒に働くのだろうか」といった人間関係やカルチャーフィットに対する不安を、従来よりも強く抱える傾向にあります。この見えない不安を解消し、入社後のイメージを具体化させることが、オンライン時代の内定者フォローにおける重要な役割です。
内定辞退と早期離職が企業に与える本当のコスト
一人の内定辞退者や早期離職者が企業に与える損失は、決して小さくありません。求人広告費や人材紹介手数料といった直接的な採用コストはもちろんのこと、選考に費やした人事担当者や現場社員の時間的コストも無駄になってしまいます。さらに、採用計画が未達になれば事業計画に影響が及び、欠員が出れば既存社員の業務負荷が増大し、組織全体の士気低下につながる可能性も否めません。内定者フォローは、こうした金銭的・非金銭的な損失を防ぎ、採用活動の投資対効果を最大化するための極めて重要な経営戦略の一つと言えるのです。
内定者が本当に求めているフォローを理解する
効果的な内定者フォローを実施するためには、まず「内定者が何を不安に思い、何を求めているのか」を正確に理解することが不可欠です。企業側が良かれと思って提供する情報と、内定者が本当に知りたい情報には、しばしばギャップが存在します。ここでは、内定者が抱えがちな3つの不安要素を深掘りします。
不安要素①:人間関係とカルチャーフィットへの懸念
内定者が抱える最も大きな不安の一つが、「人間関係」と「組織文化への適応」です。特にオンライン選考が中心だった場合、面接官以外の社員と話す機会が少なく、職場のリアルな雰囲気を掴むことが困難です。「気の合う同期はいるだろうか」「配属先の上司や先輩はどんな人だろうか」「自分の価値観や働き方が、会社のカルチャーに合うだろうか」といった漠然とした不安は、入社直前まで彼らの心に影を落とします。この不安を解消するには、社員や同期と直接的・間接的に関わる機会を提供し、ありのままの組織風土を感じてもらうことが重要です。
不安要素②:自身のスキルと入社後の成長に対する自信のなさ
社会人経験のない学生は、「自分のスキルが仕事で本当に通用するのだろうか」「入社後、プロフェッショナルとして成長できる環境があるのか」といった、自身の能力とキャリアに対する不安を抱えています。特に、意欲の高い優秀な学生ほど、自身の成長可能性を重視する傾向が強いです。入社後の具体的な業務内容、求められるスキルセット、そして将来のキャリアパスが不明確なままだと、この不安は増大し、より成長機会が明確に見える他社へ心が揺らぐ原因となります。入社後の働く姿を具体的にイメージさせ、成長への期待感を醸成するフォローが求められます。
不安要素③:「もっと良い企業があるのでは」という迷い
売り手市場において、多くの内定者は複数の選択肢を手にしています。内定を承諾した後でも、SNSを通じて他社の情報に触れたり、友人から他社の魅力的な話を聞いたりするうちに、「本当にこの会社で良かったのだろうか」「もっと自分に合う、もっと良い条件の企業があったのではないか」という、いわゆる「内定ブルー」に陥ることがあります。この迷いを断ち切り、自社への入社意思を確固たるものにしてもらうためには、定期的なコミュニケーションを通じて自社の魅力を伝え続け、「あなたの選択は正しかった」という確信を持ってもらうことが不可欠です。
内定者フォローの具体的施策
内定者の不安を解消し、入社意欲を高めるためには、目的に応じた施策を戦略的に組み合わせることが効果的です。「交流」「情報提供」「スキルアップ」という3つの切り口から、実践的なフォロー施策をご紹介します。
交流を促し、帰属意識を高める施策
人間関係への不安を解消し、「この会社の一員になりたい」という気持ちを育むための施策です。
内定者懇親会(オンライン/オフライン)
内定者同士の連帯感を醸成する絶好の機会です。自己紹介やグループワークを取り入れ、相互理解を深めます。
先輩社員との座談会・質問会
年齢の近い若手社員から中堅・ベテラン社員まで、様々な立場の社員と話す機会を設けます。仕事のやりがいや苦労話など、リアルな声を聞くことで、入社後のイメージが具体化します。
メンター制度の導入
内定者一人ひとりに対して先輩社員をメンターとして付け、定期的な面談を実施します。些細な疑問や不安も気軽に相談できる存在は、内定者にとって大きな心の支えとなります。
内定者専用SNSグループの運営
SlackやLINE WORKSなどを活用し、内定者同士や人事担当者が気軽にコミュニケーションを取れる場を提供します。事務連絡だけでなく、雑談なども交えて活発なコミュニティを形成します。
情報提供で入社後のギャップをなくす施策
入社後の働き方やキャリアに対する解像度を高め、ミスマッチを防ぐための施策です。
社内報やWeb社内報の定期的な送付
会社の最新動向や社員の活躍、企業文化などを伝えることで、会社の「今」を共有し、帰属意識を高めます。
部署・プロジェクト紹介コンテンツの配信
各部署の業務内容やミッション、活躍する社員のインタビューなどを記事や動画で紹介します。配属への理解を深め、キャリアパスをイメージしやすくします。
「社員の1日」紹介
職種別に、若手社員や中堅社員の典型的な1日のスケジュールを紹介します。具体的な働き方をイメージすることで、入社後の生活に対する不安を軽減します。
経営層からのメッセージ発信
企業のビジョンや事業戦略、内定者への期待などを経営層から直接伝えることで、エンゲージメントと働くことへのモチベーションを高めます。
スキルアップを支援し、入社への期待感を醸成する施策
入社前の時間を有効に活用してもらい、スキルへの不安を自信に変えるための施策です。
eラーニングによる入社前研修
ビジネスマナー、PCスキル(Excel、PowerPointなど)、情報セキュリティ、業界知識といった社会人としての基礎スキルを学ぶ機会を提供します。
資格取得支援制度の案内・推奨
業務に関連する資格取得を推奨し、費用補助などの支援制度を案内します。明確な目標があることで、学習意欲が高まります。
課題図書の提示
企業の理念や事業内容の理解を深めるための書籍を数冊提示します(※強制にならないよう配慮が必要です)。感想を共有する会などを設けると、学びが深まります。
内定者アルバイト
希望者を対象に、入社前に実務を体験する機会を提供します。早期から業務理解を深め、社員との関係を構築できる有効な手段です。
成果を最大化する内定者フォローの進め方
内定者フォローは、やみくもに施策を打つのではなく、内定者の心理状態の変化に合わせて、フェーズごとに適切なアプローチを行うことが成功の鍵です。「内々定~内定承諾前」「内定承諾後~内定式」「内定式後~入社直前」の3つのフェーズに分けて、効果的な進め方を解説します。
内々定~内定承諾前:入社意思決定を後押しする
この時期の内定者は、複数の企業を比較検討し、まさに意思決定の最終段階にいます。フォローの目的は、彼らの疑問や不安を解消し、自社への入社を決断してもらうことです。
施策のポイント
個別性の高いコミュニケーション
一人ひとりの志望動機や懸念点に寄り添い、個別面談(リクルーター、現場社員、人事)を設定します。
オファー面談の実施
労働条件や待遇、入社後の配属や業務内容について丁寧に説明し、疑問点をクリアにします。
誠実な情報提供
学生が他社の選考状況について相談してきた場合も、真摯に耳を傾け、自社の魅力を客観的な事実に基づいて伝えます。強引な引き留めは逆効果です。
内定承諾後~内定式:関係性を深化させ、不安を解消する
無事に内定を承諾してもらった後も、油断は禁物です。入社までの期間が長いため、モチベーションの低下や「内定ブルー」に陥りやすい時期です。関係性を維持・深化させ、不安を解消することが目的となります。
施策のポイント
定期的な接点の創出
懇親会や座談会を企画し、同期や社員とのつながりを作ります。月1回程度のメルマガ配信や連絡で、忘れられていないという安心感を与えます。
双方向のコミュニケーション
企業からの情報発信だけでなく、内定者からの質問や相談を受け付ける窓口(メンターなど)を明確にし、いつでも頼れる体制を整えます。
内定式後~入社直前:社会人へのマインドセットを醸成する
入社が目前に迫り、内定者の期待と不安が最も高まる時期です。学生から社会人へのスムーズな移行をサポートし、万全の態勢で入社日を迎えられるようにすることが目的です。
施策のポイント
具体的な準備のサポート
入社手続きの案内、入社前研修の実施、社内ツールの紹介など、事務的・実践的なサポートを手厚く行います。
期待感の醸成
歓迎の意を込めたメッセージを配属予定部署の上司や経営層から送る、社内イベントに招待するなど、会社全体で心待ちにしている姿勢を伝えます。
【NG】志望度を下げてしまう内定者フォローの7つの注意点
良かれと思って行ったフォローが、かえって内定者の心象を悪化させ、内定辞退につながってしまうケースもあります。ここでは、人事担当者が陥りがちな7つのNG行動と、その注意点を解説します。
連絡頻度の間違い(過度な連絡と放置)
過度に頻繁な連絡は「監視されている」「束縛されている」というプレッシャーを与え、逆に連絡がなさすぎると「放置されている」「自分は本当に必要とされているのか」という不安を煽ります。月1回程度の定期連絡を基本とし、イベント案内などで適宜追加する、といったバランス感覚が重要です。
学生の学業やプライベートへの配慮不足
内定者フォローで最も忘れてはならないのは、彼らの本分が「学生」であるということです。卒業論文や研究、試験、学外活動などで多忙な時期に、過度な課題を課したり、イベントへの参加を強要したりするのは厳禁です。日程調整の際は複数の候補日を提示するなど、常に相手の都合を尊重する姿勢を示しましょう。
一方的な情報提供や課題の押し付け
企業が伝えたい情報だけを一方的に送りつけたり、内定者のレベルや興味を無視した課題を課したりするのは、エンゲージメントを下げる典型的な失敗例です。内定者が何を知りたいのか、何に興味があるのかをヒアリングし、双方向のコミュニケーションを心がけることが大切です。
不誠実・不透明なコミュニケーション
質問に対して曖昧な回答をしたり、担当者によって言うことが異なったりすると、内定者は企業に対して強い不信感を抱きます。特に、給与や配属、福利厚生といった重要な情報については、誠実かつ一貫性のある説明が求められます。不明な点は確認してから回答するなど、真摯な対応を徹底しましょう。
研修参加の強制と給与未払いのリスク
入社前の研修や課題について、事実上参加を強制している場合、それは「業務」と見なされ、企業には賃金の支払い義務が発生する可能性があります。あくまで参加は任意であることを明確に伝え、内定者の自由意思を尊重する必要があります。コンプライアンス違反のリスクを正しく理解しておきましょう。
オンライン/オフラインのバランスの欠如
オンラインの施策は手軽ですが、それだけでは人間関係の構築や企業文化の深い理解には限界があります。一方で、オフラインのイベントばかりでは、地方在住の学生などに大きな負担をかけてしまいます。両者のメリット・デメリットを理解し、オンラインでの情報提供とオフラインでの交流会などをバランス良く組み合わせることが理想的です。
担当者による対応のばらつき
人事担当者やメンター、現場社員など、内定者フォローに関わる人物は複数にわたります。それぞれの担当者で対応の質や熱量にばらつきがあると、内定者は不公平感や戸惑いを感じてしまいます。フォローの目的や方針、伝えるべき情報を関係者間で事前に共有し、組織として一貫した対応を心がけることが重要です。
内定者フォロー施策に関するご相談はYUTORIにお任せください
内定者フォローをはじめ、採用活動のあらゆる課題に対し、株式会社YUTORIは独自の「採用コンソーシアム」という形で解決策をご提案します。採用コンソーシアムは、メディア運用、HP制作、広告分析など、各分野の専門家と連携し、貴社の課題に応じた最適なサポートを提供するサービスです。
Webマーケティングを主軸とし 、短期的な応募単価の削減といったコスト効率の改善 から、自社採用サイトの構築・運用といった中長期的な採用力の強化まで 、持続可能な採用体制の構築を支援します。
貴社の採用チームの一員として伴走し、採用ノウハウの蓄積や内製化までサポートすることが可能です。採用に関するお悩みは、ぜひお気軽にご相談ください。