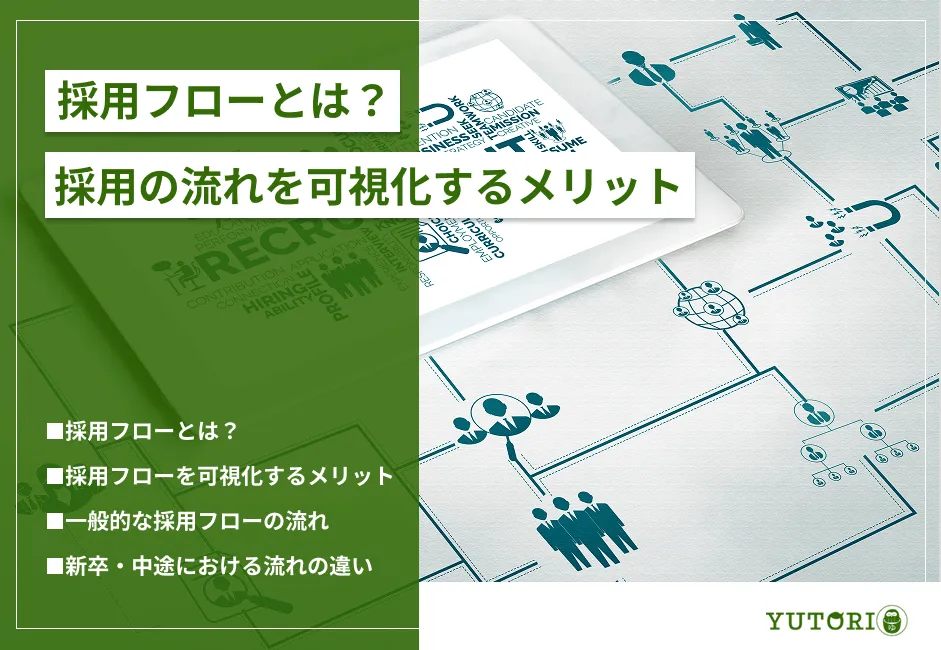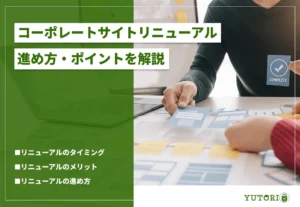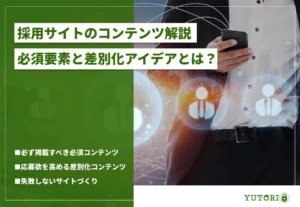採用活動が思うように進まない、優秀な人材になかなか出会えない、選考途中の辞退者が多い。こうした課題を抱える人事担当者様は少なくないでしょう。その解決の鍵を握るのが、採用活動の「設計図」ともいえる採用フローです。
本記事では、採用フローの基本的な定義から、その作成・可視化がもたらす具体的なメリット、さらには設計前の準備、具体的なステップ、そして継続的な改善手法までを網羅的に解説します。
目次
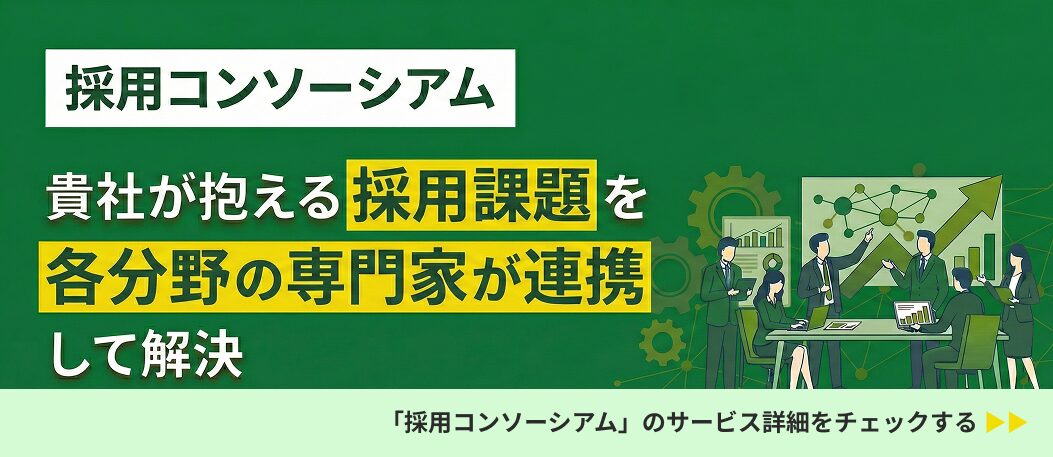
採用フローとは?
採用フローとは、企業が人材を募集し始めてから、候補者が選考を経て内定、そして実際に入社するまでの一連のプロセス(流れ)全体を指します。具体的には、「母集団形成(募集)→書類選考→面接(複数回)→内定→入社」といった各ステップで構成されます。この流れを明確に定義し、図式化・言語化することで、採用活動全体を体系的に管理することが可能になります。
なぜ採用フローの可視化が重要なのか?
近年の労働市場は、少子高齢化による生産年齢人口の減少を背景に「売り手市場」が続いており、企業間の人材獲得競争は激化しています。このような状況下で、候補者から「選ばれる」企業になるためには、採用活動の質を高めることが急務です。
採用フローを可視化することで、選考プロセスがスムーズに進み、候補者に与える印象(候補者体験)が向上します。また、採用に関わるメンバー全員が共通認識を持って活動できるため、選考の精度やスピードが上がり、結果として採用競争力を高めることに繋がるのです。
採用フローを作成・可視化する3つのメリット
採用フローをただ作るだけでなく、関係者全員が見える形に「可視化」することには、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは、採用フローを可視化することによって得られる3つの大きなメリットを詳しく解説します。
採用関係者間の認識統一と連携強化
採用活動には、人事担当者だけでなく、現場の部門長、役員など、多くの社員が関わります。採用フローが可視化されていないと、「誰が」「いつ」「何を」すべきかが曖昧になり、選考の遅延や評価基準のズレといった問題が生じがちです。
採用フローを明確にすることで、各担当者の役割と責任範囲がクリアになります。面接官ごとの評価のバラつきを防ぎ、一貫性のある選考を実現できるため、組織全体として最適な人材を見極める精度が高まります。
候補者体験(CX)の向上と辞退率の低下
候補者体験とは、候補者が企業を認知してから選考を受け、入社に至るまでのプロセス全体で感じる「体験の価値」を指します。採用フローが整理されている企業は、連絡が迅速で、次のステップが分かりやすく、候補者に安心感と信頼感を与えます。
逆に、プロセスが不透明で対応が遅い企業は、候補者の入社意欲を削いでしまいます。採用フローを可視化・最適化することは、候補者体験を向上させ、選考途中や内定後の辞退率を低下させるための重要な施策です。
データに基づいた採用課題の発見と改善
採用フローを可視化する最大のメリットの一つが、採用活動をデータに基づいて分析・改善できる点です。各選考ステップ(書類選考、一次面接、最終面接など)の応募者数、通過者数、辞退者数を記録することで、各段階の「通過率」や「辞退率」を算出できます。
例えば、「一次面接から二次面接への通過率が極端に低い」というデータが出れば、一次面接の評価基準に問題があるのではないか、といった仮説を立てることができます。このように、感覚ではなく客観的なデータに基づいてボトルネックを特定し、的確な改善策を講じることが可能になります。
採用フロー設計の前に不可欠な「採用計画」の立て方
効果的な採用フローは、その土台となる「採用計画」がしっかりしていて初めて機能します。やみくもにフローを作り始める前に、まずは「誰を」「なぜ」「どのように」採用するのかを明確に定義しましょう。ここでは、採用計画を立てるための4つのステップを紹介します。
採用目標の設定(人数・時期・ポジション)
まずは、経営計画や事業戦略と連動した採用目標を設定します。具体的には、「いつまでに」「どの部署に」「どのような役職の人材を」「何名」採用するのかを明確にします。この目標が、採用活動全体のゴールとなり、スケジュールや予算を策定する上での基礎となります。
求める人物像(ペルソナ)の明確化
次に、採用したい人材の具体的なイメージを「ペルソナ」として描き出します。ペルソナとは、年齢や性別といった基本情報に加え、保有スキル、実務経験、価値観、性格、キャリアプランなどを詳細に設定した架空の人物像です。ペルソナを明確にすることで、採用関係者間での認識のズレがなくなり、ターゲットに響く求人情報の作成や、適切な採用手法の選定に繋がります。
採用基準と評価項目の策定
設定したペルソナに基づき、選考で「何を」「どのように」評価するのかという採用基準を具体的に定めます。スキルや経験といった「MUST要件(必須条件)」と、人柄やポテンシャルといった「WANT要件(歓迎条件)」に分けて整理すると良いでしょう。さらに、面接で確認すべき質問項目や評価シートを事前に準備しておくことで、面接官による主観的な評価を防ぎ、公平で客観的な選考が可能になります。
採用手法の選定と予算の策定
採用ターゲットであるペルソナに最も効果的にアプローチできる採用手法を選定します。求人広告、人材紹介、ダイレクトリクルーティング、リファラル採用など、様々な手法のメリット・デメリットを比較検討し、自社の状況に合わせて組み合わせます。使用する手法が決まったら、各サービスの利用料や広告費などを見積もり、採用活動全体の予算を策定します。
一般的な採用の流れ(採用フロー)
採用計画が固まったら、いよいよ具体的な採用フローを構築します。ここでは、新卒・中途採用で共通して用いられることの多い、一般的な採用フローを8つのステップに分けて解説します。
Step 1: 母集団形成(募集活動)
採用したい人材層(ペルソナ)が集まる可能性の高いチャネル(求人サイト、SNS、人材紹介など)を活用し、自社の求人情報を発信します。企業の魅力を伝え、多くの候補者からの応募を促す、採用活動の入り口となる重要な段階です。
Step 2: 書類選考
応募者から提出された履歴書や職務経歴書をもとに、事前に定めた採用基準と照らし合わせ、求める経験やスキルを満たしているかを確認します。この段階で、候補者を一定数に絞り込みます。
Step 3: 適性検査・筆記試験
書類選考だけでは分からない候補者の潜在的な能力、性格、ストレス耐性などを客観的に評価するために実施します。特に新卒採用では、SPIや玉手箱といった適性検査が広く用いられます。
Step 4: 面接(複数回)
採用フローの中核となるステップです。通常、1〜3回程度の面接を実施します。一次面接では人事や現場担当者が基礎的なスキルや人柄を確認し、二次面接では所属部署の管理職が専門性やチームへのフィット感を見極めるなど、各回で目的と評価者を変えるのが一般的です。
Step 5: 最終選考(役員面接など)
役員や社長が面接官となり、候補者の入社意欲の高さや、企業理念とのマッチ度、将来性などを最終的に判断します。候補者にとっても、経営層と直接対話し、企業のビジョンを深く理解する貴重な機会となります。
Step 6: 内定通知と条件交渉
最終選考を通過した候補者に対して、採用の意思を伝える「内定通知」を行います。電話で一報を入れた後、労働条件(給与、役職、勤務地など)を明記した内定通知書を送付するのが一般的です。必要に応じて、条件面の交渉を行います。
Step 7: 内定者フォロー
内定承諾後から入社日までの間、候補者の入社意欲を維持し、不安を解消するためのフォローを行います。定期的な連絡、内定者懇親会の開催、現場社員との面談などを通じて、企業との繋がりを強化し、内定辞退を防ぎます。
Step 8: 入社準備と受け入れ
入社に必要な書類の案内や手続きを進めるとともに、社内の受け入れ体制を整えます。PCやデスクの準備、オリエンテーションの計画など、新入社員がスムーズに業務を開始できる環境を用意することが重要です。
【対象別】新卒・中途採用における流れの違いとポイント
採用フローは、採用ターゲットによって最適化する必要があります。ここでは、大きな違いがある「新卒採用」と「中途採用」のフローについて、それぞれの特徴と設計のポイントを解説します。
新卒採用のフロー
新卒採用は、社会人経験のない学生を対象とするため、現時点でのスキルよりも将来性や学習意欲といった「ポテンシャル」を重視します。広報活動の開始から入社まで1年以上に及ぶ長期戦となるのが特徴です。会社説明会やインターンシップを通じて企業理解を深めてもらう期間が重要となり、選考フローも筆記試験やグループディスカッションなど、多角的に候補者を評価するステップが組み込まれる傾向にあります。
中途採用のフロー
中途採用は、特定のポジションで即戦力となる人材を求めるため、「スキル」や「実務経験」が最も重要な評価基準となります。候補者も在職中に転職活動を行うことが多く、選考はスピードが命です。募集開始から1〜2ヶ月で内定・入社となるのが一般的で、フローも書類選考と数回の面接のみ、といったシンプルな形が多く見られます。現場のニーズとのマッチングが重要になるため、配属予定先の社員が面接に同席することが不可欠です。
採用フローの代表的な5つの型
採用フローには、基本的な流れ以外にも、企業の目的や採用ポジションに応じて様々な「型」が存在します。ここでは代表的な5つの型を紹介します。
標準型
「募集→書類選考→面接(複数回)→内定」という、最もオーソドックスなフローです。多くの企業で採用されており、汎用性が高いのが特徴です。
説明会・選考一体型
会社説明会の当日に、希望者を対象として一次選考(面接やグループワーク)まで実施するフローです。候補者の時間的負担を軽減し、選考プロセスを高速化できるため、多くの応募者を集めたい場合や、スピーディーな採用が求められる場合に有効です。
試験先行型
エンジニアやデザイナーなど、専門的な知識やスキルが必須となる職種で用いられるフローです。面接の前にプログラミングテストやポートフォリオ審査といった実技試験を先行して行い、一定のスキルレベルを持つ候補者のみを面接に進めます。
インターンシップ型
学生に一定期間、実際の業務を体験してもらうインターンシップを選考プロセスに組み込むフローです。企業は候補者の働きぶりやカルチャーフィットをじっくり見極めることができ、学生は企業や仕事への理解を深めることができます。ミスマッチの少ない採用が期待できます。
リファラル/ダイレクト型
社員紹介(リファラル採用)や、企業から候補者に直接アプローチするダイレクトリクルーティングで用いられるフローです。すでにある程度の信頼関係やスキルへの理解があるため、書類選考や一次面接を省略し、カジュアルな面談から始めるなど、柔軟でスピーディーな選考が可能です。
採用フローを「改善」し続けるための実践的手法
採用フローは一度作ったら終わりではありません。市場環境や企業のフェーズに合わせて、常に見直しと改善を続けることが、採用成功の確率を高める上で非常に重要です。ここでは、採用フローを改善し続けるための実践的な手法を紹介します。
各選考段階の「歩留まり」を算出しボトルネックを特定する
「歩留まり」とは、ある選考段階に進んだ候補者のうち、次の段階に進んだ候補者の割合を指します。例えば、100人が応募し、書類選考を通過したのが30人だった場合、書類選考の歩留まり(通過率)は30%です。各段階の歩留まりを算出することで、「どのステップで多くの候補者が離脱しているのか」というボトルネックを客観的な数値で特定できます。
課題別・改善策の具体例
ボトルネックが特定できたら、具体的な改善策を検討・実行します。
応募が集まらない場合
求人票の魅力が伝わっているか見直す、採用チャネルを増やす、スカウトメールの文面を工夫する。
書類選考の通過率が低すぎる場合
募集要件が厳しすぎないか、求める人物像が市場の実態と乖離していないかを見直す。
面接の辞退が多い場合
日程調整の連絡を迅速に行う、オンライン面接を導入するなど候補者の負担を軽減する、面接官のトレーニングを実施し面接の質を高める。
内定辞退が多い場合
オファー面談で条件や業務内容を丁寧に説明する、内定者懇親会などで既存社員との交流機会を設け、入社後のイメージを掴んでもらう。
定期的な見直しとアップデートの重要性
採用市場のトレンドや競合の動向、自社の事業戦略は常に変化します。そのため、採用フローも一度決めたら固定するのではなく、半期に一度、あるいは採用プロジェクトごとに振り返りを行い、アップデートしていくことが重要です。定期的な見直しを通じて、常により効果的な採用活動を目指しましょう。
採用施策に関するお困りごとはYUTORIにご相談ください
「採用コストが増加している」 「求人広告の効果が薄れてきた」 「社内に採用ノウハウがなかなか蓄積されない」。本記事で解説した採用フローの構築・改善とあわせて、このような採用に関する多角的なお悩みを抱えていませんか。株式会社YUTORIでは、専門性を持つ複数のパートナー企業と連携し、貴社の採用課題を多面的に解決する「採用コンソーシアム」という仕組みをご提供しています。
私たちは、貴社の採用チームの一員として課題に寄り添い、短期的な成果だけでなく、中長期的な視点で採用力の育成をサポートします。各分野のプロフェッショナルが連携し、貴社の状況に応じたオーダーメイド型の柔軟な対応が可能です。採用課題の解決に向けて、ぜひお気軽にご相談ください。