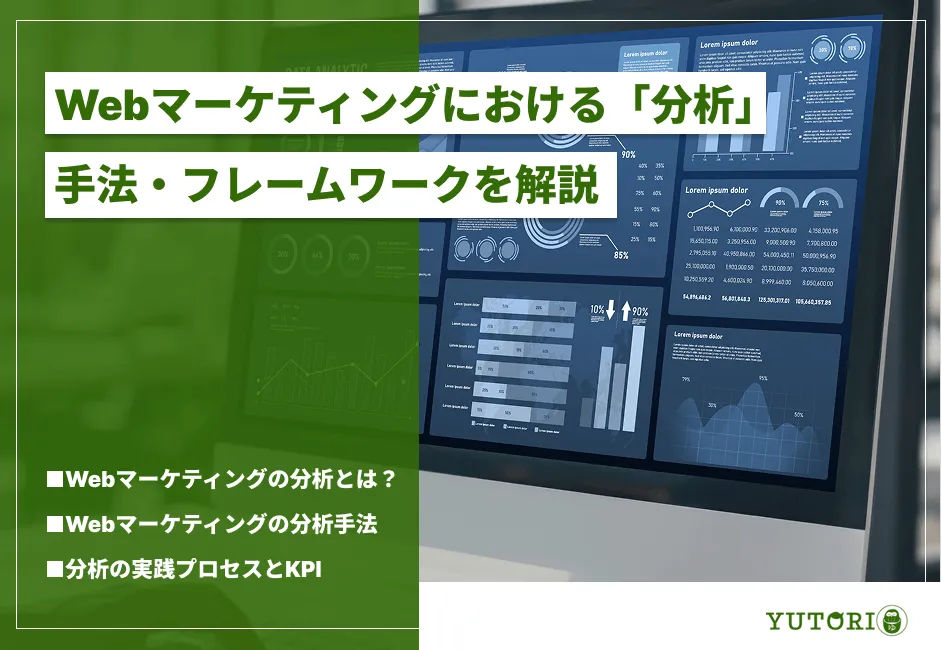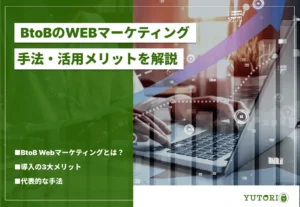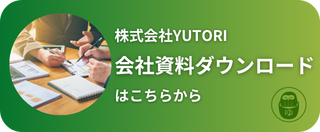Webマーケティングの重要性が叫ばれる一方で、「Webサイトや広告から思うような成果が出ない」「データを眺めてはいるが、次に何をすべきか分からない」といった課題を抱えているご担当者様は多いのではないでしょうか。その課題を解決し、事業成長を加速させるための指針となるのが、本記事のテーマである「分析」です。
この記事では、Webマーケティングにおける分析の本質から、目的別の具体的な手法・フレームワーク、実践的なプロセス、さらには分析を成果に繋げるための思考法まで、網羅的に解説します。
目次
Webマーケティングにおける分析とは?
Webマーケティングにおける分析とは、単に数値を眺めることではありません。集めたデータから事業の現状を正しく理解し、課題や機会を発見して、次の一手(アクション)に繋げるための一連の知的活動です。
「分析」と「解析」の違い
「分析」と似た言葉に「解析」があります。この二つは混同されがちですが、その役割は異なります。
解析(Analytics):
データを収集し、指標ごとに分類・整理して、現状を客観的に可視化すること。「アクセス数が先月比で10%減少した」という事実を把握する段階です。
分析(Analysis):
解析によって可視化されたデータをもとに、「なぜそうなったのか?」という原因を掘り下げ、課題を特定し、改善策の仮説を立てること。「アクセスの減少は、特定の広告キャンペーンの停止が原因ではないか」と考察する段階です。
解析が「What(何が起きたか)」を把握するのに対し、分析は「Why(なぜ起きたか)」を解明し、「How(どうすべきか)」に繋げるプロセスと言えます。
データが導く事業成長の重要性
かつてのマーケティングは、担当者の経験や勘に頼る部分が多くありました。しかし、ユーザーの行動が多様化・複雑化する現代において、経験則だけでは限界があります。 データに基づいた分析を行うことで、客観的な事実をもとに仮説を立て、施策を実行し、その結果を再びデータで評価するという科学的なアプローチが可能になります。
施策の成功確率を高め、再現性のある成長サイクルを生み出すことができるのです。
分析によって得られる3つの主要なメリット
データ分析をマーケティング活動に取り入れることで、具体的にどのようなメリットが得られるのでしょうか。ここでは主要な3つのメリットをご紹介します。
課題の早期発見と機会の特定
定期的にデータを観測することで、売上の減少やユーザー離脱率の上昇といった事業上の課題を早期に察知できます。例えば、特定のページの離脱率が急に高まった場合、そのページのデザインやコンテンツに何らかの問題が発生した可能性にいち早く気づけます。 同時に、データは新たなビジネスチャンスも示してくれます。想定していなかったキーワードからの流入が増えている、特定の顧客層からのコンバージョン率が非常に高い、といったデータは、新たなターゲット市場や商品開発のヒント(機会)になり得ます。
マーケティング施策の最適化とROI向上
Webマーケティングでは、SEO、広告、SNS、メールマガジンなど、様々な施策を同時に展開します。分析を行うことで、どの施策がどれだけ成果(コンバージョン)に貢献しているかを数値で明確に評価できます。 成果の高い施策には予算やリソースを集中させ、効果の低い施策は改善または停止するといった判断が可能になり、マーケティング投資全体の費用対効果(ROI:Return On Investment)を最大化することができます。
顧客理解の深化と関係構築
アクセス解析データは、ユーザーの「声なき声」の宝庫です。ユーザーがどのようなキーワードでサイトを訪れ、どのページを熱心に読み、どこで離脱してしまうのか。これらの行動データを分析することで、顧客が何を求め、何に不満を感じているのか、そのインサイトを深く理解することができます。 顧客理解が深まれば、一人ひとりのニーズに合わせた情報提供やアプローチが可能となり、顧客との良好な関係構築に繋がります。
Webマーケティングの主要分析手法・フレームワーク
Webマーケティングの分析には、思考を整理し、抜け漏れなく現状を把握するための様々な「フレームワーク」が存在します。ここでは、代表的なフレームワークを「外部環境・市場」「自社・内部資源」「顧客」「戦略策定」という4つの目的別に分類してご紹介します。
外部環境と市場を把握するためのフレームワーク
自社を取り巻くビジネス環境や市場の全体像を捉えるためのフレームワークです。
3C分析
「Customer(市場・顧客)」「Competitor(競合)」「Company(自社)」の3つのCの観点から、自社の事業環境を分析する最も基本的なフレームワークです。市場のニーズはどこにあるのか、競合の強み・弱みは何か、そして自社の強みをどこで活かせるのか、といった成功要因を見つけ出すのに役立ちます。
PEST分析
「Politics(政治)」「Economy(経済)」「Society(社会)」「Technology(技術)」という4つのマクロな外部環境要因が、自社にどのような影響を与えるかを分析する手法です。法改正や景気変動、流行、技術革新など、自社ではコントロールできない大きな変化を予測し、中長期的な戦略を立てる際に活用します。
ファイブフォース分析
業界の構造を分析し、その業界の収益性を決定する5つの競争要因(Force)を明らかにするフレームワークです。「競合との敵対関係」「新規参入の脅威」「代替品の脅威」「売り手の交渉力」「買い手の交渉力」の5つの力関係を分析することで、自社が属する業界の魅力度や、その中での収益獲得の難易度を評価します。
自社の立ち位置と内部資源を評価するフレームワーク
外部環境を踏まえた上で、自社の強みや弱み、立ち位置を客観的に評価するためのフレームワークです。
SWOT分析
自社の内部環境である「Strength(強み)」「Weakness(弱み)」と、外部環境である「Opportunity(機会)」「Threat(脅威)」の4つの要素を整理し、分析する手法です。これらの要素を掛け合わせる「クロスSWOT分析」を行うことで、「強みを活かして機会を掴む」といった具体的な戦略オプションを導き出すことができます。
VRIO分析
企業の持つ経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報など)が、競争優位性の源泉となるかを評価するためのフレームワークです。「Value(経済的価値)」「Rarity(希少性)」「Imitability(模倣困難性)」「Organization(組織)」の4つの問いに答える形で分析を進め、自社の真の強みが何かを特定します。
顧客を深く理解するためのフレームワーク
Webサイトのデータなどを活用し、顧客の行動や属性を理解するためのフレームワークです。
ファネル分析
ユーザーが商品を認知してから購入・契約に至るまでの心理や行動のプロセスを、漏斗(ファネル)のような形で図式化し、各段階でどれくらいのユーザーが次の段階へ進んだか(あるいは離脱したか)を分析する手法です。ボトルネックとなっている段階を特定し、改善策を講じるのに役立ちます。
RFM分析
顧客の購買行動を「Recency(最終購入日)」「Frequency(購入頻度)」「Monetary(累計購入金額)」の3つの指標で分析し、顧客をランク付けする手法です。優良顧客、休眠顧客などを特定し、それぞれのグループに適したアプローチ(例:優良顧客には限定セールの案内、休眠顧客には再訪を促すクーポン発行など)を行うのに有効です。
バスケット分析
「この商品を買った人は、こちらの関連商品も一緒に買う傾向がある」といった、商品の併売パターンを見つけ出すデータ分析手法です。ECサイトのレコメンド機能の最適化や、セット販売の企画、実店舗での商品陳列の改善などに活用されます。
マーケティング戦略を策定するためのフレームワーク
分析結果をもとに、具体的なマーケティング戦略を策定するためのフレームワークです。
STP分析
効果的な市場を狙うために、「Segmentation(市場細分化)」「Targeting(ターゲット選定)」「Positioning(自社の立ち位置の明確化)」の3つのステップで分析を進める手法です。市場全体を同じニーズを持つグループに分け(S)、その中から自社が狙うべきグループを定め(T)、競合との差別化ポイントを明確にする(P)ことで、戦略の精度を高めます。
4P分析・4C分析
マーケティング戦略の具体的な実行計画(マーケティングミックス)を策定する際に用いられるフレームワークです。
4P分析(企業視点):
「Product(製品)」「Price(価格)」「Place(流通)」「Promotion(販促)」の4つの要素をどう組み合わせるかを考えます。
4C分析(顧客視点):
4Pを顧客側から捉え直したもので、「Customer Value(顧客価値)」「Cost(顧客コスト)」「Convenience(利便性)」「Communication(コミュニケーション)」の4要素で考えます。 これらをセットで用いることで、企業本位ではない、顧客に寄り添った戦略を立てることができます。
Webマーケティング分析の実践プロセス
フレームワークを学んでも、いざ実践するとなると何から手をつければ良いか迷ってしまうかもしれません。ここでは、分析を成果に繋げるための具体的な5つのステップをご紹介します。
Step 1:目標設定(KGI・KPI)を明確にする
分析を始める前に、まず「何のために分析するのか」という目的を明確にする必要があります。そのために設定するのが、KGIとKPIです。
KGI(Key Goal Indicator/重要目標達成指標):
事業の最終的な目標を測る指標です。「売上高」「利益率」「成約数」などが該当します。
KPI(Key Performance Indicator/重要業績評価指標):
KGIを達成するための中間的な目標を測る指標です。KGIが「ECサイトの売上月1,000万円」なら、KPIは「サイトへのセッション数」「購入率(CVR)」「客単価」などに分解されます。
最初にKGI・KPIを設定することで、見るべきデータが明確になり、分析の軸がブレなくなります。
Step 2:適切なツールを選定し、データを収集する
設定したKPIを計測するために、適切なツールを選定し、データを収集できる環境を整えます。Webマーケティングにおいては、後述する「Googleアナリティクス」や「Googleサーチコンソール」が基本のツールとなります。その他、広告の効果測定ツールやSNSの分析ツールなど、目的に応じて必要なツールを導入します。
Step 3:フレームワークを活用してデータを分析する
収集したデータを、目的に合ったフレームワークに当てはめて整理・分析します。例えば、サイト全体のユーザー行動に課題がありそうなら「ファネル分析」を、競合と比較した自社の立ち位置を見直したいなら「3C分析」や「SWOT分析」を用いる、といった形です。データとにらめっこするだけでなく、フレームワークという型を使うことで、思考が整理され、本質的な課題が見えやすくなります。
Step 4:課題を特定し、改善策(アクションプラン)を策定する
分析によって明らかになった事実から、「なぜそうなっているのか?」という原因を考察し、取り組むべき「課題」を特定します。そして、その課題を解決するための具体的な「改善策(アクションプラン)」に落とし込みます。「誰が」「いつまでに」「何を」「どのように」実行するのかを明確にすることが重要です。
Step 5:施策を実行し、効果測定と改善を繰り返す
策定したアクションプランを実行します。そして、実行したら終わりではなく、必ずその施策がKPIにどのような影響を与えたのか「効果測定」を行います。期待通りの成果が出れば継続・発展させ、そうでなければ原因を再度分析し、新たな改善策を立てて実行します。このサイクルを粘り強く回し続けることが、Webマーケティングを成功に導く鍵となります。
分析に不可欠なツールと押さえるべき主要指標(KPI)
Webマーケティング分析を実践する上で、必須となるツールと、必ず押さえておくべき主要な指標(KPI)について解説します。まずはここから始めてみましょう。
基本となるアクセス解析ツール
Webサイトのデータを分析するための、無料で利用できる非常に強力なツールです。
Googleアナリティクス
Webサイトに訪れたユーザーの行動を詳細に分析できるツールです。「ユーザーが何人来たか」「どこから来たか」「どのページを見たか」「どれくらい滞在したか」といった、サイト内のユーザー行動に関するほぼ全てのデータを取得・解析できます。Webマーケティングの分析は、まずこのツールを使いこなすことから始まります。
Googleサーチコンソール
ユーザーがサイトに訪れる「前」の、Google検索におけるパフォーマンスを分析できるツールです。「どのような検索キーワードで表示されたか(インプレッション数)」「そのうち何回クリックされたか(クリック数)」「検索結果の何位に表示されたか(掲載順位)」などを把握できます。SEO対策を進める上で不可欠なツールです。
施策別に追うべき主要KPIの例
分析の際には非常に多くの指標を目にしますが、ここでは特に重要となる基本的なKPIをいくつかご紹介します。
CVR(コンバージョン率)とCV数(コンバージョン数)
コンバージョン(CV)とは、Webサイトにおける最終的な成果のことで、「商品購入」「資料請求」「問い合わせ」などを指します。CV数はその絶対数、CVRはサイト訪問者のうち何パーセントがコンバージョンに至ったかを示す割合です。事業の売上に直結する最重要指標と言えます。
CVR(%) = コンバージョン数 ÷ セッション数(またはクリック数) × 100
CTR(クリック率)とインプレッション数(表示回数)
インプレッション数は、広告や検索結果がユーザーの画面に表示された回数です。CTRは、表示された回数のうち、どれだけクリックされたかを示す割合です。この数値が高いほど、ユーザーの興味を惹きつける魅力的なタイトルや広告文であると評価でき、サイトへの集客効率を示す重要な指標となります。
CTR(%) = クリック数 ÷ インプレッション数 × 100
PV数(ページビュー数)、セッション数、直帰率
PV数:
Webサイト内のページが閲覧された総回数。
セッション数:
ユーザーがサイトを訪問した回数。1回の訪問(セッション)で複数のページを見ることもあります。
直帰率:
ユーザーがサイトに訪問し、最初の1ページだけを見てサイトを離れてしまったセッションの割合。
これらの指標は、サイトがどれだけ閲覧されているか、ユーザーがサイト内をどれだけ回遊してくれているか、といったサイト自体の魅力を測るための基本的な指標です。
分析を「やって終わり」にしないための思考法
最後に、分析を単なるデータ整理で終わらせず、真にビジネスの成果に繋げるために心得るべき3つの思考法をご紹介します。
フレームワークは思考の整理道具であり、目的ではない
3C分析やSWOT分析などのフレームワークは、あくまで思考を整理し、分析を効率化するための「道具」です。フレームワークの各項目を埋めること自体が目的になってしまうと、本質的な課題の発見や、斬新なアイデアの創出には繋がりません。重要なのは、フレームワークを通じて得られた示唆をもとに、「だから何なのか?」「次に何をすべきか?」を考え抜くことです。
定量データと定性データの両面からインサイトを導き出す
Googleアナリティクスなどで得られるアクセス数やCVRといった数値データは「定量データ」と呼ばれます。これは「何が起きたか」を客観的に示してくれます。 一方で、ユーザーアンケートやインタビューで得られる「お客様の声」や、SNS上の口コミなどは「定性データ」と呼ばれ、「なぜそう感じたのか」というユーザーの感情や背景を理解するのに役立ちます。 この両者を組み合わせることで、数値の裏にあるユーザー心理(インサイト)を深く洞察し、より的確な改善策に繋げることができます。
PDCAサイクルを回し、継続的な改善文化を醸成する
分析から施策立案、実行、効果測定までの一連の流れは、一度きりで終わるものではありません。「Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Action(改善)」というPDCAサイクルを、高速で、そして継続的に回し続けることが不可欠です。 小さな成功と失敗を繰り返しながら、学びを蓄積し、次の改善に活かしていく。このプロセスを個人だけでなく、チームや組織全体の文化として根付かせることが、変化の速いWebマーケティングの世界で勝ち続けるための鍵となります。
WEBサイトの分析・改善はYUTORIにご相談ください
株式会社YUTORIは、Webサイト制作から広告運用、分析・改善まで、Webマーケティングを主軸とした支援を行っております。大手人材派遣会社様のオウンドメディアを最適化し、応募単価を88%削減した実績もございます。
Webマーケティングの専門家が、お客様のビジネスに”ゆとり”を提供できるよう 、課題解決をサポートいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。