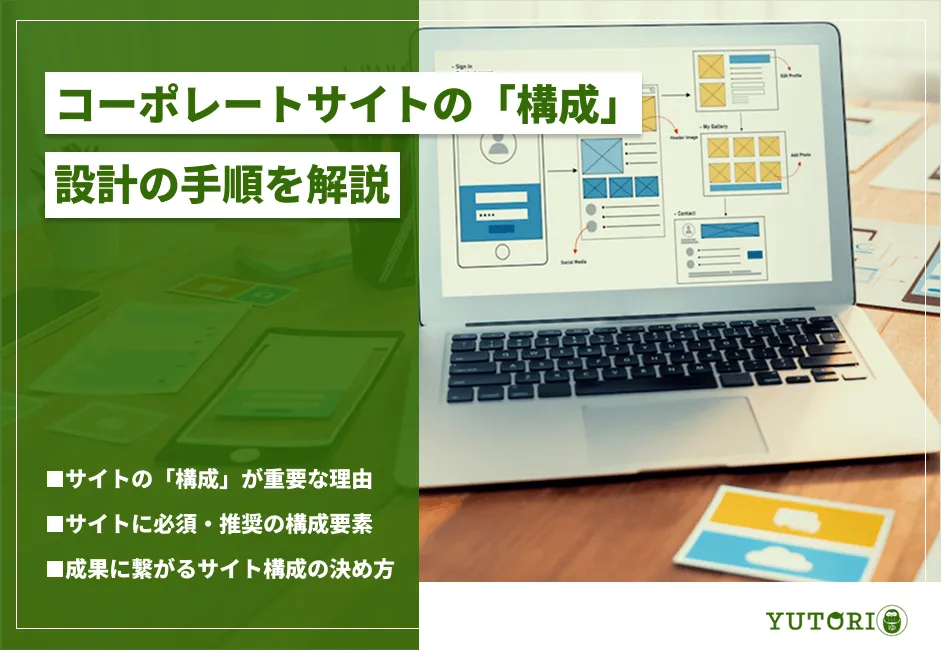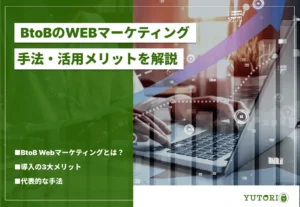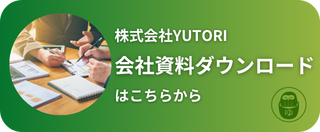コーポレートサイトは、単に企業情報を掲載するだけの「オンライン版パンフレット」ではありません。顧客との出会いの場であり、企業の信頼性を伝え、採用活動やIR活動を支える、まさに「ビジネスのハブ」となる重要なツールです。そして、その効果を最大化する鍵こそが、サイトの骨格となる「構成」にあります。優れた構成は、訪問者をスムーズに目的の情報へ導き、企業のメッセージを的確に伝え、最終的なビジネス成果へと繋げます。
本記事では、コーポレートサイトの構成がなぜ重要なのかという理由から、具体的な必須コンテンツ、成果につながる設計手順、そして失敗しないためのポイントまで、網羅的に解説します。自社のサイト構成を見直したい、あるいはこれから新規構築を考えているWeb担当者の方は、ぜひご一読ください。
目次
コーポレートサイトの「構成」が重要な理由
サイト構成の設計は、家を建てる際の設計図作りによく似ています。見た目のデザインも重要ですが、土台となる設計がしっかりしていなければ、使い勝手が悪く、目的も果たせないものになってしまいます。戦略的に設計された構成は、「検索エンジン」「ユーザー」「企業(自社)」の三方にとって大きなメリットをもたらし、サイトの価値を飛躍的に高めます。
検索エンジンに正しく評価される
サイトの構成が論理的で分かりやすいと、Googleなどの検索エンジンがサイト内の情報を正確に収集・理解しやすくなります。各ページがどのような関連性を持っているのかをクローラーが把握することで、サイト全体が「特定の分野について専門性の高い情報を提供している」と評価され、検索結果で上位に表示されやすくなります。結果として、潜在的な顧客や求職者に見つけてもらえる機会が増加します。
UX(ユーザー体験)の向上
コーポレートサイトを訪れるユーザーは、「製品情報を知りたい」「問い合わせをしたい」「採用に応募したい」など、明確な目的を持っています。どこに何の情報があるか直感的にわかる構成は、ユーザーがストレスなく目的の情報にたどり着く手助けをします。このような快適な利用体験(UX)は、ユーザーの満足度を高め、離脱率を低下させるだけでなく、「お問い合わせ」や「資料請求」といった企業の定めるゴール(コンバージョン)へとスムーズに導きます。
ブランドイメージの構築
整理され、体系的に情報がまとめられたサイトは、訪問者に対して「しっかりとした企業である」という信頼感や安心感を与えます。事業内容や企業理念、実績などが分かりやすく配置されていることで、企業の専門性や独自性が明確に伝わり、ポジティブなブランドイメージの構築に繋がります。乱雑で情報が探しにくいサイトは、それだけで企業の信頼性を損なう可能性があるのです。
運用効率の改善
優れた構成は、サイトを運用するWeb担当者にとってもメリットがあります。コンテンツがどこに格納されているかが明確なため、新しい情報の追加や既存コンテンツの修正・削除といった更新作業が容易になります。作業効率が向上し、属人化を防ぐことができます。将来的にサイト規模を拡大していく際にも、体系的な構成が土台にあることで、スムーズな拡張が可能になります。
コーポレートサイトに必須・推奨の構成要素
コーポレートサイトと一言で言っても、企業の規模や業種、目的によって必要なコンテンツは異なります。ここでは、あらゆる企業に共通して「必須」と言える基本的なコンテンツと、企業の成長戦略に応じて追加を「推奨」するコンテンツに分けてご紹介します。自社に必要な要素は何かを考える際の参考にしてください。
【必須】あらゆる企業に不可欠な基本コンテンツ
まずは、企業の「名刺」代わりとなる、最低限備えておくべき基本的なコンテンツです。これらが欠けていると、企業の信頼性に関わる可能性があります。
トップページ
サイトの「顔」であり、すべての情報の入り口です。企業の最も伝えたいメッセージ(キャッチコピー)、最新のお知らせ、主要なコンテンツへの導線(ナビゲーション)などを集約し、訪問者が一目で「どんな会社か」を理解できるように設計します。
会社概要
企業の公式な基本情報を掲載するページです。社名、所在地、設立年月日、資本金、役員一覧、沿革、アクセスマップなどを記載します。取引先や求職者、金融機関など、多くのステークホルダーが確認する重要なページです。
事業内容・製品/サービス紹介
「この会社が何をしているのか」を具体的に伝える、サイトの中核となるコンテンツです。誰のどのような課題を、自社の製品やサービスでどのように解決できるのかを、分かりやすく紹介します。
お知らせ・ニュース
プレスリリース、新製品情報、イベント出展、メディア掲載情報など、企業の最新動向を発信するページです。定期的な更新は、企業が活発に活動していることを示す証にもなります。
お問い合わせフォーム
顧客や取引先からの連絡を受け付ける窓口です。用件に応じて複数のフォーム(例:「製品に関するお問い合わせ」「協業に関するお問い合わせ」)を用意すると、ユーザーの利便性と社内の対応効率が向上します。
プライバシーポリシー
個人情報の取り扱いに関する方針を示すページです。お問い合わせフォームなどで個人情報を取得する際には、設置が法律で義務付けられています。企業のコンプライアンス遵守姿勢を示し、信頼性を担保します。
【推奨】事業成長を加速させる追加コンテンツ
必須コンテンツに加えて、以下のようなコンテンツを充実させることで、ブランディング強化、リード獲得、人材採用など、企業のさらなる成長を後押しします。
実績・導入事例
自社の製品やサービスを導入した顧客が、どのような課題を抱え、どのように解決し、どんな成果を得たのかを具体的に紹介します。第三者の声は信頼性が高く、導入を検討している見込み客の意思決定を強力に後押しします。
採用情報
企業の成長に不可欠な人材を獲得するためのページです。募集要項はもちろん、事業にかける想い、社風、社員インタビュー、福利厚生などを掲載し、求職者に対して働く魅力を伝えます。
よくある質問(FAQ)
顧客やユーザーから頻繁に寄せられる質問と、その回答をまとめたページです。ユーザーが自己解決できることで顧客満足度が向上し、電話やメールでの問い合わせ対応業務の負担を軽減する効果もあります。
代表メッセージ・企業理念
経営者の考えや企業のビジョン、社会に対する存在意義などを発信するページです。共感を醸成し、企業のファンを増やすことで、他社との差別化を図り、ブランド価値を高めます。
IR情報
株主や投資家に向けて、経営状況や財務情報などを公開するページです。上場企業にとっては必須のコンテンツですが、非上場企業でも設置することで経営の透明性を示し、社会的な信用を高める効果が期待できます。
CSR・ESG情報
企業の社会的責任(CSR)や、環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)への取り組みを発信するページです。企業の持続可能性や社会貢献への姿勢を示すことは、企業価値の向上に繋がります。
成果につながるサイト構成の決め方
効果的なサイト構成は、感覚で決めるものではありません。「誰に、何を伝え、どう動いてほしいか」という戦略に基づき、論理的なステップを踏んで設計することが不可欠です。ここでは、成果に繋がるサイト構成を決定するための4つのステップを解説します。
ステップ1:目的とターゲット(ステークホルダー)を明確にする
最初に、「何のためにサイトを運営するのか(目的)」と「誰に情報を届けたいのか(ターゲット)」を定義します。 目的の例としては、「製品の問い合わせを月20件獲得する」「採用応募者を前年比150%にする」「企業の認知度を向上させる」などが挙げられます。 ターゲットは顧客だけでなく、取引先、株主・投資家、求職者、地域社会など、企業を取り巻くあらゆる関係者(ステークホルダー)が対象です。ターゲットごとに求める情報は異なるため、誰を最優先するのかを明確にすることが重要です。
ステップ2:必要なコンテンツをすべて洗い出す
ステップ1で定めた目的とターゲットに基づき、サイトに掲載すべきコンテンツ(ページや情報)を漏れなくリストアップします。この段階では、構造は意識せず、ブレインストーミング形式で自由にアイデアを出していくのが良いでしょう。競合他社のサイトを参考にしたり、営業部門や採用部門など、各部署の担当者にヒアリングしたりするのも有効です。
ステップ3:コンテンツを論理的にグループ化する
洗い出したコンテンツを、関連性の高いもの同士で分類・整理(グルーピング)していきます。例えば、「会社概要」「沿革」「代表メッセージ」は「企業情報」という大きなカテゴリにまとめることができます。「製品A紹介」「製品B紹介」「導入事例」は「製品・サービス」というカテゴリに分類できます。このグループが、サイトの主要なナビゲーション(グローバルナビゲーション)の項目になります。
ステップ4:サイトマップで階層構造を可視化する
グルーピングしたコンテンツを元に、サイト全体の構造を樹形図(ツリー構造)で視覚化した「サイトマップ」を作成します。トップページを頂点とし、大カテゴリ、中カテゴリ、そして個別のページへと枝分かれしていく形で整理します。サイトマップを作成することで、サイト全体の構造が一目で把握でき、情報の抜け漏れや重複、階層の深さなどを客観的にチェックすることができます。関係者間でのイメージ共有にも役立ちます。
失敗しないための構成設計の重要ポイント
最後に、構成を設計する上で特に注意したい、ユーザーの使いやすさやサイトの評価に直結する3つの重要ポイントをご紹介します。これらの点を軽視すると、せっかくのコンテンツもその価値を十分に発揮できません。
階層は浅く、シンプルに(3クリックルール)
サイトの階層構造は、できるだけ浅くシンプルに保つことが理想です。一般的に、ユーザーが目的の情報にたどり着くまでに3クリック以内で到達できるのが望ましいとされています(3クリックルール)。階層が深すぎると、ユーザーは「どこにいるのか分からない」「目的の情報が見つからない」と感じ、サイトから離脱してしまう可能性が高まります。情報を整理し、ナビゲーションを工夫することで、浅い階層を維持しましょう。
ユーザーの行動動線を意識する
サイトを設計する際は、ユーザーがサイト内でどのようにページを移動するか(行動動線)を意識することが重要です。例えば、製品紹介ページを読んだユーザーが次に関心を持つのは「導入事例」や「価格表」「お問い合わせ」かもしれません。そうしたページの終わりに、次のアクションを促す関連コンテンツへのリンクやボタンを適切に配置することで、ユーザーをスムーズにゴールへと導くことができます。
スマートフォンでの閲覧を前提に設計する
現在、多くのWebサイトはPCよりもスマートフォンで閲覧されています。そのため、サイト構成はPCでの見え方だけではなく、スマートフォンの小さな画面で閲覧されることを前提に設計する必要があります。PCでは分かりやすいナビゲーションも、スマートフォンでは見づらく、使いにくい場合があります。ハンバーガーメニューの活用や、タップしやすいボタンサイズなど、モバイル環境での最適なUXを常に考慮しましょう。
サイト構成の設計を含めたリニューアルのご相談はYUTORIにお任せください
株式会社YUTORIは、本記事で解説した戦略的なサイト構成の設計はもちろん、Webサイト制作からその後のマーケティングまでワンストップでご支援する総合パートナーです。Webクリエイティブ事業とマーケティングプロモーション事業を主軸に、お客様の目的やビジョンに沿ったクリエイティブで企業成長を支えます。
採用支援事業で培った知見を活かしたご提案も可能で、実際にオウンドメディアの最適化により応募単価を88%削減した実績もございます。
これまで100件を超える制作実績を重ねてまいりました。コーポレートサイトの新規構築やリニューアルでお悩みでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。