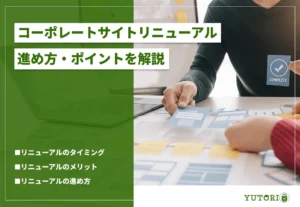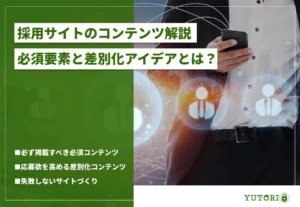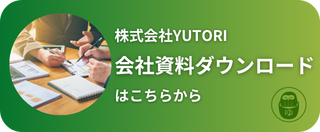Webサイトの制作やリニューアルを任されたものの、「何から手をつければ良いかわからない」「一般的な流れを知りたい」と悩んでいませんか。サイト制作は多くのステップを踏むため、全体像を把握していないと、スケジュール遅延や「思ったものと違う」といった失敗につながりがちです。
この記事では、サイト制作の全体像を「依頼前の準備」から「公開後の運用」まで、具体的な8ステップで解説します。各工程でWeb担当者が押さえるべきポイントも紹介しますので、プロジェクトをスムーズに進めるための手引きとしてご活用ください。
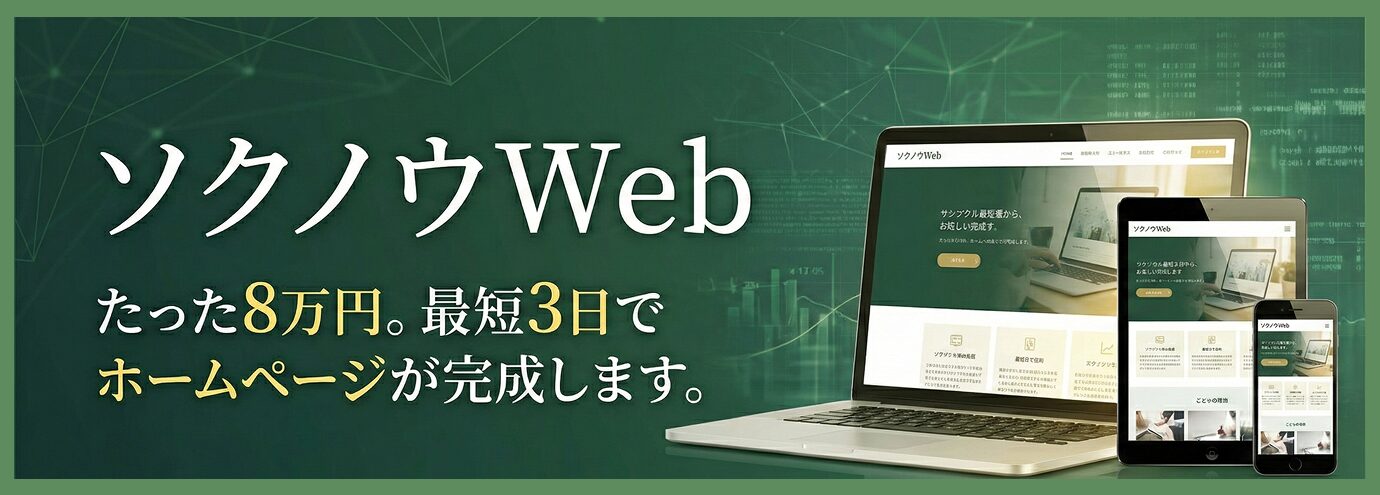
サイト制作における「依頼前の準備」
制作会社に依頼する前に、社内で明確にしておくべき重要な3つのポイントがあります。この「準備」がプロジェクトの土台となり、成果を大きく左右します。曖昧なまま進めると、手戻りが発生したり、成果の出ないサイトになったりするため、時間をかけて議論しましょう。
目的とゴールを明確化する
最も重要なのが「なぜサイトを作るのか」という目的の明確化です。例えば、「企業の認知度を上げたい(ブランディング)」「製品の問い合わせ件数を増やしたい(リード獲得)」「優秀な人材を採用したい(採用強化)」など、企業によって目的は様々です。
さらに、目的を達成できたか測るために、「月間問い合わせ100件」「採用応募数 月20名」といった具体的な数値目標(ゴール=KGI・KPI)も設定しましょう。ここが明確でないと、制作会社も最適な提案ができません。
ターゲットユーザーを具体的に設定する
「誰に」情報を届けたいのかを具体的にします。「30代女性」といった漠然としたターゲットではなく、「東京都内で働く、35歳の女性。最近、キャリアアップのために転職を考えており、情報収集のために平日の夜にスマホで情報を見ることが多い」といった、具体的な人物像(ペルソナ)まで設定するのが理想です。
ペルソナが明確になることで、サイトのデザインテイスト、必要なコンテンツ、使いやすい導線(UI/UX)の方向性が定まります。
予算と希望納期を決定する
サイト制作は、実現したい機能やデザインのクオリティによって費用が大きく変動します。あらかじめ「〇〇円〜〇〇円まで」という予算の幅を決めておきましょう。予算を提示することで、制作会社はその範囲内で実現可能な最善の提案を検討してくれます。
また、「新サービス発表に合わせて〇月〇日までに公開したい」といった希望納期も必須です。納期によってプロジェクトの進め方や人員体制が変わるため、必ず伝えましょう。
サイト制作の工程8ステップと役割
依頼前の準備が整ったら、いよいよ制作会社との実作業に入ります。ここからは、制作会社への依頼からサイト公開までの一般的な流れを8つのステップで解説します。各ステップでWeb担当者が何をすべきかも確認しましょう。
STEP1:制作会社の選定と依頼
まずはプロジェクトを任せるパートナーとなる制作会社を選びます。準備段階で決めた目的や予算、納期をまとめた「RFP(提案依頼書)」を作成し、複数の会社に提案と見積もりを依頼するのが一般的です。
各社の提案内容や実績、費用、担当者との相性などを比較検討し、1社に絞り込みます。契約を締結したら、プロジェクトが正式にスタートします。
STEP2:企画・要件定義
プロジェクトの土台となる最も重要な工程です。制作会社とWeb担当者が集まり、キックオフミーティングを行います。
依頼前に準備した「目的」や「ターゲット」を改めてすり合わせ、サイトに必要な機能(例:ブログ機能、お問い合わせフォーム、資料ダウンロード機能)や仕様(例:CMSはWordPressを使う、常時SSL化する)を詳細に決定します。ここで決めた内容が「要件定義書」としてまとめられます。
STEP3:サイト構造の設計
要件定義に基づき、サイト全体のページ構成と階層構造を設計します。これを「サイトマップ」と呼びます。トップページの下にどのページがあり、それらのページがどう関連しているかを一覧化したものです。
Web担当者は、ユーザーが必要な情報に迷わずたどりける構造になっているか、必要なコンテンツが漏れていないかを制作会社と一緒に確認します。
STEP4:情報設計とワイヤーフレーム作成
サイトマップで決めた各ページについて、具体的な「設計図」を作成します。これを「ワイヤーフレーム(WF)」と呼びます。WFは、デザイン要素(色や装飾)を排除し、情報やパーツの「配置」を決めるものです。
「このページには、まずメインの画像があり、次にキャッチコピー、その下に関連記事へのリンクを置く」といったレイアウトを決定します。Web担当者は、この設計図がターゲットユーザーにとって分かりやすいか、情報を伝える順番として適切かを確認します。
STEP5:デザイン制作
ワイヤーフレームをもとに、デザイナーが具体的なビジュアル(配色、フォント、写真、イラストなど)をデザインしていきます。ここで作成されるのが「デザインカンプ(完成見本)」です。
Web担当者は、デザインカンプが企業のブランドイメージと合っているか、ペルソナに響くデザインかを確認します。「自分の好み」ではなく、「ターゲットの視点」でフィードバックすることが重要です。通常、まずトップページのデザインを確定させ、その後、下層ページのデザインに進みます。
STEP6:開発・実装
確定したデザインカンプを、Web上で閲覧できるようにプログラミング言語(HTML, CSS, JavaScriptなど)に変換していく作業です。これを「コーディング」と呼びます。
同時並行で、CMS(WordPressなど)の導入や、お問い合わせフォームなどのシステム構築(バックエンド開発)も行われます。このステップは制作会社側の作業が中心となります。
STEP7:テストと最終確認
サイトがほぼ完成したら、公開前に最終チェック(テスト・デバッグ)を行います。
「リンクが切れていないか」「誤字脱字はないか」「フォームは正常に動作するか」「PCやスマートフォンなど、異なる環境でもデザインが崩れていないか(レスポンシブ対応)」など、多岐にわたる項目をチェックします。Web担当者も、要件定義通りの機能が実装されているか、実際の操作感を必ず確認しましょう。
STEP8:サイト公開と運用・保守
テストで発見された不具合をすべて修正し、最終確認が完了したら、いよいよサイトを本番環境にアップロードし、公開します。
しかし、サイトは公開がゴールではありません。ここからが本当のスタートです。公開後は、アクセス解析を行いながらコンテンツを更新・改善していく「運用」と、サーバーやシステムの安全性を保つ「保守」が必要になります。
失敗しないサイト制作会社選びのチェックリスト
サイト制作の成否は、パートナーとなる制作会社選びで決まると言っても過言ではありません。数ある会社の中から、自社に最適なパートナーを見つけるための3つのチェックリストを紹介します。
実績は自社の課題と合っているか?
制作会社のWebサイトには必ず「制作実績」が掲載されています。デザインの好みだけで選ぶのではなく、「自社と同じ業界」や「自社と似た課題(例:BtoBのリード獲得、中小企業のブランディング)」を解決した実績が豊富かを確認しましょう。
得意分野は会社によって異なります。自社の課題と実績が合致しているかが重要です。
Webマーケティングの視点を持っているか?
サイトは「作るだけ」では成果は出ません。公開後に「どう集客し、どう成果につなげるか」というWebマーケティングの視点が不可欠です。
SEO(検索エンジン最適化)の知見があるか、公開後の運用やアクセス解析、広告運用までサポートしてくれるかなど、「作るだけで終わらない」体制があるかを確認しましょう。
3. コミュニケーションは円滑か?
サイト制作は数ヶ月にわたる共同作業です。担当者とのコミュニケーションが円滑に進むかは非常に重要です。
レスポンスの速さ、専門用語を多用せず分かりやすい言葉で説明してくれるか、自社のビジネスを理解しようと努めてくれるかなど、見積もりや提案の段階で「信頼できるパートナー」として伴走してくれそうかを見極めましょう。
サイト制作にかかる期間の目安
Web担当者がよく疑問に思うのが「制作期間」です。サイトの規模や機能、制作会社のリソース、自社の確認スピードによって大きく変動しますが、一般的な目安を知っておきましょう。
小規模なサイト(10ページ程度)であれば、準備から公開まで2〜3ヶ月程度。一般的なコーポレートサイト(30〜50ページ程度)であれば、3〜6ヶ月程度が目安です。ECサイトや複雑なシステム開発が伴う場合は、半年以上かかることも珍しくありません。期間を短縮する鍵は、「依頼前の準備」を徹底することと、制作会社からの確認依頼に迅速に対応することです。
サイト制作に関するご相談はYUTORIにお任せください
サイト制作は準備や工程が多く、信頼できるパートナー選びが成功の鍵です。株式会社YUTORIは、企業の魅力を最大限引き出すWebサイト制作 や、集客・売上アップにつながるLP(ランディングページ)制作 を得意としています。
私たちの強みは「作って終わり」にしないこと。成果につながるWebマーケティング戦略の提案 から広告運用 、SNS運用 まで、Webに関わる課題をワンストップで支援します 。 サイトに必要な企業PR動画の制作 や、プロフェッショナルによる写真撮影 も一括でお任せいただけます。
サイト制作やリニューアルでお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。