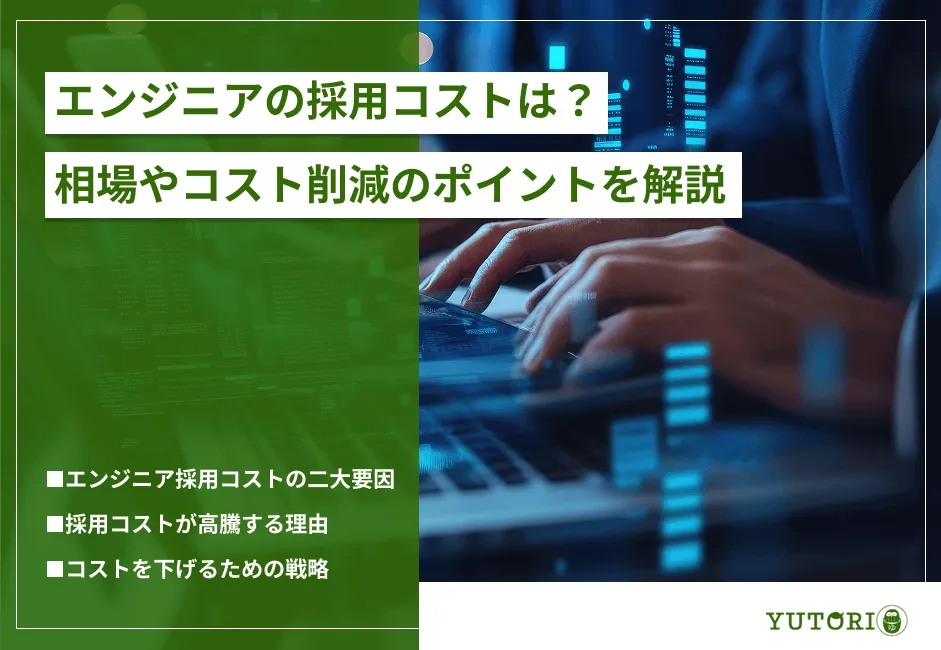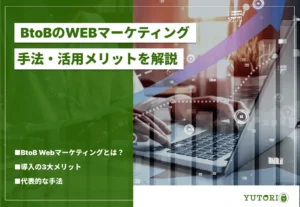DX推進の波が社会全体に広がる中、事業成長の鍵を握るエンジニアの存在価値はかつてないほど高まっています。しかし、多くの企業が「エンジニアの採用が思うように進まない」「採用コストが高騰し続けている」といった課題に直面しているのではないでしょうか。採用活動は、企業の未来を創る重要な投資ですが、そのコスト構造を正しく理解し、戦略的に管理しなければ、経営を圧迫する要因にもなりかねません。
本記事では、エンジニア採用にかかるコストの相場や内訳といった基本から、コストが高騰する根本的な原因、そして実践できる具体的なコスト削減戦略まで網羅的に解説します。
エンジニアの採用コストの二大要因
エンジニアの採用コストについて考えるとき、まず押さえておきたいのが、コストが「外部コスト」と「内部コスト」という二つの要素で構成されている点です。求人サイトの掲載料など、目に見えやすい外部コストだけでなく、社員が採用活動に費やす時間といった内部コストも正確に把握することが、効果的なコスト管理の第一歩となります。
採用コストを構成する「外部コスト」と「内部コスト」の内訳
採用コストを具体的に分解すると、以下のようになります。自社の活動と照らし合わせ、どの項目にどれくらいの費用がかかっているかを確認してみましょう。
外部コスト:社外のサービスや業者に支払う費用
求人広告掲載費
求人サイトやWebメディアに求人情報を掲載するための費用。掲載期間やプランによって料金は変動します。
人材紹介サービス手数料
人材紹介会社(エージェント)経由で採用が決定した場合に支払う成功報酬。一般的に、採用した人材の理論年収の30%~35%が相場とされています。
採用イベント出展費
合同企業説明会や技術者向けのカンファレンスなどに出展するための費用。ブースの装飾費やパンフレット作成費なども含まれます。
ダイレクトリクルーティングサービス利用料
企業が直接候補者にアプローチできるサービスの利用料。月額課金制や成功報酬型など様々な形態があります。
採用管理システム(ATS)利用料
応募者情報の一元管理や選考進捗の可視化を行うツールの利用料です。
その他
リファラル採用の外部ツール利用料、採用パンフレットや動画の制作費などが該当します。
内部コスト:社内の人材やリソースに関わる費用
採用担当者の人件費
採用戦略の立案、母集団形成、面接調整、内定者フォローなど、採用活動全般に関わる担当者の給与や業務時間から算出されるコスト。
面接官の人件費
現場のエンジニアや役員が面接に費やす時間もコストとして捉える必要があります。「時給 × 面接時間 × 面接回数」で算出できます。
リファラル採用のインセンティブ費用
社員紹介によって採用が決定した場合に、紹介した社員へ支払う報奨金。
その他
内定者との懇親会費用、採用活動に伴う交通費や通信費などが含まれます。
正確な費用対効果を測るための「採用単価」計算方法
採用活動の費用対効果を客観的に評価するために不可欠な指標が「採用単価」です。採用単価は、一人の人材を採用するためにかかった総コストを示すもので、以下の計算式で算出します。
採用単価 = (外部コストの合計 + 内部コストの合計) ÷ 採用人数
この採用単価を算出することで、「どの採用チャネルが最も効率的か」「前年度と比較してコストはどう変動したか」などを具体的に分析でき、採用戦略の見直しに役立てることができます。
IT業界の平均採用コストは全体より高い水準
株式会社リクルートの「就職白書2020」によると、2019年度の企業における中途採用の採用単価(一人あたり)の平均は103.3万円でした。しかし、これは全職種の平均値です。
IT業界、特にエンジニア採用においては、この平均値を大幅に上回るケースが少なくありません。需要の高さと専門性から、人材紹介サービスの利用率が高く、結果として一人あたりの採用単価が150万円~300万円、あるいはそれ以上に達することも珍しくないのが実情です。
【職種・企業規模別】エンジニアの採用単価の目安
エンジニアの採用単価は、求める職種や企業の規模によっても大きく変動します。
職種別
Web・アプリケーションエンジニア
比較的母数が多いため、他の専門職種よりは単価が抑えられる傾向にありますが、それでも100万円以上かかることが一般的です。
インフラエンジニア、SRE
企業の基盤を支える重要な役割であり、高い専門性が求められるため、採用単価は高くなる傾向があります。
AIエンジニア、データサイエンティスト
最先端分野であり、対応できる人材が極端に少ないため、採用競争が最も激しい職種の一つです。採用単価は300万円を超えることもあり、場合によっては青天井になる可能性もあります。
企業規模別
大手企業
知名度やブランド力により応募が集まりやすく、一人あたりの採用単価を抑えられる可能性があります。しかし、採用人数が多いため、採用コストの総額は大きくなります。
中小・ベンチャー企業
一人あたりの裁量が大きくやりがいをアピールできる一方、知名度の低さから人材紹介への依存度が高まり、採用単価が高騰しやすい傾向にあります。
なぜ高い?エンジニア採用コストが高騰し続ける3つの根本原因
なぜ、エンジニアの採用コストはこれほどまでに高騰を続けているのでしょうか。その背景には、構造的で根深い3つの原因が存在します。これらの原因を理解することが、効果的な対策を講じるための第一歩となります。
需要と供給のギャップが広がる深刻な「IT人材不足」
最も大きな原因は、IT人材に対する旺盛な需要に対し、供給が全く追いついていないという深刻な需給ギャップです。経済産業省の調査では、IT人材は2030年に最大で約79万人不足すると予測されています。あらゆる業界でDXが急務となる中、エンジニアの獲得競争は激化の一途をたどっており、これが採用単価を直接的に押し上げています。
AI・クラウドなど、求められるスキルの高度化・専門化
テクノロジーの進化に伴い、企業がエンジニアに求めるスキルセットは年々高度化・専門化しています。特に、AI、機械学習、クラウド(AWS, Google Cloud, Azure)、データサイエンス、サイバーセキュリティといった分野では、専門知識を持つ人材が極端に限られています。このような希少性の高いスキルを持つエンジニアを獲得するためには、他社よりも高い報酬や好条件を提示する必要があり、採用コストの高騰に拍車をかけています。
採用チャネルの多様化による採用競争の激化
かつては求人広告や人材紹介が中心だった採用活動も、現在ではダイレクトリクルーティング、SNS、技術ブログ、リファラル採用、採用イベントなど、そのチャネルは多岐にわたります。企業は候補者と接点を持つために、複数のチャネルを並行して運用する必要に迫られています。
各チャネルでの競争が激化するだけでなく、採用活動全体の工数(内部コスト)が増大し、結果として総コストを押し上げる要因となっています。
エンジニア採用コストを下げるための10の戦略
エンジニア採用コストの構造を理解した上で、戦略的にアプローチすることで、費用を抑制し、かつ採用の質を高めることは十分に可能です。ここでは、コスト削減に繋がる10の具体的な戦略をご紹介します。
採用手法の見直し:コストパフォーマンスの高いチャネルへ移行する
まずは、現在利用している採用チャネルごとの「採用単価」を算出しましょう。どのチャネルから何人応募があり、何人採用に至り、総額でいくらかかったのかを可視化します。その上で、費用対効果の低いチャネルへの出稿を停止・縮小し、効果の高いチャネルに予算やリソースを集中させる判断が重要です。
リファラル採用を制度化し、質の高い人材を低コストで獲得する
リファラル採用(社員紹介制度)は、採用コストを大幅に削減できる極めて有効な手法です。広告費や紹介手数料がかからず、インセンティブ費用のみで済むため、外部コストを劇的に圧縮できます。また、社員の紹介であるため、カルチャーフィットしやすく、入社後の定着率が高いというメリットもあります。制度を形骸化させないためには、紹介しやすい仕組みの構築(定期的な周知、シンプルな申請フロー)と、社員にとって魅力的なインセンティブ設計が鍵となります。
ダイレクトリクルーティングで「待ち」から「攻め」の採用へ転換する
求人広告を出して応募を待つ「待ち」の採用から、企業が自ら候補者を探し、直接アプローチする「攻め」のダイレクトリクルーティングへ転換することも有効です。転職潜在層にもアプローチできるため、採用ターゲットが広がるメリットがあります。成功報酬型の人材紹介よりもコストを抑えられるケースが多く、スカウト文面を工夫することで、自社の魅力をダイレクトに伝えられます。
SNSやオウンドメディアを活用し、自社の採用ブランドを構築する
技術ブログやnote、X(旧Twitter)などを通じて、自社のエンジニアが技術情報や開発文化、働く環境について継続的に発信することは、中長期的に見て非常に効果的な戦略です。これらは「採用広報」や「採用ブランディング」と呼ばれ、企業のファンを増やし、「この会社で働きたい」という応募者を自然に惹きつけます。即効性はありませんが、一度ブランドが確立すれば、広告費に依存しない採用活動が可能になります。
採用要件を再定義し、ミスマッチによる無駄なコストをなくす
採用における最大のコストは、採用した人材が早期に離職してしまうことです。これを防ぐには、採用のミスマッチをなくすことが不可欠です。現場が求めるスキル要件を鵜呑みにするのではなく、「絶対に必須のスキル(Must)」と「あれば尚良いスキル(Want)」を明確に切り分けましょう。スキルだけでなく、企業の文化や価値観に共感してくれるか(カルチャーフィット)を重視することで、入社後の定着率が向上し、結果的に無駄な採用コストの発生を防ぎます。
選考プロセスを効率化・オンライン化し、内部コストを削減する
選考プロセスにかかる時間や手間は、すべて内部コストです。ATS(採用管理システム)を導入して応募者情報を一元管理したり、一次面接をWeb面接に切り替えたりすることで、採用担当者や面接官の工数を大幅に削減できます。また、面接官によって評価基準がブレないよう、事前にトレーニングを行い、評価シートを標準化することも、選考の質を高め、効率化に繋がります。
既存社員の定着率を向上させ、採用活動そのものを減らす
最も根本的なコスト削減策は、そもそも採用活動の必要性を減らすこと、つまり「社員の離職率を下げる」ことです。魅力的なキャリアパスの提示、公正な評価制度の構築、働きやすい環境の整備、良好な人間関係の促進など、従業員エンゲージメントを高める施策に投資することは、結果的に新たな採用コストを抑制する最も効果的な一手となります。
採用ターゲットを広げる(未経験者・外国籍人材・アルムナイ)
即戦力となる経験豊富なエンジニアの採用が困難な場合、採用ターゲットを広げる視点も重要です。
未経験者・ポテンシャル採用
育成コストはかかりますが、採用コスト自体は大幅に抑えられます。自社の文化に染まりやすく、長期的な活躍が期待できます。
外国籍人材
国内だけでなく、海外にも視野を広げることで、優秀な人材に出会える可能性が高まります。
アルムナイ採用
一度退職した社員を再雇用する制度です。人柄やスキルを既に把握しているため、ミスマッチのリスクが極めて低く、即戦力としての活躍が期待できます。
正社員に固執せず、フリーランスや派遣も活用する
全ての業務を正社員でまかなう必要はありません。特定のプロジェクトや期間限定の業務であれば、フリーランスのエンジニアや派遣社員といった外部人材の活用も有効な選択肢です。正社員採用に比べて、採用にかかるコストや時間を大幅に短縮でき、必要なスキルを迅速に確保することが可能です。
国や自治体の助成金・補助金を積極的に活用する
企業の採用活動や人材育成を支援するための助成金・補助金制度が、国や自治体によって数多く用意されています。例えば、非正規雇用の労働者を正規雇用に転換した場合に利用できる「キャリアアップ助成金」や、特定の求職者(高齢者、障害者など)を雇用した場合の「特定求職者雇用開発助成金」などがあります。自社が対象となる制度がないか、積極的に情報収集し、活用しましょう。
エンジニア採用の戦略立案・実行はYUTORIにご相談ください
本記事で解説したような「採用コストの高騰」や「社内にノウハウが蓄積されない」といった課題は、多くの企業が直面する悩みです。株式会社YUTORIは、こうした採用に関するあらゆる課題を包括的に解決するため、「採用コンソーシアム」という新しい形の支援サービスを提供しています。
採用コンソーシアムとは、Webマーケティングを主軸に、媒体運用のプロ、HP制作、広告分析の専門家など、各分野のパートナー企業が連携し、貴社の採用チームの一員として多角的にサポートする仕組みです。
部分的な課題解決から全体的な採用戦略の最適化まで、貴社の状況に合わせて柔軟に対応いたします。エンジニア採用にお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください 。