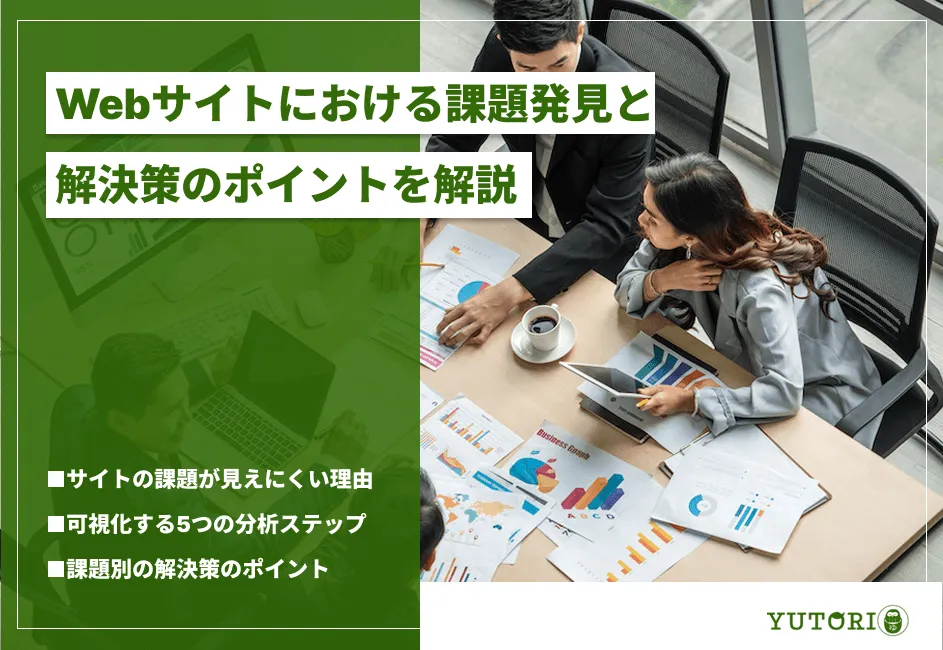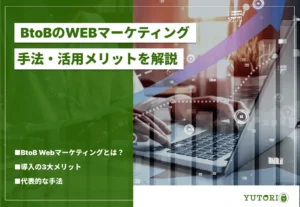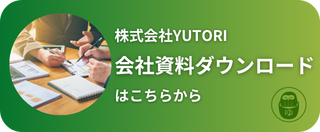自社のWebサイトを運用しているものの、「どこから手をつければ良いかわからない」「リニューアルしたいが、具体的な課題が見えない」といった悩みを抱えていませんか?多くの企業が、Webサイトの潜在的な問題を把握できず、成果につながる改善の機会を逃しています。
この記事では、Webサイトの課題がなぜ見えにくいのか、その原因を解き明かすとともに、データを活用して課題を可視化する具体的な分析ステップを5つに分けて解説します。さらに、よくある課題別の解決策のポイントから、改善を継続させるためのPDCAサイクルの回し方まで、成果を出し続けるWebサイトへの第一歩を踏み出すためのノウハウを網羅的にご紹介します。
目次
なぜ自社サイトの課題は見えないのか?
多くのWeb担当者が自社サイトの課題を的確に把握できないのには、共通した「落とし穴」があります。それは、客観的なデータに基づかず、主観的な判断でサイトを評価してしまうことです。ここでは、課題発見を妨げる3つの典型的なケースを見ていきましょう。
データではなく「勘」や「社内の声」に頼っている
「ここのデザインが古い」「この情報が足りないのでは?」といった意見は、社内の会議でよく聞かれるかもしれません。しかし、それらはあくまで個人の感想や推測であり、サイトを利用する大多数のユーザーが同じように感じているとは限りません。声の大きい人の意見や担当者の「勘」を頼りに改善を進めてしまうと、ユーザーが本当に求めていることとズレが生じ、時間とコストをかけたにもかかわらず、全く成果が出ないという事態に陥りがちです。まずは、データという客観的な事実に基づき、仮説を立てることが重要です。
「とりあえず競合の真似」で本質的な課題を見失う
競合サイトの分析は、自社の立ち位置を把握する上で非常に重要です。しかし、「あのサイトがやっているから」という理由だけで、表層的なデザインや機能を安易に真似してしまうのは危険です。競合と自社では、ターゲット顧客、ブランドイメージ、事業戦略などが異なります。競合の成功事例が、必ずしも自社に当てはまるとは限りません。他社の動向を参考にしつつも、あくまで自社のデータと向き合い、「自社にとっての本質的な課題は何か?」を見極めることが、成果への最短距離となります。
目的が不明確なままデザインリニューアルを進めてしまう
「サイトが古くなったから」「見た目を今風にしたい」といった理由だけでデザインリニューアルを進めるのは、最も陥りやすい失敗の一つです。Webサイトは、企業の目的(売上向上、リード獲得、ブランディングなど)を達成するための「手段」です。目的が不明確なままリニューアルを行うと、単に見た目が変わるだけで、ビジネス上の成果にはつながらない可能性が高くなります。「リニューアルによって何を達成したいのか(KGI/KPI)」を明確に定義し、その目的を達成するための課題は何かを明らかにしてから、具体的な設計に進むべきです。
Webサイトの課題を可視化する5つの分析ステップ
思い込みや主観を排除し、サイトの課題を客観的に洗い出すためには、ツールを活用したデータ分析が不可欠です。ここでは、5つの分析ステップをご紹介します。これらのステップを踏むことで、これまで見えていなかったサイトの健康状態や改善点が具体的に浮かび上がってきます。
Step 1:Googleアナリティクスで見るべき指標
Googleアナリティクスは、サイトの現状を把握するための最も基本的なツールです。まるで健康診断のように、サイト全体の数値から問題の兆候を発見できます。まずは以下の5つの指標に注目してみましょう。
流入数・流入経路
何がわかるか?
どれくらいのユーザーが、どこから(Google検索、SNS、広告など)サイトに訪れているかがわかります。
見るべきポイント
特定の経路からの流入が極端に少ない場合、そのチャネルの集客施策に課題がある可能性があります。例えば、自然検索からの流入が少なければSEO対策の強化が必要です。
ユーザー属性・使用デバイス
何がわかるか?
サイト訪問者の年齢、性別、地域、そして閲覧に使用しているデバイス(PC、スマートフォン、タブレット)がわかります。
見るべきポイント
想定しているターゲット層と実際の訪問者層にズレがないかを確認します。また、スマートフォンからのアクセスが多いにもかかわらず、サイトがスマホ表示に最適化されていない(レスポンシブ対応が不十分)場合、大きな機会損失につながっています。
直帰率・離脱率
何がわかるか?
「直帰」はユーザーがサイトの最初の1ページだけを見て帰ってしまった割合、「離脱」は複数のページを見た後、そのページを最後にサイトを去ったことを示します。
見るべきポイント
特定のページの直帰率や離脱率が異常に高い場合、そのページの内容がユーザーの期待と合っていない、または次に見るべきページへの導線が分かりにくい、といった課題が考えられます。
CVR(コンバージョン率)
何がわかるか?
サイトの目標(商品購入、問い合わせ、資料請求など)を達成したユーザーの割合です。Webサイトの成果を測る最も重要な指標の一つです。
見るべきポイント
アクセス数はあるのにCVRが低い場合、サイトのどこかに目標達成を妨げる障壁があります。例えば、入力フォームが使いにくい、購入ボタンが分かりにくい、といった課題が考えられます。
ページの表示速度
何がわかるか?
各ページがユーザーのブラウザに表示されるまでの時間です。
見るべきポイント
ページの表示速度はユーザー体験に直結します。Googleの調査では、表示に3秒以上かかると53%のモバイルユーザーが離脱すると言われています。表示速度が遅いページは、コンテンツ以前の問題でユーザーを逃している可能性があります。「PageSpeed Insights」などのツールで確認し、改善しましょう。
Step 2:Googleサーチコンソールで流入キーワードの機会と損失を知る
Googleサーチコンソールは、ユーザーがサイトに「訪れる前」の、Google検索上での行動データを分析できるツールです。アナリティクスと連携させることで、課題発見の精度が格段に上がります。
見るべきポイント
「表示回数」は多いのに「クリック率(CTR)」が低いキーワードがないか探しましょう。これは、ユーザーの検索結果に自社サイトは表示されているものの、タイトルや説明文が魅力的でなく、クリックされていない「機会損失」を示しています。タイトルを改善するだけで、流入数を増やせる可能性があります。
また、掲載順位が11位~20位あたり(2ページ目)のキーワードは、コンテンツを少しリライトしたり、内部リンクを最適化したりすることで1ページ目に表示され、流入が大幅に増える可能性があります。
Step 3:競合サイトから学ぶべきポイントと自社の立ち位置
自社サイトのデータだけでは見えない、相対的な強みや弱みを把握するために競合分析を行います。闇雲に真似るのではなく、以下の視点で比較・分析しましょう。
コンテンツ
競合はどのような切り口で情報を発信しているか?自社に不足しているコンテンツは何か?
SEO対策
競合はどのようなキーワードで上位表示されているか?
サイト構造・導線
競合サイトは使いやすいか?ユーザーをスムーズにコンバージョンまで導けているか?
これらの分析を通じて、自社が取るべき戦略や、差別化できるポイントを見つけ出します。
Step 4:ヒートマップでわかる「ユーザーの本当の動き」
ヒートマップツールは、ページ内でのユーザーの行動(マウスの動き、クリック箇所、スクロール到達度など)を色の濃淡で可視化するツールです。Googleアナリティクスの「数値データ」ではわからない、ユーザーの心理や行動の「なぜ?」を理解するのに役立ちます。
熟読エリアの分析
よく読まれている箇所はユーザーの関心が高い部分です。その内容をさらに充実させたり、関連コンテンツへのリンクを設置したりすると効果的です。
クリックエリアの分析
リンクが設定されていない画像やテキストが頻繁にクリックされている場合、ユーザーはそこにリンクがあることを期待しています。リンクを設置することで、サイト内回遊を促進できます。
終了エリアの分析
ユーザーがどこまでスクロールして離脱しているかがわかります。重要な情報やCTA(行動喚起)ボタンが、ユーザーが到達する前に配置されていないか確認しましょう。
Step 5:ユーザーテストで「数値では見えない」課題をあぶり出す
究極の課題発見方法は、実際にユーザーにサイトを使ってもらい、その様子を観察する「ユーザーテスト」です。ターゲットに近いユーザーに特定のタスク(例:「このサイトで〇〇という商品を探して、カートに入れてください」)をお願いし、その過程での思考や感情、つまずいた点などを直接ヒアリングします。
データ分析では「どこで離脱したか」はわかっても、「なぜ離脱したか」は推測するしかありません。ユーザーテストは、その「なぜ」を明らかにし、作り手側では気づけなかった根本的な課題(例:「ボタンの名称が分かりにくい」「専門用語が多くて理解できない」)を発見できる非常に強力な手法です。
課題別の解決策のポイント
分析によって課題が見えてきたら、次はいよいよ解決策の検討です。ここでは、Webサイトが抱えがちな3つの代表的な課題と、それぞれの解決策のポイントを解説します。
サイトの訪問者数が少ない
そもそもサイトに見込み顧客が訪れていなければ、成果は生まれません。訪問者数を増やすためには、サイトへの「入り口」を広げる施策が必要です。
SEO(検索エンジン最適化)
ユーザーが検索するであろうキーワードを調査し、そのキーワードに対する答えとなる質の高いコンテンツを作成します。また、Googleがサイトの内容を正しく理解できるよう、内部構造を整える(内部対策)ことも重要です。
Web広告の活用
リスティング広告やSNS広告などを活用し、ターゲット層に直接アプローチします。即効性が高く、特定の層にピンポイントで情報を届けたい場合に有効です。
SNSの活用
自社のターゲット層が多く利用するSNSで情報を発信し、サイトへの流入を促します。ユーザーとのコミュニケーションを通じてファンを育成することも重要です。
直帰率・離脱率が高い
せっかくサイトに訪れてくれても、すぐに帰られてしまっては意味がありません。ユーザーがサイトに留まり、他のページも見てみようと思えるような工夫が必要です。
コンテンツの見直し
ユーザーが検索したキーワードの意図と、ページの内容が合致しているかを確認します。専門的すぎないか、情報量は十分か、読みやすく構成されているか、といった視点で見直しましょう。
UX(ユーザーエクスペリエンス)の改善
ナビゲーションは分かりやすいか、文字の大きさや行間は適切か、ページの表示速度は遅くないか、スマートフォンで快適に閲覧できるか、といったユーザーの「使いやすさ」「快適さ」を追求します。
内部リンクの最適化
関連性の高いページ同士をリンクでつなぎ、ユーザーが興味の赴くままにサイト内を回遊できるように促します。
課題3:コンバージョン率(CVR)が低い(導線・フォームの課題)
サイトへの集客もできており、ユーザーも回遊しているのに、最終的な成果(問い合わせや購入)につながらないケースです。ゴール直前の導線に問題がある可能性が高いです。
CTA(Call To Action)の改善
「資料請求はこちら」「無料相談を予約する」といった、ユーザーに行動を促すボタンやリンク(CTA)を見直します。ボタンの色や形、配置場所、文言などを変えるだけでも、クリック率は大きく変わります。A/Bテストなどで最適なパターンを見つけましょう。
入力フォームの最適化(EFO)
入力フォームはコンバージョンにおける最大の関門です。入力項目は必要最小限に絞る、入力例を示す、エラー表示を分かりやすくするなど、ユーザーの入力の手間とストレスを極限まで減らす工夫がCVR改善に直結します。
コンバージョンまでの導線の簡略化
ユーザーが目標を達成するまでに、不要なページやクリックを挟んでいないか確認します。できるだけ少ないステップでゴールにたどり着けるよう、導線をシンプルに見直しましょう。
サイトの課題解決を仕組み化するPDCAサイクルの進め方
Webサイトの改善は、一度行ったら終わりではありません。ユーザーのニーズや市場環境は常に変化するため、継続的に改善を繰り返していく「仕組み」を作ることが不可欠です。そのためのフレームワークが「PDCAサイクル」です。
改善施策の優先順位付け
分析を行うと、やるべき改善案が数多く出てくるはずです。しかし、リソースは限られています。そこで重要になるのが「優先順位付け」です。すべての施策を「改善による効果(インパクト)」と「実施にかかる手間(工数)」の2軸で評価し、マトリクス上にプロットします。まずは「インパクトが大きく、工数が少ない」施策から着手するのが最も効率的です。
実行と効果測定
施策を実行(Do)する際は、「この改善を行えば、〇〇という指標が△△%改善されるはずだ」という「仮説」を立てることが重要です。そして施策実施後は、必ず効果測定(Check)を行い、その仮説が正しかったのかをデータで検証します。期待通りの結果が出ればその施策を本格展開し、もし結果が出なければ、その原因を分析して次の改善(Action)につなげます。この繰り返しが、サイトを着実に成長させます。
専門家の活用も視野に
高度な分析や大規模な改修には、専門的な知識やスキル、時間が必要です。もし自社のリソースだけで対応するのが難しい場合は、外部の専門家(Webコンサルタント、制作会社、広告代理店など)の力を借りることも有効な選択肢です。客観的な第三者の視点が入ることで、社内では気づかなかった新たな課題や解決策が見つかることもあります。
サイト改善のご相談やリニューアルのご依頼はYUTORIにお任せください
Webサイトの課題分析や改善施策の実行には、専門的な知識とリソースが必要です。自社での対応が難しいと感じたら、専門家の活用も有効な選択肢です。
株式会社YUTORIは、「あなたのビジネスに”ゆとり”を提供します 」をコンセプトに、採用支援からクリエイティブ制作、マーケティングまで、お客様の企業成長を支える総合パートナーです。企業の魅力を最大限に引き出す「Webサイト制作」や「ランディングページ制作」を行うWebクリエイティブ事業 、Web広告やSNS運用を駆使して成果につながる戦略をご提案するマーケティングプロモーション事業 、そして心に響く映像とビジュアルを制作する映像制作・写真撮影事業 を展開しております。
本記事で解説したようなデータ分析に基づく課題の可視化から、お客様の目的・ビジョンに沿ったクリエイティブ制作 、そして成果を出すための改善サイクルまで、一気通貫でサポート可能です。Webサイトに関するお悩みは、ぜひお気軽に株式会社YUTORIへご相談ください。