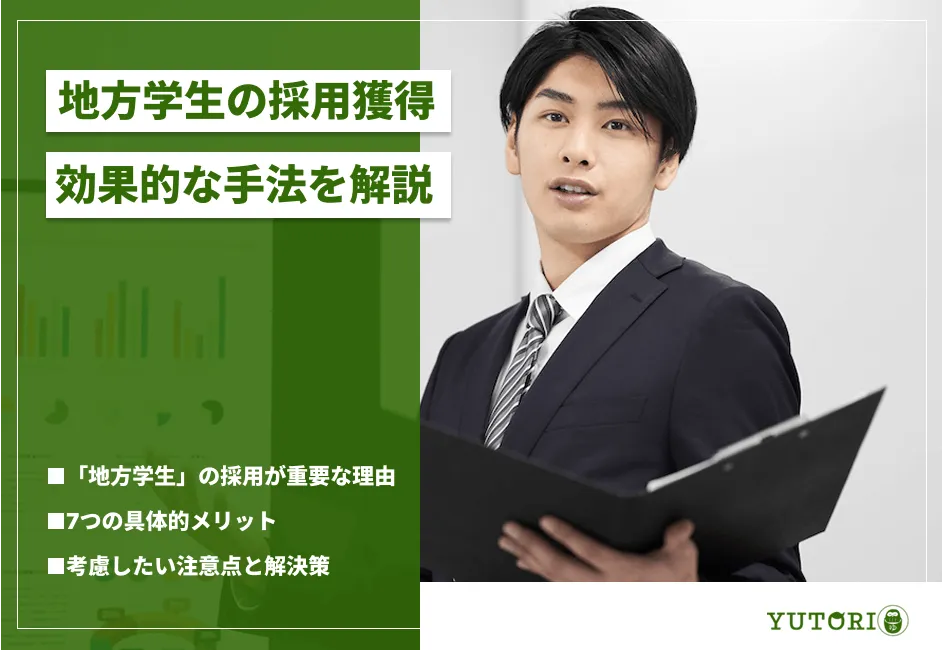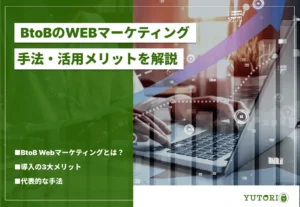都市部での採用競争が激化し、多くの企業が新たな人材獲得の活路を模索しています。その中で、大きな可能性を秘めているのが「地方学生」の採用です。これまで地理的な制約などからアプローチが難しかった地方には、高いポテンシャルを持つ優秀な人材が数多く眠っています。
本記事では、なぜ今、地方学生の採用が企業の成長戦略に不可欠なのか、その具体的なメリットから、彼らの心に響く効果的なアプローチまでを体系的に解説します。
目次
「地方学生」の採用が企業の成長戦略に不可欠な理由
採用市場の構造変化とDXの進展は、企業の採用活動に大きな変革をもたらしました。もはや、地方学生の採用は単なる人材確保の一手段ではありません。変化の激しい時代を勝ち抜くための、企業の持続的成長を支える極めて戦略的な一手へと進化しているのです。ここでは、その理由を3つの視点から解説します。
競争が激化する都市部採用市場からの脱却
都市部における新卒採用市場は、年々競争が激しさを増しています。高い有効求人倍率、採用コストの高騰、そして学生優位の売り手市場。多くの企業が同じパイを奪い合う中で、思うように母集団を形成できなかったり、内定辞退に悩まされたりするケースは少なくありません。
このような状況下で、あえて競争の激しい市場から視点を移し、地方の採用市場に目を向けることは、採用活動における「レッドオーシャン」から抜け出し、新たな可能性が広がる「ブルーオーシャン」へと漕ぎ出すことに他なりません。これまで出会えなかった優秀な人材と出会うための、賢明な戦略的シフトと言えるでしょう。
地方に眠る、優秀でポテンシャルの高い人材との出会い
地方には、都市部の学生に勝るとも劣らない、優秀でポテンシャルの高い人材が数多く存在します。旧帝大をはじめとする地方の国公立大学や、特定の分野で高い専門性を持つ私立大学、そして実践的な技術を身につけた高等専門学校(高専)の学生など、その才能は多岐にわたります。
彼らは、落ち着いた環境で学業に真摯に取り組み、粘り強さや誠実さを兼ね備えている傾向があります。また、情報が限られている分、一つひとつの企業と真剣に向き合い、深く企業研究を行う学生も少なくありません。こうした人材との出会いは、企業の将来を担うコアメンバーの獲得に繋がる大きなチャンスです。
DX時代がもたらした採用活動の地理的制約の解消
かつて、地方学生の採用における最大の障壁は「地理的な距離」でした。しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大を機に、オンライン説明会やWeb面接は一気に普及し、今や採用活動のスタンダードとなりました。
この変化は、企業と学生双方にとって地理的な制約を劇的に解消しました。企業は、これまでアプローチできなかった地域の学生にも、低コストかつ効率的に自社の魅力を伝えることが可能になりました。学生側も、移動時間や交通費を気にすることなく、全国の企業の選考に参加できるようになったのです。このDX時代がもたらした恩恵を最大限に活用しない手はありません。
地方学生の採用がもたらす7つのメリット
地方学生の採用は、単に採用競争を回避できるというだけでなく、組織の活性化や定着率の向上など、企業経営に多岐にわたるプラスの効果をもたらします。ここでは、人事が知っておくべき7つの具体的なメリットを詳しくご紹介します。
競争率の低い市場で優秀な学生を確保
前述の通り、地方の採用市場は都市部に比べて競合となる企業が少ない「ブルーオーシャン」です。これは、学生に対して自社の魅力をじっくりと伝え、他社との差別化を図りやすいことを意味します。都市部では多くの企業の中に埋もれてしまうような中小・ベンチャー企業であっても、地方では学生にとって魅力的な選択肢となり得ます。結果として、競争に勝ち抜く形で優秀な学生を確保できる可能性が高まります。
地方拠点への配属ミスマッチと早期離職の防止
全国に拠点を持つ企業にとって、地方拠点への配属は大きな課題の一つです。都市部で採用した社員を地方に配属した結果、生活環境の変化に馴染めず、早期離職に繋がってしまうケースは後を絶ちません。
その点、地元での就職やUターン・Iターンを希望する地方学生を採用できれば、こうしたミスマッチを根本から防ぐことができます。地域への愛着や理解があるため、スムーズに職場に定着し、長期的に活躍してくれることが期待できます。これは、企業の人的資本を安定させる上で非常に大きなメリットです。
多様な価値観が組織を活性化させる
企業の持続的な成長には、イノベーションの創出が不可欠です。そして、イノベーションの源泉となるのが、多様な人材がもたらす多様な価値観です。採用する人材の出身地が都市部に偏ってしまうと、組織の価値観や発想も均質化しがちです。
地方で生まれ育った学生は、都市部の学生とは異なる生活環境や文化の中で独自の価値観を育んでいます。こうした多様なバックグラウンドを持つ人材が組織に加わることで、新たな視点やアイデアが生まれ、組織全体の活性化、ひいては企業競争力の強化に繋がります。
採用ブランディングの強化と企業イメージの向上
地方の大学との連携を深めたり、地域に根差した採用イベントに参加したりすることは、その地域における企業の認知度向上に直結します。地域社会との繋がりを大切にし、雇用の創出に貢献する姿勢は、「地域貢献企業」としてのポジティブなブランドイメージを構築します。このような活動は、学生だけでなく、その保護者や大学関係者、さらには地域住民からの信頼獲得にも繋がり、長期的な視点での採用ブランディング強化に大きく貢献します。
一社一社と真摯に向き合う学生による高いエンゲージメント
地方学生は、都市部の学生に比べてアクセスできる企業情報が限られている場合があります。そのため、自ら積極的に情報を探し、一社一社の企業説明会に真剣に耳を傾け、深く企業研究を行う傾向が見られます。
こうしたプロセスを経て入社を決意した学生は、企業に対する理解度や納得度が高く、入社後のエンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)も高いレベルを維持しやすいと言われています。結果として、主体的に仕事に取り組み、早期に戦力化してくれる可能性が高まります。
リファラル採用への波及効果
地方学生を採用し、彼らが自社で生き生きと働く姿は、何よりの広告塔となります。満足度の高い社員は、自然と自社を母校の後輩や地元の友人に勧めてくれるようになります。
特に地方では、大学や地域コミュニティの繋がりが強い傾向にあるため、一人の採用が、リファラル採用(社員紹介採用)という形で、次の優秀な人材の獲得へと繋がる波及効果が期待できます。採用コストを抑えつつ、質の高いマッチングを実現する有効なサイクルです。
運転免許所持率の高さなど、実務的な利点
地方では、日常生活において自動車が必須であることが多く、学生の運転免許所持率は都市部に比べて格段に高い傾向にあります。このことは、営業職や技術職など、業務で自動車の運転が必要となる職種においては、非常に実務的なメリットとなります。入社後の免許取得を待つ必要がなく、即戦力としてスムーズに業務を開始できる点は、企業にとって見逃せない利点です。
地方学生採用における考慮したい注意点と解決策
メリットの多い地方学生採用ですが、一方で、成功させるためには乗り越えるべき特有の課題も存在します。ここでは、代表的な2つの注意点と、それを克服するための具体的な解決策を合わせて解説します。
採用コストの増加
地方学生に対面での面接や説明会を実施する場合、学生が本社まで来るための交通費や宿泊費を企業が負担するのが一般的です。対象となる学生が増えれば増えるほど、このコストは看過できない金額になります。
【解決策】
この課題の最も有効な解決策は、オンライン選考の最大限の活用です。説明会から一次・二次面接までをオンラインで完結させ、最終面接など、どうしても対面が必要なフェーズのみに絞って交通費を支給するハイブリッド型が主流です。また、後述する「1日完結選考」のように、学生の来訪を1回で済ませる工夫もコストと負担の軽減に繋がります。
根強い「地元志向」の壁
地方学生の中には、親の意向や地元への愛着から、「生まれ育った地域を離れたくない」という根強い地元志向を持つ層が一定数存在します。こうした学生に対して、本社が都市部にある企業がアプローチするのは、時に困難を伴います。
【解決策】
まず、自社がその地域でどのように貢献しているか、あるいは将来的に貢献できるかを具体的に示すことが重要です。地方に支社や工場がある場合は、そこでの働きがいやキャリアパスを積極的にアピールしましょう。また、Uターン・Iターンで活躍する先輩社員の事例を紹介することも極めて効果的です。彼らのリアルな声を通して、都市部での経験を地元で活かすキャリアの魅力を伝えることで、学生の心理的な壁を取り除くことができます。
地方学生に響く効果的な採用アプローチ6選
課題を乗り越え、地方に眠る優秀な学生に自社の魅力を効果的に届けるためには、戦略的なアプローチが不可欠です。ここでは、明日からでも始められる6つの具体的な手法をご紹介します。これらを組み合わせることで、採用成功の確率は格段に高まります。
ダイレクトリクルーティングとSNSによる個別接点創出
従来の「待ち」の採用スタイルでは、地方の優秀な学生と出会うことは困難です。企業側から積極的にアプローチする「攻め」の姿勢が求められます。
ダイレクトリクルーティングサービス(スカウト型採用サービス)を活用し、企業の求めるスキルや経験を持つ地方学生に直接スカウトメッセージを送ることで、認知度を一気に高めることができます。また、X(旧Twitter)やInstagramなどのSNSで、企業の日常や社員の働く様子をカジュアルに発信することも、学生との心理的な距離を縮める上で有効です。個別メッセージでのフランクなコミュニケーションから、選考へと繋がるケースも増えています。
地方特化型サービスと大学との連携強化
地方学生の採用を成功させるには、彼らが日常的に利用するプラットフォームやコミュニティにアプローチすることが重要です。
地方学生に特化した就職サイトや合同説明会は、ターゲット層に効率的にリーチできる絶好の機会です。また、それ以上に重要なのが、各大学のキャリアセンターとの関係構築です。定期的に訪問して情報交換を行ったり、学内説明会やOB・OG訪問に協力したりすることで、信頼関係を築き、自社にマッチする学生を優先的に紹介してもらえる可能性が高まります。
オンライン説明会・Web面接の戦略的導入
単に説明会や面接をオンライン化するだけでは不十分です。地方学生が参加しやすいように「戦略的」に導入することが成功のカギとなります。
例えば、地方の大学の授業スケジュールを考慮した開催時間の設定、ブレイクアウトルーム機能を活用した少人数での座談会、チャット機能を活用したリアルタイムでの質疑応答など、双方向のコミュニケーションを促す工夫が求められます。また、学生の通信環境に配慮し、資料を事前に送付したり、音声トラブル時の対応策をあらかじめ伝えたりする細やかな配慮も、企業イメージの向上に繋がります。
地方学生の視点に立った採用サイト・コンテンツ制作
採用サイトやパンフレットのコンテンツは、本当に地方学生の知りたい情報に応えられているでしょうか。都市部の学生向けと同じ内容では、彼らの心には響きません。
地方出身の先輩社員のインタビューは必須コンテンツです。彼らがなぜその会社を選んだのか、Uターン・Iターン就職のリアルな体験談は、学生にとって何よりの道しるべとなります。また、社宅や家賃補助といった福利厚生制度や、もし地方拠点があればその拠点の働きがいや周辺環境の魅力など、彼らが新生活を具体的にイメージできるような情報発信を心がけましょう。
参加しやすいオンライン/ハイブリッド型インターンシップの設計
インターンシップは、学生が企業文化や仕事内容を深く理解する上で非常に重要ですが、地方学生にとって長期・対面のインターンシップへの参加は物理的なハードルが高いのが現実です。
そこで有効なのが、1Day〜数日間の短期オンラインインターンシップです。オンラインであれば、場所を問わず気軽に参加できます。また、グループワークはオンラインで行い、最終日の成果発表会だけ対面で実施するハイブリッド型も、学生の負担を軽減しつつ、リアルな交流の機会を提供できるため効果的です。プログラム内容を工夫し、オンラインでも企業の魅力を最大限に伝えられる設計が求められます。
「1日完結選考」など効率的な選考プロセスの導入
選考プロセスが複数回にわたり、その都度本社へ足を運ぶ必要があるとすれば、地方学生は選考を辞退してしまう可能性が高まります。
学生の時間的・金銭的負担を劇的に軽減するのが、会社説明会からグループディスカッション、複数回の面接までを1日で行う「1日完結選考会」です。企業側にとってはオペレーションの負担が大きいものの、学生に対する「おもてなし」の姿勢が伝わり、志望度を大きく向上させる効果が期待できます。オンライン選考と組み合わせ、最終選考のみをこの形式で実施するのも良いでしょう。
採用戦略にまつわるお悩みはYUTORIにご相談ください
本記事では、地方学生の採用が企業の成長戦略においていかに重要であるか、そして、その採用を成功させるための具体的なメリットやアプローチについて解説しました。
しかし、実際に採用活動を進める中で、以下のようなお悩みを抱えている企業様も多いのではないでしょうか。
- 採用コストが年々増加し、効率的な方法を模索している
- 求人広告の効果が低下し、採用単価が高騰している
- 採用ノウハウが社内に蓄積されず、同じ課題が繰り返されている
- 外部委託に依存し、予算超過や依存リスクを懸念している
- 短期成果に偏り、中長期的な採用戦略が不足している
株式会社YUTORIの「採用コンソーシアム」は、こうした採用課題を包括的に解決するサービスです。各分野の専門家が連携し、貴社の採用チームの一員として伴走。ペイドメディアの最適化、オウンドメディア構築、アーンドメディアの活用など、現状の課題に応じた柔軟な施策を実施し、短期的な成果だけでなく、持続可能な自社採用力の強化を実現します。
実際に、応募単価40%削減、応募数1.5倍増加、応募者のスクリーニング通過率40%向上など、多くの成功事例が生まれています。地方学生採用を含む採用活動全体の最適化に向けて、ぜひお気軽にご相談ください。