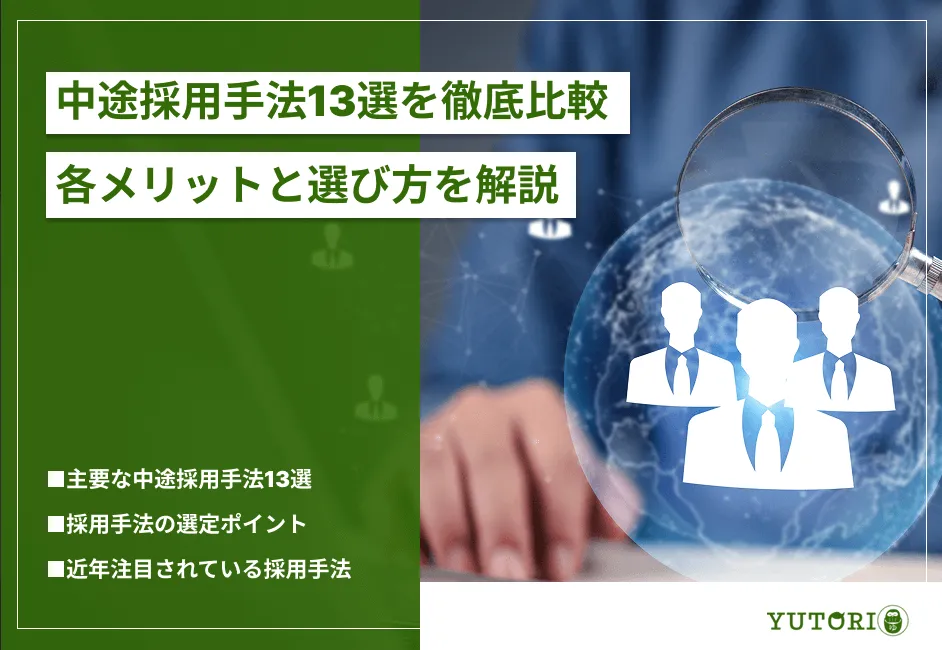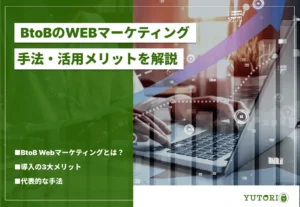企業の成長に不可欠な中途採用。しかし、「求人を出しても応募が来ない」「自社にマッチした人材が見つからない」といった悩みを抱える人事担当者の方も多いのではないでしょうか。採用市場が変化し続ける現代において、従来の手法だけでは優秀な人材の獲得は困難になっています。
本記事では、主要な中途採用手法13選を徹底的に比較し、それぞれのメリット・デメリット、そして自社に最適な手法を選ぶためのポイントを詳しく解説します。最新の採用トレンドも押さえ、競争の激しい中途採用市場を勝ち抜くための戦略的なヒントを提供します。
主要な中途採用手法13選
中途採用の手法は多岐にわたり、それぞれに特徴や強みがあります。ここでは、主要な13種類の手法について、その概要とメリット・デメリットを解説します。自社の採用課題や求める人物像に合わせて、最適な手法を見つけるための参考にしてください。
1. 求人広告・求人サイト
求人広告・求人サイトは、最も一般的な中途採用手法の一つです。リクナビNEXTやdodaといった総合型のサイトから、特定の職種や業界に特化したサイトまで様々な種類があります。
メリット
- 幅広い層の求職者にアプローチできる。
- Webサイトであれば、掲載開始までのスピードが速い。
- 基本的に応募を待つ「待ち」のスタイルのため、採用工数が比較的少ない。
デメリット
- 多くの求人情報に埋もれてしまい、応募が集まらない可能性がある。
- 採用が成功しなくても、掲載費用が発生する(掲載課金型の場合)。
- 応募者の質がばらつきやすく、選考工数が増えることがある。
2. 人材紹介
人材紹介は、紹介会社(エージェント)が企業の採用要件に合った候補者を探し出し、紹介するサービスです。採用が成功した場合に費用が発生する「成功報酬型」が一般的です。
メリット
- 採用要件にマッチした人材を効率的に探せる。
- 非公開求人として募集できるため、競合他社に採用動向を知られずに済む。
- エージェントが候補者との日程調整や条件交渉を代行してくれるため、採用工数を削減できる。
デメリット
- 採用決定時の成功報酬が高額になる傾向がある(理論年収の30〜35%が相場)。
- 紹介会社の介在により、候補者との直接的なコミュニケーションが取りにくい場合がある。
- 必ずしも自社が求める人材が登録しているとは限らない。
3. ダイレクトリクルーティング
ダイレクトリクルーティングは、企業が「攻め」の姿勢で、求める人材に直接アプローチする採用手法です。BizReach(ビズリーチ)やLinkedInなどのデータベースを利用して、候補者を探し出し、スカウトメールを送ります。
メリット
- 潜在層(転職を積極的に考えていない層)にもアプローチできる。
- 自社の魅力やビジョンを直接伝えることで、入社後のミスマッチを防ぎやすい。
- 長期的に見ると、一人当たりの採用コストを抑えられる可能性がある。
デメリット
- 候補者探しからスカウトメールの作成・送信、面談まで、採用担当者の工数がかかる。
- すぐに採用に繋がるとは限らず、中長期的な視点が必要。
- 企業の知名度やブランド力がないと、スカウトメールの開封率や返信率が低くなる傾向がある。
4. リファラル採用
リファラル採用は、自社の社員に知人や友人を紹介してもらう採用手法です。社員のネットワークを活用することで、信頼性の高い人材を獲得しやすいのが特徴です。
メリット
- 社員の紹介であるため、カルチャーフィットしやすく、定着率が高い傾向がある。
- 求人広告費や紹介手数料がかからず、採用コストを大幅に抑えられる。
- 潜在層へのアプローチが可能になる。
デメリット
- 社員の人間関係に依存するため、候補者の数や質が不安定になりやすい。
- 不採用になった場合、紹介者と被紹介者の関係に影響が出る可能性がある。
- 紹介制度の設計や、社員への協力依頼・インセンティブ設計など、制度運用のための工数がかかる。
5. SNS採用(ソーシャルリクルーティング)
Facebook、X (旧Twitter)、LinkedInなどのSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を活用して採用活動を行う手法です。企業の文化や働く人の様子を発信し、候補者とのコミュニケーションを図ります。
メリット
- 企業のリアルな情報を発信しやすく、共感を軸とした採用ブランディングが可能。
- 「いいね」や「シェア」による情報の拡散が期待でき、潜在層にもリーチできる。
- 無料で始められるアカウントも多く、低コストでの運用が可能。
デメリット
- 炎上リスクがあり、企業イメージを損なう可能性があるため、慎重な運用が求められる。
- 継続的な情報発信が必要で、コンテンツ企画や運用の工数がかかる。
- すぐに採用成果に結びつくとは限らず、中長期的な運用が必要。
6. オウンドメディア採用
自社で運営するブログやウェブサイト(オウンドメディア)を通じて、企業のビジョン、事業内容、社員インタビューなどのコンテンツを発信し、採用に繋げる手法です。
メリット
- コンテンツを通じて、企業の文化や価値観を深く伝えることができ、ミスマッチの少ない採用が期待できる。
- コンテンツが資産として蓄積され、中長期的な採用ブランディングに繋がる。
- 潜在層に対して、自社のファンになってもらうきっかけを作れる。
デメリット
- 質の高いコンテンツを継続的に作成・発信するための企画力やリソースが必要。
- 効果が出るまでに時間がかかり、短期的な採用には向かない。
- SEO対策など、集客のための専門的な知識が必要になる場合がある。
7. 転職イベント(合同企業説明会)
複数の企業が一堂に会し、求職者に対して自社の説明を行うイベントです。大規模なものから、特定の業界や職種に特化した小規模なものまで様々です。
メリット
- 転職意欲の高い求職者と一度に多数接触できる。
- その場で直接対話することで、自社の魅力を伝えやすく、候補者の反応もダイレクトにわかる。
- 他社の採用動向や人気度などを肌で感じることができる。
デメリット
- 出展費用が高額になる場合がある。
- 多くの企業が出展するため、自社のブースに集客するための工夫が必要。
- 接触できる時間は限られており、一人ひとりと深くコミュニケーションを取ることは難しい。
8. ハローワーク
国が運営する公共職業安定所(ハローワーク)を通じて、求人を行う手法です。地域に密着した採用活動に適しています。
メリット
- 無料で求人票を掲載できるため、採用コストがかからない。
- 全国各地に拠点があり、地域に根差した人材の採用に強い。
- 助成金の対象となる場合がある。
デメリット
- 利用者の年齢層が高めである傾向や、求職者のスキルレベルにばらつきがある場合がある。
- 求人票のフォーマットが決まっており、自社の魅力を伝えにくい。
- 基本的に応募を待つスタイルであり、専門職やハイスキル人材の採用には向かないことが多い。
9. ヘッドハンティング
企業の経営層や幹部、特殊なスキルを持つ専門家など、特定の優秀な人材を外部のヘッドハンターがスカウトする手法です。
メリット
- 市場に出てこないような優秀な人材や、競合他社のキーパーソンにアプローチできる。
- 採用要件が極めて高いポジションの採用に適している。
- 秘密裏に採用活動を進めることができる。
デメリット
- 着手金や成功報酬が非常に高額になる。
- ヘッドハンターのスキルやネットワークに依存するため、必ずしも成功するとは限らない。
- 候補者との交渉が難航する場合がある。
10. アルムナイ採用
企業の退職者(アルムナイ)を再雇用する採用手法です。「出戻り採用」とも呼ばれます。
メリット
- 一度自社で働いた経験があるため、即戦力として期待でき、カルチャーフィットのミスマッチが起こりにくい。
- 他社での経験を積んでいるため、新たな視点やスキルを組織にもたらす可能性がある。
- 採用にかかるコストや手間を大幅に削減できる。
デメリット
- 退職時の状況や理由によっては、再雇用が難しい場合がある。
- 既存社員との人間関係や処遇のバランスに配慮が必要。
- 対象となる退職者がいなければ実施できない。
11. 人材派遣
人材派遣会社に登録しているスタッフを、一定期間「派遣社員」として受け入れる雇用形態です。厳密には直接雇用の中途採用とは異なりますが、紹介予定派遣などを通じて直接雇用に切り替えることも可能です。
メリット
- 必要なスキルを持つ人材を、必要な期間だけ確保できる。
- 募集から採用までのプロセスを派遣会社に任せられるため、手間がかからない。
- 紹介予定派遣を利用すれば、一定期間働きぶりを見た上で直接雇用するかを判断できる。
デメリット
- 契約期間が定められており、長期的な戦力にはなりにくい(直接雇用を除く)。
- 任せられる業務範囲に制限がある。
- 帰属意識が低くなりがちで、重要な業務を任せにくい場合がある。
12. ミートアップ
特定のテーマに興味を持つ人々が集まり、交流する小規模なイベントを自社で開催し、採用に繋げる手法です。カジュアルな雰囲気で、企業と候補者が相互理解を深める場となります。
メリット
- リラックスした雰囲気で、候補者の素顔や価値観に触れることができる。
- 企業の文化や働く環境を直接見てもらうことで、採用ブランディングに繋がる。
- 潜在層との接点を作り、将来的な採用候補者との関係を構築できる。
デメリット
- イベントの企画・集客・運営に工数がかかる。
- 直接的な採用に結びつくとは限らず、費用対効果が見えにくい場合がある。
- 集客がうまくいかないリスクがある。
13. クリック課金サービス
Indeedに代表される、求人情報がクリックされるごとに費用が発生するタイプの求人検索エンジンです。掲載自体は無料で、求職者の目に触れた分だけ費用がかかる仕組みです。
メリット
- 低リスクで求人掲載を始められる。
- クリック単価や予算を自社でコントロールできるため、費用対効果を調整しやすい。
- 運用次第では、求人サイトよりも採用単価を抑えられる可能性がある。
デメリット
- 効果を出すためには、求人票の最適化やクリック単価の調整など、専門的な運用ノウハウが必要。
- 人気のある職種やエリアでは、クリック単価が高騰しやすい。
- 応募に繋がらなくても、クリックされれば費用が発生する。
自社に合った採用手法の選定ポイント
数ある採用手法の中から、自社にとって最適なものを選ぶには、どのような点に注意すればよいのでしょうか。ここでは、採用戦略を立てる上で欠かせない3つの選定ポイントを解説します。
採用目標(ペルソナ・人数・いつまでに)を明確にする
まず最も重要なのは、「どのような人材を(ペルソナ)」「何人(人数)」「いつまでに(期限)」採用したいのかを具体的に定義することです。例えば、「営業経験豊富で即戦力となる人材を2名、3ヶ月以内に採用したい」のであれば、転職意欲の高い層が集まる人材紹介や求人広告が有効でしょう。
一方で、「3年後の事業拡大を見据え、特定の専門スキルを持つ若手エンジニアを長期的に探したい」のであれば、ダイレクトリクルーティングやSNS採用、オウンドメディア採用といった中長期的なアプローチが適しています。このように採用目標を明確にすることで、取るべき手法が自ずと絞られてきます。
採用にかけられるコスト(費用・工数)を算出する
採用活動には、求人広告費や成功報酬といった「費用」だけでなく、採用担当者の人件費や時間といった「工数」もかかります。それぞれの採用手法について、トータルでどのくらいのコストがかかるのかを事前に把握することが重要です。
例えば、ダイレクトリクルーティングは成功報酬がかからない分、費用を抑えられる可能性がありますが、候補者の選定やスカウトメールの作成に多くの工数がかかります。反対に、人材紹介は費用が高額になりがちですが、工数を大幅に削減できます。自社の採用チームのリソースや予算と照らし合わせ、費用対効果が最も高い手法を選択しましょう。
自社の知名度や採用ブランド力を考慮する
自社の知名度や、求職者から見た「働きたい企業」としての魅力(採用ブランド力)も、手法選定における重要な要素です。
知名度が高く、採用ブランドが確立されている企業であれば、求人広告やオウンドメディアだけでも多くの応募者を集めることが可能です。しかし、知名度が低い中小企業やBtoB企業の場合、応募を待つだけの手法では苦戦する可能性が高いでしょう。その場合は、ダイレクトリクルーティングやリファラル採用、人材紹介といった、企業側から積極的にアプローチする手法や、信頼性を担保できる手法を組み合わせることが効果的です。自社の現状を客観的に分析し、身の丈に合った戦略を立てることが成功の鍵となります。
【採用トレンド】近年注目されている採用手法とは?
採用市場の競争激化や働き方の多様化に伴い、従来の手法だけでは優秀な人材の獲得が難しくなってきています。ここでは、近年の採用トレンドとして特に注目されている2つの手法を紹介します。
トレンド①:ダイレクトリクルーティング
前述の通り、ダイレクトリクルーティングは企業から候補者へ直接アプローチする「攻め」の採用手法です。転職潜在層にもアプローチできる点や、企業と候補者のミスマッチを減らせる点が高く評価され、導入する企業が急増しています。データベースの充実に伴い、多様な職種・キャリアの候補者を探し出せるようになっており、採用競争を勝ち抜くための重要な一手として定着しつつあります。
トレンド②:リファラル採用
社員の紹介によるリファラル採用も、近年その重要性が再認識されています。採用コストを大幅に削減できるだけでなく、社員の紹介という信頼性の高いルートを経ることで、入社後の定着率が高いという大きなメリットがあります。働きがいのある組織作りと連動させることで、社員が自発的に会社を推薦したくなるような好循環を生み出すことができ、持続可能な採用力の構築に繋がる手法として注目されています。
採用手法の立案・実行はYUTORIにお任せください
本記事では、13の中途採用手法と、その選び方について解説しました。しかし、多様な手法の中から自社に最適な戦略を立案し、実行していくことには多くのリソースと専門的なノウハウが求められます。
株式会社YUTORIでは、そうした企業様の採用課題を包括的に解決するため、「採用コンソーシアム」という形でご支援しています。採用コンソーシアムは、Webマーケティングを主軸とし、媒体選定、HP制作、広告分析、LINE運用といった各分野の専門家がチームとなって貴社の採用活動を多角的にサポートする仕組みです。
変化の激しい時代を勝ち抜くための採用戦略の立案・実行に課題を感じていらっしゃいましたら、ぜひお気軽にご相談ください。