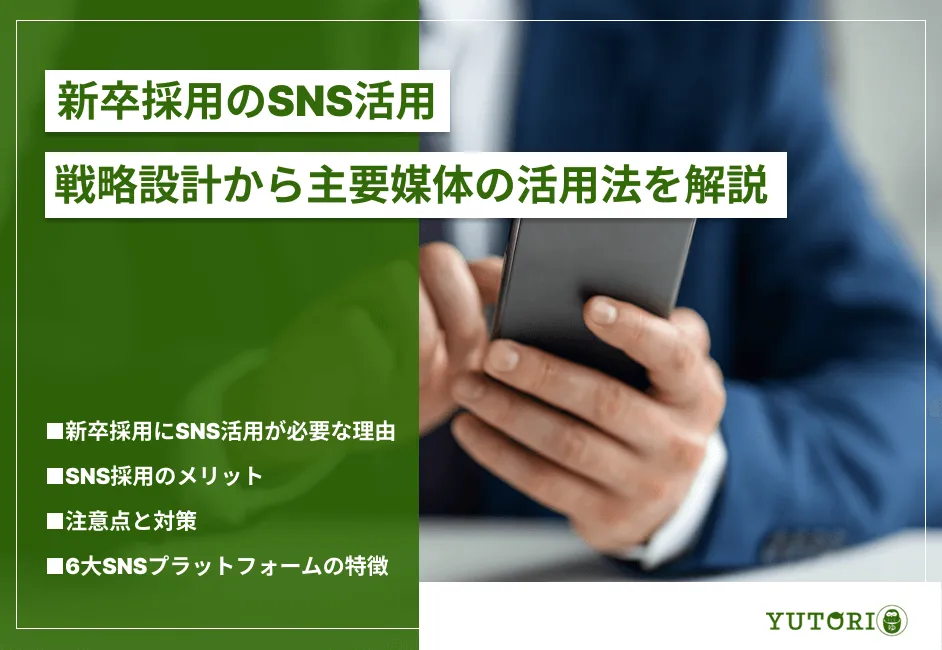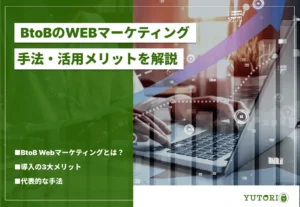新卒採用市場における競争が激化する中、従来のナビサイト中心の採用活動だけでは、自社が求める優秀な人材に出会うことが難しくなってきています。現代の就活生にとって、情報収集の主戦場はSNSへと移行しており、企業は彼らのフィールドで魅力を伝えていく必要があります。
しかし、「何から始めればいいかわからない」「運用リソースがない」「炎上が怖い」といった理由で、SNS活用に踏み出せないでいる採用担当者様も多いのではないでしょうか。 本記事では、新卒採用でSNS活用が不可欠な理由から、具体的な戦略設計、主要6媒体の活用法、そして失敗しないための注意点まで、網羅的に解説します。
目次
新卒採用にSNS活用が不可欠な理由
なぜ今、これほどまでに新卒採用におけるSNSの重要性が注目されているのでしょうか。その背景には、就職活動を行う学生の情報収集スタイルの変化と、彼ら「Z世代」が持つ特有の価値観が深く関わっています。ここでは、SNS活用が「選択肢」ではなく「必須」となりつつある3つの理由を解説します。
就活生の6割がSNSを利用
かつて就活の情報収集といえば、就職情報サイトや合同説明会が主流でした。しかし、スマートフォンが当たり前の世代にとって、SNSは最も身近で信頼できる情報源です。ある調査では、就活生の6割以上がSNSを企業の情報収集に利用しているというデータもあります。彼らは、企業の公式発表だけでなく、ハッシュタグ検索を通じて社員や他の就活生の「リアルな声」を探しています。この主戦場の変化に対応できない企業は、学生の選択肢にすら上がらない時代になりつつあります。
従来の採用手法では出会えない「潜在層」へのアプローチ
ナビサイトや人材紹介は、すでに就職・転職活動を始めている「顕在層」へのアプローチが中心です。一方SNSでは、「良い企業があれば考えたい」といった、まだ積極的に活動していない「潜在層」にもアプローチが可能です。学生が日常的に利用するSNSで、企業の魅力や働く人の想いを継続的に発信することで、潜在層の中に自社の認知を広げ、興味を喚起し、将来の応募者へと育成していくことができます。これは、従来の採用手法では実現が難しかったアプローチです。
Z世代の価値観とSNSの親和性
Z世代と呼ばれる現代の若者は、情報の透明性や企業文化とのマッチングを非常に重視します。彼らは、加工された情報よりも、社員の日常や生の声を写し出す「リアル」な情報に価値を感じ、共感できる企業で働きたいと考える傾向が強いです。双方向のコミュニケーションが可能で、動画や画像を通じて企業の「空気感」を伝えやすいSNSは、こうしたZ世代の価値観と非常に親和性が高いツールです。SNSを通じて企業の素顔を見せることが、彼らの共感と信頼を獲得する鍵となります。
SNS採用とは?2つの主要な活用法「アカウント運用」と「広告運用」
SNS採用(ソーシャルリクルーティング)とは、InstagramやX(旧Twitter)などのソーシャルネットワーキングサービス(SNS)を活用して行う採用活動全般を指します。 その活用法は、大きく分けて2つあります。
アカウント運用(プル型)
自社で公式アカウントを開設し、継続的に情報を発信することで、自社に興味を持つ学生のフォロワーを増やし、ファンになってもらう手法です。企業の魅力を伝え、関係性を構築する中長期的な活動です。
広告運用(プッシュ型)
SNSプラットフォームの広告機能を活用し、ターゲットとなる学生に直接情報を届ける手法です。説明会の告知やインターンシップの募集など、特定の目的のために短期的に多くの学生へアプローチしたい場合に有効です。
SNS採用の7つのメリット
SNS採用に取り組むことで、企業は従来の採用活動だけでは得られなかった多くのメリットを享受できます。コスト面からブランディング、そして入社後の定着率に至るまで、その効果は多岐にわたります。ここでは、SNS採用がもたらす7つの具体的なメリットをご紹介します。
メリット1:低コストで始められる採用広報
SNSアカウントの開設は無料です。ナビサイトへの高額な掲載料や、大規模な合同説明会への出展費用と比較すると、圧倒的に低コストで採用広報をスタートできます。もちろん、広告運用やコンテンツ制作にこだわれば費用はかかりますが、まずはスモールスタートで始められる手軽さは大きな魅力です。
メリット2:拡散力による認知度向上
SNSの最大の特徴の一つが「拡散力」です。X(旧Twitter)のリツイートやInstagramのリポスト機能などにより、発信した情報がユーザーの手で次々と広がっていく可能性があります。一つの投稿が「バズる」ことで、これまで自社を知らなかった多くの学生に一瞬で認知を広げ、企業の知名度を飛躍的に高めることも夢ではありません。
メリット3:企業の「リアル」を伝え、採用ブランディングを強化
企業のWebサイトやパンフレットでは伝えきれない、社内の雰囲気や社員の素顔といった「リアル」な情報を発信できるのがSNSの強みです。オフィスでの日常風景、社員インタビュー、ランチの様子などを投稿することで、学生は企業のカルチャーを肌で感じることができます。こうした情報発信の積み重ねが、独自の採用ブランドを構築し、他社との差別化に繋がります。
メリット4:学生との双方向コミュニケーションによる志望度向上
SNSは、企業からの一方的な情報発信だけでなく、学生との双方向コミュニケーションを可能にします。投稿へのコメントや「いいね!」、質問への回答などを通じて、学生一人ひとりと対話することができます。採用担当者や社員と直接コミュニケーションをとることで、学生は企業に対して親近感を抱き、志望度を大きく高める効果が期待できます。
メリット5:入社後のミスマッチを防ぎ、定着率を改善
メリット3とも関連しますが、SNSを通じて企業のありのままの姿を発信することは、入社後のミスマッチ防止に絶大な効果を発揮します。良い面だけでなく、仕事の厳しさや大変さなども含めてリアルな情報を伝えることで、学生は入社後の働き方を具体的にイメージできます。これにより、「こんなはずではなかった」という早期離職を防ぎ、社員の定着率改善に貢献します。
メリット6:DMによるダイレクトスカウトの可能性
SNS上で優秀な学生や、自社の理念に共感してくれそうな学生を見つけた場合、ダイレクトメッセージ(DM)を通じて直接アプローチすることも可能です。特に、特定のスキルを持つ学生や、特徴的な活動をしている学生に対して、個別のメッセージを送ることで、特別感を演出し、効果的なスカウト活動に繋げることができます。
メリット7:データ分析による採用活動の改善
各SNSプラットフォームには、投稿の閲覧数(インプレッション)や「いいね!」の数、フォロワーの属性などを分析できるインサイト機能が備わっています。どのような投稿が学生に響くのか、どの時間帯の投稿が効果的かなどをデータに基づいて分析し、採用広報の戦略を継続的に改善していくことが可能です。
【注意点】SNS採用の4つのデメリットと対策
多くのメリットがある一方で、SNS採用には注意すべきデメリットも存在します。しかし、これらは事前にリスクとして認識し、適切な対策を講じることで十分に乗り越えることが可能です。ここでは、代表的な4つのデメリットと、それぞれに対する具体的な対策をセットで解説します。
デメリット1:成果が出るまで時間がかかる
SNS運用は、始めてすぐにフォロワーが急増したり、応募が殺到したりするわけではありません。学生との信頼関係を築き、自社のファンになってもらうには、地道な情報発信の継続が必要です。
対策
短期的な成果を求めすぎず、最低でも半年~1年単位での中長期的な計画を立てましょう。「すぐに母集団を形成したい」といった短期的な目標には、SNS広告を併用するなどの使い分けが重要です。
デメリット2:継続的な運用に工数がかかる
質の高いコンテンツを企画・制作し、定期的に投稿し、コメントやDMに対応するには、相応の工数がかかります。他の業務と兼務している担当者が一人で抱え込むと、更新が滞ったり、投稿の質が低下したりする原因となります。
対策
本格的に運用を始める前に、専任の担当者を置くか、複数名でチームを組むなど、継続的な運用が可能なリソースを確保しましょう。投稿のネタ出しや制作を分担する、投稿スケジュールを事前に計画するなど、チームで効率的に運用できる体制を整えることが成功の鍵です。
デメリット3:炎上リスク
不適切な表現や誤った情報発信、内定者への過度な干渉などが原因で、企業の評判を大きく損なう「炎上」に繋がるリスクは常に存在します。一度炎上すると、信頼の回復には多大な時間と労力がかかります。
対策
投稿内容のガイドライン(言葉遣い、公開して良い情報・ダメな情報の範囲など)を明確に策定しましょう。そして、投稿前には必ず複数の目で内容を確認する「Wチェック体制」を構築することが不可欠です。万が一炎上が発生してしまった場合の対応フローも事前に決めておくと、冷静に対処できます。
デメリット4:採用への直接的な貢献度が見えにくい
SNSの投稿が、最終的な採用成功にどれだけ貢献したのかを直接的に測定するのは難しい場合があります。「フォロワーは増えたが、応募に繋がっているのかわからない」という状況に陥りがちです。
対策
運用を開始する前に、SNS採用における目標(KPI)を明確に設定することが重要です。例えば、「フォロワー数」「エンゲージメント率(いいね!やコメントの割合)」「説明会予約サイトへのクリック数」など、目的に応じた指標を設定し、定期的に効果を測定することで、活動の貢献度を可視化し、改善に繋げることができます。
SNS採用を成功させるための戦略的5ステップ
SNS採用を成功させるためには、やみくもに投稿を始めるのではなく、しっかりとした戦略設計が不可欠です。目的を定め、ターゲットを理解し、計画的に運用を進めることで、初めてその効果を最大化できます。ここでは、SNS採用を始めるための具体的な5つのステップを解説します。
ステップ1: 目的の明確化
まず初めに、「何のためにSNSを運用するのか」という目的を明確にします。例えば、「企業の認知度向上」「採用ブランディングの強化」「母集団の質の向上」「内定者フォロー」など、自社の採用課題と結びつけて具体的な目的を設定します。この目的が、今後の全ての活動の軸となります。合わせて、「フォロワー数1,000人」「説明会への送客数〇〇人」といった具体的な数値目標(KPI)も設定しましょう。
ステップ2: ターゲット(ペルソナ)設計
次に、情報を届けたい学生の具体的な人物像(ペルソナ)を設定します。学部、学年、価値観、興味関心、よく利用するSNS、情報収集のスタイルなどを詳細に描き出すことで、どのようなコンテンツが響くのか、どのような言葉遣いが適切かが見えてきます。「全ての学生」に向けた曖昧な発信ではなく、特定のペルソナに深く刺さるコンテンツを目指しましょう。
ステップ3: プラットフォームの選定
設定した目的とペルソナに基づき、最も効果的なSNSプラットフォームを選定します。例えば、企業のキラキラした雰囲気や世界観を伝えたいなら「Instagram」、リアルタイムな情報発信や学生とのフラットな交流を重視するなら「X (旧Twitter)」、会社のカルチャーや事業内容を深く伝えたいなら「YouTube」といったように、各媒体の特性と自社の相性を考慮して選びます。複数の媒体を連携させるのも有効です。
ステップ4: コンテンツ企画
誰に(ペルソナ)、どのSNSで(プラットフォーム)、何を伝えるか(目的)が決まったら、具体的なコンテンツを企画します。企業の魅力を伝える軸(例:「人」「事業」「文化」など)を定め、一貫性のある世界観を保つことが重要です。社員インタビュー、オフィスツアー、1日の仕事の流れ、Q&Aコーナーなど、学生が興味を持ち、楽しめるような企画を考えましょう。
ステップ5: 運用体制の構築と効果測定
継続的な運用を行うための体制を整えます。担当者、投稿の頻度、コンテンツの作成フロー、コメントへの返信ルールなどを決めます。そして、運用を開始したら、定期的に成果を振り返ることが不可欠です。ステップ1で設定したKPIを元に、インサイトツールなどを用いて数値を分析し、「どの投稿が反応が良かったか」「フォロワーは何に興味を持っているか」を把握し、次のコンテンツ企画に活かすPDCAサイクルを回していきます。
【比較】新卒採用で活用すべき6大SNSプラットフォームの特徴
一口にSNSと言っても、その特徴は様々です。自社の魅力やターゲット学生に合わないプラットフォームを選んでしまうと、せっかくの努力が実を結びません。ここでは、新卒採用で特に活用されることの多い6つのSNSについて、それぞれの特徴と採用活動における活用法を比較解説します。
Instagram|企業の雰囲気や世界観の伝達に最適
ビジュアルコミュニケーションに特化したSNS。写真やショート動画(リール)、24時間で消えるストーリーズ機能などを通じて、企業の魅力的な雰囲気やブランドの世界観を直感的に伝えるのに最適です。特にアパレル、美容、食品、デザイン業界など、ビジュアルでの訴求が効果的な企業に向いています。社員のオフショットやオフィスのおしゃれな風景などを投稿することで、学生に「ここで働きたい」という憧れを抱かせることができます。
X (旧Twitter)|リアルタイム性と拡散力で学生との接点を最大化
140文字(日本語)の短文で気軽に情報を発信できるのが特徴。リアルタイム性に優れ、説明会の満席情報やゲリラ的なオンラインイベントの告知などに迅速に対応できます。リツイートによる拡散力は全SNSの中でもトップクラスで、多くの学生に情報を届けたい場合に非常に有効です。ハッシュタグを活用して就活生と繋がったり、カジュアルな口調で採用担当者の「中の人」として親近感を演出したりする運用が人気です。
TikTok|ショート動画で企業の認知度を爆発的に高める
15秒~数分程度のショート動画がメインのプラットフォーム。強力なレコメンドアルゴリズムにより、フォロワーが少なくてもコンテンツが面白ければ爆発的に拡散される可能性があります。企業の認知度を短期間で一気に高めたい場合に最適です。オフィスツアーや社員の特技、仕事の「あるある」などを、トレンドの音楽に乗せて楽しく紹介するコンテンツが人気を集めています。
YouTube|動画でしか伝えられない企業文化と事業の魅力を深掘り
長尺の動画で、情報をじっくりと伝えられるのが強みです。事業内容や製品・サービス紹介、社員の1日に密着したVlog、社長メッセージ、若手社員の座談会など、テキストや写真だけでは伝えきれない企業文化や事業の奥深い魅力を伝えるのに適しています。コンテンツ制作のハードルは高いですが、学生の企業理解を格段に深め、志望度の高い応募者の獲得に繋がります。
LINE|クローズドな環境で候補者との関係を構築・維持
日本のコミュニケーションインフラとも言えるLINEは、一対一やグループでの密なコミュニケーションに適しています。LINE公式アカウントを活用し、説明会参加者やインターンシップ生など、既に接点のある学生に対して、限定情報の発信や選考日程のリマインド、個別の質疑応答を行うのに有効です。オープンなSNSとは異なり、クローズドな環境で候補者一人ひとりと丁寧に関係を構築し、内定承諾までフォローし続けることができます。
Facebook|実名制の信頼性を活かした丁寧な情報発信
実名登録が原則であるため、情報の信頼性が高く、ビジネスシーンでの利用者が多いのが特徴です。フォーマルな情報発信や、OB・OG訪問のリクルーターを探すといった活用に向いています。特に、外資系企業やIT企業を目指す学生、大学のキャリアセンターなどが活用しているケースも多く見られます。他のSNSと比べてやや年齢層が高めですが、真摯な姿勢で企業の情報を伝えたい場合に有効な選択肢となります。
SNS採用を成功させるためのチェックポイント
最後に、これまで解説してきた戦略やテクニックを実践する上で、根底に持っておくべき大切な心構えについてお伝えします。SNS運用は、時に地道で根気のいる活動です。以下の3つのチェックポイントを常に意識することが、SNS採用を真の成功へと導く鍵となります。
「ファンづくり」を意識する
SNS採用の本質は、単なる「募集」ではなく、自社の「ファンづくり」です。一方的に情報を発信するのではなく、学生とコミュニケーションを楽しみ、彼らの声に耳を傾ける姿勢が大切です。そして何より、発信する採用担当者自身が楽しんで運用することが、投稿の熱量となり、画面の向こうの学生にも伝わります。義務感で更新される投稿よりも、楽しんで作られたコンテンツの方が、人の心を動かす質の高い発信になるのです。
継続こそが力
SNS運用は、一朝一夕で結果が出るものではありません。デメリットでも触れた通り、成果を急ぐあまり、数ヶ月で更新が止まってしまうアカウントが非常に多くあります。しかし、SNSで企業の信頼を築くには、地道な発信の「継続」が不可欠です。すぐに「いいね」やフォロワーが増えなくても、焦る必要はありません。中長期的な視点を持ち、コツコツと誠実に情報を届け続けることが、数年後の大きな資産となります。
常に改善を
「やりっぱなし」にしないことが、SNS運用を成功させる最後の秘訣です。各SNSに備わっているアナリティクス(分析)機能を定期的にチェックし、「どんな投稿が伸びたか」「フォロワーはどんな層か」「どの時間帯の反応が良いか」といったデータを客観的に把握しましょう。そのデータに基づいて、「次はこうしてみよう」という仮説を立て、実行し、また結果を検証する。このPDCAサイクルを回し続けることで、運用の精度は着実に高まっていきます。
SNSを活用した採用戦略の立案・実行はYUTORIにご相談ください
「SNS採用の重要性は理解できたが、何から手をつければいいかわからない」「継続的な運用リソースがない」「SNSだけでなく、採用活動全体を根本的に見直したい」このようなお悩みをお持ちの採用担当者様は、ぜひ株式会社YUTORIにご相談ください。
YUTORIでは、Webマーケティングを主軸に、企業の採用課題を包括的に解決する「採用コンソーシアム」という独自の支援サービスを提供しています。
採用コンソーシアムは、媒体選定、原稿作成、HP制作、広告分析、LINE運用など、各分野の専門家がチームを組んで貴社の採用活動を多角的にサポートする仕組みです。貴社の採用チームの一員として伴走し、現場の課題に即した最適な戦略を立案・実行します。
短期的な成果はもちろん、中長期的な視点で貴社内にノウハウを蓄積し、持続可能な採用力を構築することを目指します。部分的な課題解決から全体的な採用力強化まで、状況に応じて柔軟にサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。